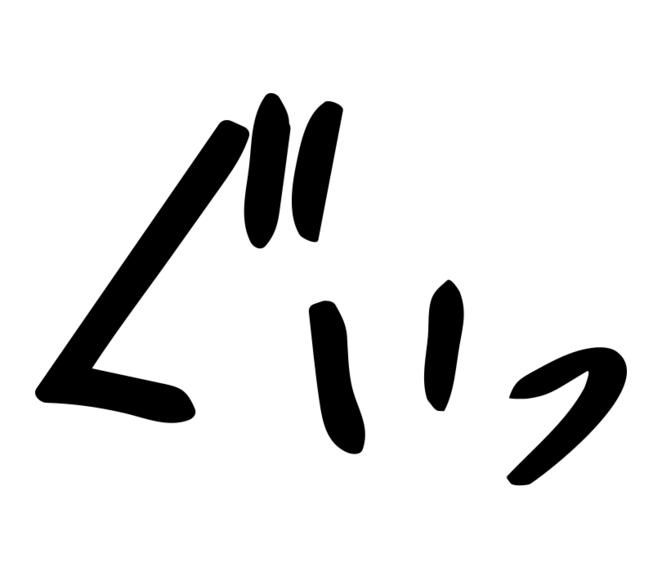斉宮優理は、とにかく人と喋る事が苦手である。
どのような事を言えば良いのかいつも判断がつかない。人に話し掛けられたとき、どのように返せば良いか分からない。
毎日学校で、そんな優理を会話に入れてくれるクラスメート達にさえ、まともに話が出来た覚えがない。
例えば今日の話題であった、
「A先生よりB先生のほうがかっこいい」
というテーマに、他の女の子たちは同意見なり反対意見なりを思い思いに話していたのに、優理は相槌を打つことすら出来ずにいた。
「ねえ、優理は?優理はどう思う?」
誰かが振ったその質問を、優理はかなり『ずるい』言葉で乗り切った。
「うーん……どっちも格好良くて、私はどっちの方がって選べないかな……」
曖昧に濁したその言葉に、数人が笑い、数人がつまらなそうな顔をする。それだけで、優理の心臓は凍り付きそうになった。
人と話すと、話した相手からは何らかの反応が返ってくる。その反応が自分に好意的でないことが、優理には恐怖の対象だったのだ。