車がガタンと揺れて、僕は目を覚ました。
座ったままで寝たせいか体の節々が痛んだ。長く油を差していない歯車のように、ギシギシと軋む。
陽のそそがない車内は暗く、多くの未だ少年少女と呼べる歳の子供達が詰め込まれていた。僕とて、その一人である。
誰かが啜り泣く声が耳障りだ、人の熱気が気持ち悪い。
車内の環境を一言で言うならば……犯罪者や奴隷を運ぶ車だろうか。つまるところ乗り心地は最悪で、漂う雰囲気は陰鬱だった。
車がガタンと揺れて、僕は目を覚ました。
座ったままで寝たせいか体の節々が痛んだ。長く油を差していない歯車のように、ギシギシと軋む。
陽のそそがない車内は暗く、多くの未だ少年少女と呼べる歳の子供達が詰め込まれていた。僕とて、その一人である。
誰かが啜り泣く声が耳障りだ、人の熱気が気持ち悪い。
車内の環境を一言で言うならば……犯罪者や奴隷を運ぶ車だろうか。つまるところ乗り心地は最悪で、漂う雰囲気は陰鬱だった。



起きたのか、ルシュト





……うん?


隣に座っていたササムが、ジロリとこちらを見た。暗闇の中で、彼の瞳は猫のように光って見える。



まぁた寝てたんだろ





ああ





戦いに行くってのに……緊張感がねぇな





緊張感なんてものは多分、どっかに置き忘れてきたんだよ、僕は





はは、だろうな


ササムは僕の軽口に小さく笑った。
ササムだって余裕じゃないか、と言おうとして、僕は彼の手が震えていたのに気がついた。



あ……悪い





……いや


僕が見ていたのに、ササムもまた気づいてしまった。もう片方の手で抑えていたが、震えは大きくなるばかりだった。
はぁ、と彼はため息をつく。
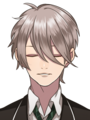


……俺ら。ついてないよなぁ





何が?





だって、初陣なのにさ


僕の通う学校は軍部に属していて、ここに通う者は、学生であると同時に兵士だった。
一日の半分を訓練に費やし、半年間の研修の後、学校に通いつつ順次任務に就いていく。
危険な任務もありはするが実際に戦争に駆り出されることはないし、絶体絶命の状況になることはまずない……はずだった。
しかし、第六訓練隊、そう銘打たれた僕らに課された初任務は、



魔都の奪還、なんて





といっても本隊のサポートだろ





まあ、そうだけどさ


しかし、危険なことに変わりはなかった。
魔獣に奪われた土地――魔都。
それを奪い返しに行くのは、敵地に乗り込むことと何ら変わりない。
それこそ警護や点検、巡回などの任務もある中で、どうしてよりによって、と。
考えても仕方のないことだ。しかし考えずにはいられない。
なぜならこの車が止まれば、化け物と殺し合いをしなければならないのだから。
殺すか殺されるかの争いを。
そして帰るころには、この窮屈な車内が少なからず快適になっていることを――それが示す意味も含めて――僕たちはよく知っていたのだから。



俺は、怖ぇよ





……うん





うんって、さ……
何でお前はそんなに落ち着いてられるんだよ、ルシュト


ササムは僕の名をいささかの非難を込めて呼んだ。



何でって、それは……





それは?


いつの間にか、車内のすすり泣きが止んでいた。
誰かが、誰もが僕の言葉に耳を向けているような気配を感じた。
期待させて申し訳ないが、生き残れる秘訣だの方法だの、教えられるようなものは何もない。
僕は小さく肩をすくめた。



訓練でなんとかなったから、本番でも大丈夫かなって





……そんなわけあるかよ


ササムでない他のやつが、気楽なこって、と言うのが聞こえた。その声は揺れていた。



お前のために言っておくがな、実戦と訓練じゃ、まるで違うと思うぜ


ササムは僕に釘を刺すように僕に言った。
そして、僕がそのことを“改めて”悟るのは……それより少し後のことだった。
それからも暫く車は動き続け、もう三度ほど跳ねた時だったろうか、突然グルングルンと唸りを立ててその足を止めた。
車内に一瞬で緊張と恐怖とが奔る。一旦止んでいた泣き声がまた上がる。
騒がしいな、と言おうとしてやめた。
善意ではなく、余計に煩くなったら嫌だったから。
後ろのハッチが、静かに開けられる。
突然に差してきた光に僕は目を細め、泣き声は絶望に染まった。すでに仮面や装甲を纏った兵士が、僕たちに怒鳴るように言った。



第六訓練隊、降りろ


返答もなく、誰もがその命令にすぐさま従った。
これからの苦痛の前に、命令違反という罰による苦痛も重ねたいなどという物好きは、流石にいないらしい。
バタバタと皆、車を降りて行った。
あたりを見渡せば、一面の森だった。
息も詰まるほどの濃密な緑が目に痛いほどだ。
しかし、そういうものなのだ、魔都というのは。
魔獣に奪われた瞬間から、その土地は森に侵食され始める。
人の住めぬ土地へと、変貌していくのだ。



ああ、そういえば……


昔、どこかの宗教家が魔獣を”神の使い”と呼んだ。
人間に穢された土地を、森に変えて浄化しているのだと。
……その者がその後一体どうなったのかは知らないが、たとえそうだったとしても、人間は魔獣を殺すのをやめられないだろう。
魔獣は、”有用な物質”なのだから。
欲にまみれ突き動かされて、止まることなどできないのだ。
と、そこまで考えて、頭にふと浮かんだ疑問があったが、



おい、早くしないと怒られるぞ





あ、ああ……


ササムに声をかけられて、それは淡く霧散した。
ホルスターに付けられていた仮面を外し、別の車に積まれていた各々の装備を受け取る。
厚さ6ミリほどのプラスチックのような仮面と、防具に似た薄くも硬い装甲。
忘れてしまった疑問を振り返っている暇はなかった。
総重量10キロほどのこれらが――僕らが今から頼れるものの全てなのだから。



装着しろ


号令とともに、僕らは一斉にそれらを付けた。初任務の緊張はあるだろうに、しかし誰の腕も指先も、手慣れた作業に迷うことなく動いていた。
レッグフレーム、アームフレームの順にパチリ、パチリと嵌めると、僕は真っ白な仮面を付け、固定するようにヘッドギアを上から被った。
視界が白濁する。
全ての装着が終われば、続けて腕や指、脚の動作確認を行なう。
軽く屈伸、そして手を握り、開く。
よし……問題ない。
あらかじめ着ていた“配電盤スーツ”を神経回路の代替として、仮面が受信した脳信号は過不足なく装甲へと行き渡っている。
機械に過ぎないものたちが、体の一部になったような感覚が確かにあった。
——認証コードの確認を——
脳内に声が響いた。
仮面とそこに組まれたプログラムが僕の脳に干渉しているのだ。
この感覚だけは、いつまで経っても不快で慣れない。



R、L、F、N、W、W、B、……


アルファベットの羅列を呟くように言う。このコード自体に大した意味はない。
これは本来、声紋認証のための作業に過ぎない。



……、H、D、C、N、C、T


言い終わるとともに、仮面は再び話し出した。
——確認、完了しました、仮面を起動します——

僕の視界は曇った白から透明へと変わった。
眩しさに目を一瞬細めて、それから周囲を確認する。
奇妙な動きをしているものが一人。
俺の白いままの仮面と違い、赤い模様の入った仮面をつけているので、それが誰かは、すぐに分かった。



何してるんだよ……ササム





何って、動作確認に決まってるだろ。


その声には、もはや怯えもなければ憂いもなかった。
いたって普通で、到底戦場に向かう者のそれとは思えない。
右目に、仮面の通信を通してササムの顔が映る。



よし、大丈夫だな


その顔は、笑っていた。



お前、もう平気なのか





何が?





何がって、さっきまで、あんなに怖がっていたのに……





ああ、それなら”仮面”つけたら吹っ飛んじまったよ。スゲェよな、仮面って!





……そうだな


ササムの、朗らかな笑い声が聞こえて、僕は顔が険しくなりそうなのを何とか堪えた。
分かっていた。
分かっていたはずだった、仮面はそういうものだと。
仮面型装具および装身具一式。
そんな正式名称を持つ、対魔獣、対軍団兵器。
魔獣からできた、化け物の装甲。
それは、どういう原理かは理解していないが、人の怯えや恐怖を消し、その本性——破壊性やら凶暴性、生存本能なんかを露わにする。
そうして、弱さも全て曝け出してしまう。
……だから嫌だ。だから、嫌いだ。



じゃあ、行こうぜルシュト





……ああ


膨れ上がりそうになる感情を、爆ぜないように、ばれないようにと抑え込む。
嗚呼、いっそ何もかも、誰もを——



ルシュト、どうかしたのか?





いや……何でもないよ


聞いてきたササムに、誤魔化すように笑った。
僕の視界を一瞬、黒色が奔った気がした。
