――窮屈な箱庭に住む私たち――
――窮屈な箱庭に住む私たち――

もし私たちが天に愛されているなら、『生』はあれども『死』はないはずだ。わざわざ、苦しめる必要はないのだから。
だが残念なことに、生き物には『死』がある。
現に、胸やけするような灰色のスモッグを吸い込み、毒の呼気を出して命を削っているのだ。



なんで、私は生きてるのかしら


人生に羅針盤はない。
だからこそ、方角もない海原で彷徨うばかりだ。
そうやって気を取られているうちに、『生』の意味なんて考えなくなってしまう。私はそれが嫌だった。
何かしら『生』の意味がないと、息をしていることすら無駄に思えてしまう。
人間の目のように、ギョロリと光る太陽を見上げる。
ああ、崇高な太陽――あなたは46億年間、ずっと私のような愚劣な生き物を見下してどう思っていたのかしら。
すぅっと溜息のようなそよ風が頬を撫ぜた。太陽でさえも、あきれ果てているというのか。



生きている意味なんて、考えなくていいんです


返ってきた声は、心臓が凍りつくほど冷たいものであった。私の隣に佇んでいたアンドロイドが発した声だ。それが何となく、人間を軽視した言葉のように思えて苛立ちを覚えた。
彼はきっと、「生きている意味」を知っているのだろう。
そう、知っていながらも濁世で溺れ生きる人間をよそに、高みの見物をきめこんでいるのだ。
見えない鉄格子の中で怯えすくむ私たちは、必死に鉄格子の鍵を探している。



何よ


ふんと鼻で笑う。
息さえしていない機械のくせに、と蔑視する。



ああ、そうね
そもそも生きていないアンドロイドなんかとは無縁の話題よね
ごめんなさいね





…………


すると、よく観察しなければわからない程度ではあるが、彼の眉頭がピクリと動く。
ほら、こうやって私を小馬鹿にしたような顔をする。
彼――ニビは伏せ目で一瞬こちらを伺い見たが、すぐに目を逸らした。
私が生まれたときから彼は変わらない。
こうやっていつも金魚の糞のように私の後ろを死守して、電柱のように薄汚い目で監視する。



木偶の坊、役立たず


彼に吐いた暴言は、私の乾いた感情と連動していて、異様に湿度の低いものだった。
行き場のない怒りは、毎日毎日目の前の非生物へぶつけてしまう。
それが日常茶飯事で、罪悪感など微塵もなかった。
大丈夫、きっと彼のガラクタを集めたような心臓には刺さらないだろう、と思っていたのだ。



木偶の坊なりに、貴女を心配しているのですよ


ずいっと顔を近づけてきた彼に、驚きを隠しきれなかった。
彼はいつも私と距離を置いていたからだ。それは物理的な距離でもあり、精神的な距離でもある。
現に彼は、私にはミサという名前があるのに、今まで一度たりとも私の名前を呼んだことはない。それに、肌という肌に触れたこともない。
だからこそ、今はじめて気づいたことがあった。
顔に彼の吐息があたる。息を、していたんだ……機械のくせに。
至近距離で目が合う。
どうせ光電管のちっぽけな目だろうと踏んでいたのに、光沢のある大きな目と、それを縁どる長い睫毛が備わっている……機械のくせに。



意味が分からない……


歯ぎしりをしながら睨み上げた後、そっぽを向いた。
そこで私は、いつものように考えることをやめてしまった。うまく彼に丸め込まれているような気がしてならない。
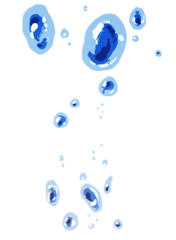
物心ついた時から、私の思い出には彼が染みついていた。
シャツについたチョコレートのように、厄介で簡単には落ちない記憶でもある。
友人は彼を美しいと評するが、私にはそう思えなかった。
漂白剤のように白い肌、
ヘドロのような髪、
突然死して血が集まった魚のような目。
――まあ、私の審美眼がないだけの問題かもしれないが。
彼の容姿さえも不快なものにしか例えられない私は、心底彼を嫌っているのかもしれない。
そんな彼は、一人遊びが大好きな私の教育者でもあった。私が飛んでいたトンボをつかまえ、羽をちぎりとって本にペタペタと貼っていると、



弱いものを大切にしないといけませんよ


と静かに叱りつけたこともあった。
「なんで」と尋ねる幼い私に、



あなたがそのトンボだったら嫌でしょう?


と棒読みで諭してきたのだ。
「わたし、トンボじゃないもん。にんげんだもん。
トンボじゃないもん!」
当時の私は、そんな的外れな答えを連呼して泣き叫び、彼を困らせていた。
『もしトンボだったら』という仮定は、必要ない。
そう――人間として生まれてきたのに、なぜ弱い者のことなど考えなければならないのか。小さい頃の私はそう思い込み、そこで思考停止していたのだ。



ご主人、カマキリを踏んでいますよ


我に返り視線を落とすと、そこには胴体をつぶされて痙攣するカマキリが横たわっていた。途端に気持ち悪くなり、足を退いてはち切れんばかりに振り回す。
――気持ち悪い、何で私の歩く場所に出てきたのよ。
その時の私は、理不尽に踏まれたカマキリの気持ちなんて一塵も考えていなかったのだ。



そ、それがどうしたの? 生きてれば知らないうちに虫を踏むものよ


思い返してみれば、あれから私は変わっていない。
変わろうとも思わない。
だって、人間がこの世界のカーストでは上位なのだから、大きい顔をして当然じゃない。何が悪いの?



『可哀想』です


可哀想、だって?
思わず、目を瞬かせた。
彼の口から感情を表現する意見が出ることは、今まで一度たりともなかったからである。彼はしゃがみこみ、潰れてしまったカマキリを凝視した。



このカマキリも、そして……貴女も


ゾクリと背筋が凍りついた。ゆっくりと彼は振り返り、鋭い目線で私を射抜く。
あれ、なんで足の指に力が入らないのだろう。
怯えているの? この私が?
――人間の、私が?



……はぁ?


もしかして――この機械は、人間の私を嘲笑っているのか?
いいや、そんなわけはない。だって、人間が一番偉いのだから……あれ? 人間って、どの部分が機械よりも勝っているのだろう――?
生理的に肌が粟立つ。これが機械への畏怖だと気づくのに時間がかかってしまった。
しかし人間である私が機械に怯えるなんて、「常識的に」許されない。
彼の地を這うような声は、私の骨を振動させ、さらに恐怖感を煽る。



このカマキリや、幼い貴女が羽をむしりとったトンボはある意味、貴女なんですよ


立て続けに彼は言葉で私を畳みかける。



なぜ貴女は罪を重ねていくのですか
生きていると犠牲がつきものですが、貴女は反省もしない――


ニビは空を指さし、少しだけ口端をつりあげた。



太陽は、四六時中貴女を見守っています
そして、この僕も……



ニビの奇行から数週間経った。
あれ以来きちんと睡眠がとれていなくて、目の下には青いクマが居座っている。



おはよう……あれ?


目をこすりながらリビングへ足を踏み入れ、すぐに異変を感じた。
そう、ニビがいないのだ。



え……ニビ? ニビ!


1階から2階までくまなく探すものの、彼の姿はなかった。
あの几帳面すぎる彼が置き手紙もなく外出するなんてありえない。
迷わず外へ出た。すると、更なる奇怪な現象が起こっていた。



誰か、誰かいないの!?


叫びながら見慣れた道路を走る。だがやはり、人っ子一人いない。
喉が締め付けられ、息があがる。
苦しい。助けてほしい。
この際、ニビでもいいから――! いつも一緒について回ってたくせに、寝る時だって寝静まるまで傍にいたくせに!
ずっと、どんな時でも、見捨てないでくれたのに……。
とうとう不安が最高潮に達して目頭が熱くなる。アスファルトに雫が弾けて原型がなくなる。でも、私の心のほうが壊れて、原型さえ保たれていないはずだ。
鼻をすすりながら天を仰ぐ。すると、ありえない光景が広がっており、驚きのあまり言葉を失った。



あ……


太陽が2個もある。いいや、違う。あれは――。
太陽の正体に気づいてしまった途端、強い地震が起こった。きゃあっという悲鳴を打ち消すほどの地鳴りが耳をつんざく。

と、天から悦に入った笑い声が降り注いだ。
すると空に亀裂が入り、青空が真っ黒に変わる。
同時に、太陽――否、あれは目だ。それも、相当大きな人の目。
巨人の目だけではなく、顔までもが浮かび上がる。
巨人は、口を三日月型に変えた。
ビルくらいの大きな手が伸びる。それが、尻餅をついて震える私の襟をつかみ、引き上げた。
首がぎゅうっと締まり、苦しさのあまりにもがきまくる。それはまるで、絞首刑のようであった。



くる、し……!





そうか、苦しいか
だが、お前が踏みつぶしたカマキリの苦しみと比べたら、たいしたものではないだろう


確かにそうかもしれない。これは天罰覿面というものだ。
今まで感じたこともなかった罪悪感がどっと湧き上がる。今まで目隠ししていた感情が、この謎の巨人によって解かれるのだなんて。
この巨人は誰?……酸素不足になり、ぼんやりとした頭が問いかけた。



せっかくニビがお前を諭していたというのに、お前は傲慢にもそれを無視した
そもそも、お前は『人間』ではないというのに……





どういう……こと……?


頭のてっぺんから冷水を浴びせられたように感じた。
なぜ、巨人の口からニビの名前が出るのか。
それに、私が『人間』じゃない? その意味が分からず、フリーズする。



お前は、私の作った仮想世界の『サンプル』だ
いわゆる、お前の住んでるこの世界は仮想空間
そしてお前はランダムの性格を組み合わせてつくられた仮想人間ということだ
まあ、一番人間に似せることができた傑作だとは思っていたが――ただの失敗作になるとは……


はぁっと、巨人――否、人間の溜息が降りかかる。それは以前、そよ風だと感じていたものであった。



お前は確かに人間らしかった
しかし、少しばかり『謙虚さ』というものと、『罪悪感』、『反省』というものが足りなかったのだ
私の分身であるニビを仕わせても、全く成長しなかった


期待外れだ、と低い声が私の鼓膜を殴りつけた。冷や汗が額から流れ、目に伝う。そして目からは涙が流れ、顎へ流れていく。
私がただのサンプルだったなんて、信じられるものか。16年間の思い出がぎっしりとつまっているのに。
それなら、ニビと過ごしたあの時間も嘘だったのか。煩わしいと思い込んで、彼を引き離していたけれども、実は一番心地よい時間だったのに。
私は鮮明に覚えているわ。彼が初めて笑ってくれた瞬間、それは私が気まぐれで彼の似顔絵をあげた時。目を見開かせた後、「上手ですね」と微笑んでくれた。あの微笑みさえ、嘘だったというの?
巨人のもう片方の手が視界に迫る。
もしかして私は――このまま殺されるの?
心まで殺され、思い出さえ『無』にされるの?



いやあああ!!


一気に恐怖感が募り、手足を暴れさせた。
死にたくない、死にたくない、死にたくない……!
例え自分がサンプルとして作られた人工物だとしても、今まで生きてきた……はずなのだから。このハリボテの世界で。
恐怖感とはすなわち、喪失感なのだ――心の奥底で、ニビの声に似たささやき声が聞こえた。



哀れなサンプルだ
お前が今まで犯してきた罪を償ってもらおう


その瞬間、走馬灯のように脳裏に映像が走る。そして五感で耐え切れない責苦が一瞬で押し寄せた。
悠々と空を飛んでいると、視界がぐるりと変わる。「きゃはは」という声が脳を揺らすと、背中が抉られる。背中が、痛い。
一旦ブラックアウトした後、アスファルトが視界に入る。地面を這いつくばっていると、体が圧迫される。全身がものすごく痛い。頭上から、「生きてれば知らないうちに虫を踏むものよ」という声がとどめを刺す。
延々と私が犯してきた罪が自分に降りかかる。悲鳴など出ないほど、疲労困憊していた。
すると最後に、ニビが現れる。あ、と乾いた声を漏らし、手を伸ばした。
あれ……? 私の手が――メッキが剥がれて、コンセントが這い出てる。伸ばした手を引っ込めて、嗚咽を漏らした。
ニビは口の右端を上げ、目を細めた。
「木偶の坊、役立たず」
心が、死ぬほど痛かった。
ガラガラと、メッキが更に剥がれ、体が崩れ落ちた。
奈落の底へ落ちていくとは、こういうことなのか。
ああ、これらの痛みはあのトンボやカマキリたち、そしてニビが受けた痛みだったのか。



ごめんなさ……い……


自分がその身となって初めて痛みが分かるとは、本当に愚かなサンプルだったんだ。
何て酷いことをしてきたのか。
謝っても償えない罪だと知り、傷が刻み込まれた体の疼きに耐えながら泣き叫んだ。



ごめん。ごめんなさい……


しゃがれた声でも、一番言いたかった言葉を一言一句絞り出した。
機械のあなたでも、こんなにも痛かったのね。
メッキの下には、血であふれた心臓があったのね――。
視界が白いヴェールに包まれ、疲弊したせいか思考が途切れそうになった。
すると、懐かしいあの声が耳元で聞こえた。



ご主人、ご主人……いや、ミサ


重い瞼を持ち上げると、今まで見たことのないほどの柔和なほほえみを浮かべたニビがいた。
彼は、かろうじて体と呼べる私の残骸を抱きしめた。
皮肉にも、それが生まれて初めて彼から受けた名前呼びと、抱擁であった。
そして本能のままに嗚咽を漏らす私は、今までで一番人間らしく思えた。
――全ての罪を償った私は、そこで意識が途絶えてしまった。
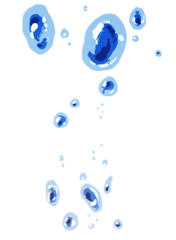



あ、起きたかい?


朦朧とした意識のヴェールがはがれていき、駆け寄ってきた白衣を着た老人を見やる。
するとその老人は、にぃっと笑って金歯を見せた。



おはよう、アンドロイド君
――いや、ニビ君と呼んだほうがいいのかのぉ
仮想空間で疲れただろうに
こっち(現実)とあっち(仮想空間)の行き来は容易ではないからのぉ


今、彼は何と言った?
『ニビ君』?
いや、違う。私の名前は――。
「はい」
口が勝手に動き、ぎょっとした私は「違う、違うの!」と声を出そうとしたが、不思議なことにその声は出すことができない。
私という意志があるのに、主要の意志に邪魔されているのだ。
そこで気づいてしまった。
私は、この主格である『ニビ』と混ざり合ってしまったことを。
そして、どう頑張っても、『私』という名前を思い出せないということを。
渾身の力をこめて口を動かそうと努力する。
確か、私の名前は『ミ』がついたはずだ。ただ、そこからが思い出せない。
「ミ、ミ……」と、蚊の鳴くような声を発したところで、激しい頭痛が襲い、脳内で私は金切り声をあげた。



違う、お前はもう『ニビ』なんだよ。
お前はあの時、この『ニビ』を享受してしまった。慈悲深く、消えるはずだったお前を助けたこのニビに感謝しろ


ガツンと鈍器で殴られたような感覚に陥る。
頭に直接響くその声は、明らかにニビのものだった。
するとどうしたことだろう。私以外の金切り声が脳内で木霊する。
「助けて、私をここから出して!」
「俺は何も悪くない。お願いだから許してくれ」
「サンプルだなんて、知らなかったのよ!」
そうか、そういうことだったのか。様々な断末魔を聞き、瞬時に理解してしまった。
私以外にも、被害者は数多にいるのだ。それだけではない。彼、『ニビ』に取り込まれると、もう二度と外へ出ることはできないし、「自分」を完全には忘れることができないのだ。
まさに、生き地獄。
「私を、騙したのね……」
深淵のような絶望感を感じきる前に、自己防衛本能から『私』は考えることをやめて、『ニビ』に溶け込んだ――。

*hana*さま、ご精読ありがとうございました。そして感想もいただけて嬉しく思います。捻くれた性格で小生意気なミサですが、可愛いと思っていただけて良かったです。
うつろさん、感想を書いてくださりありがとうございます!
ニビがかっこいいと言っていただけてとても嬉しいです。世界観まで褒めていただけて、至極光栄に存じます。
ちびねこさん、こちらからも感想を書いていただきありがとうございます!
まさにそこに着眼点を置いていただきたかったので、大変嬉しく存じます。にんげんはロボットと違った恐ろしさがある、ということを表現したかったので、そこに言及していただけて書いたかいがあったと思いました。
Twitterでも感想書いたけど、書ききれなかったから(A;´・ω・)
こっちでも。ニビとミサの生きる意味。共存してしまったけど、二人ともの意識が残るって事にはならないのね…少し片方が消えるという事に寂しさも感じたかな。