猫又は気まぐれに前脚をなめながらそう呟いた。
もう片方の脚で押さえつけた獲物は逃がさないように、ぐっと力を込めて。すると、脚の下に敷かれた小さい獲物が、蚊の鳴くような声でうめき声を上げた。
そうだ、この状況には覚えがある。まったく似た状況を、猫又も体験していたのだ。



嗚呼――そうにゃ。思い出したよ。





ぁ――ぅ。


猫又は気まぐれに前脚をなめながらそう呟いた。
もう片方の脚で押さえつけた獲物は逃がさないように、ぐっと力を込めて。すると、脚の下に敷かれた小さい獲物が、蚊の鳴くような声でうめき声を上げた。
そうだ、この状況には覚えがある。まったく似た状況を、猫又も体験していたのだ。



そういえば昔、ここで蛇の親子を食べたっけにゃぁ。いつの頃か忘れたけど、あの時の肉の味は憶えているよ。





神様といっても、下民の拙い信仰心で祀り上げられただけの張りぼてみたいなお粗末なものだったにゃあ。





けどまあ……不思議なことだけど、あの時食べた子どもが生きていただにゃんて。美味しいところだけいただいて、食べ残しはしたかもしれにゃいけど





……その残りに魑魅魍魎の魂でも宿って甦ったのかい?アタシが憎くて?恨みで鬼にでもなったっていうのかにゃ?精霊が?





にゃははははははは!


猫又の笑い声が沼地に渡る。
その声を、蛟鬼はぼんやりとした意識の中で聞いていた。
蛟鬼もまた遠い昔のことを思い出していた。鬼になってから昔のことは殆ど忘れてしまったけれど、鬼になった日のことは少しだけ覚えている。
母を失い、大化け猫に食い荒らされた自分は、それでも生きることに執着していた。その理由は、もう憶えていないけれど。
今だってそうだ。体を半分つぶされて意識が薄れているというのに、口が勝手に動いてうわごとを呟く。



……す……て





うん?にゃんだい、命乞いかにゃ?それとも誰か助けを呼んでるのかにゃ?





……う





ふふふ……にゃはは!アタシは天下の猫又様だよぅ。命乞いなんて無駄だし、誰が来たって返り討ちにゃあ!





にゃはっにゃはははー!





――ししょう







にゃッ――!?


その時、猫又は大きな衝撃に見舞われた。かと思えばぐらりと視界が揺れる。突然、体のバランスがとれなったことに驚いて猫又が脚元を見れば、そこに踏みつけていたはずの子鬼がいなくなっていた。
というか、脚先もなくなっていた。
夜闇に紛れてなどと比喩的な意味ではなく、直接的な意味で。その証拠に訳の分からない痛みが追って襲いかかる。



……は?はニャァぁああ!?





にゃっ、アタシ、アタシの脚が千切れ……っ。にゃ、にゃんでにゃぁあ!?


脚を失った猫又はひっくり返り、地面の上でのたうち回りながら喚く。混乱する彼女は、傍らに千切られた脚の一部が転がっているのに気づきもしない。その脚を蹴り飛ばして歩み寄って来る存在がいたことも――。



手遅れ……にはならなかったか





――だっ、だれにゃ!?


第三者の声が聞こえたのに、猫又はようやく気付く。
真っ先に目に入ったのは丈夫な蔦で編まれた笠――それを突き破って頭部から伸びた角。破れた蔦の網目から覗く鋭い目と合うと猫又は畏怖の念を覚えた。



カクヨノの……鬼。


カクヨノ山の土地は東西に分かれ、それぞれ精霊と妖怪が納めていることは他所の地を渡る化け猫も知っていたことだった。けれど、西側を治める頭の鬼はとんだ出不精だと聞いていた。縄張りを守る結界に甘えて滅多に姿を現さないと……。



今度は会えたな。


鬼は猫又に目を向けて、臓腑に響くような重たい声で似つかわしくないことを言う。手にはその身の丈ほどある太い金棒を握り、反対の手には見失ったあの子鬼がぶら下がっていた。
鬼の言葉の真意こそわからないが、その光景を見ただけで、猫又は自分が置かれた状況を理解した。
此奴はあの子鬼の仕返しに来たのだ――と。



察しがいい奴だ。なら自分がとるべき行動もわかっているだろう。





うにゃ……ああ、わかっているさ。すぐに出ていくにゃ。それでお前も満足だろう?


まさか出会うはずがないと今回も高をくくっていた猫又だが、カクヨノ山の鬼と対峙したことで、それは愚かな考えだったと悔い改める。そう反省した様子を見せてこの場から逃れようとしたわけだったが……。



……命乞いすらまともにできないとは、甚振る面白みもない猫めが。





――え?


鬼王丸は呟くと片手に持った金棒を猫又めがけて振り上げた。置いただけで地面にめり込むほどの鉄の塊が、頭上にあるのを猫又は茫然と見る。ぽかんと口から出た声が猫又の最期の言葉だった。



お前のような小さき魂は、鬼の業火で焼き尽くしてやろう!


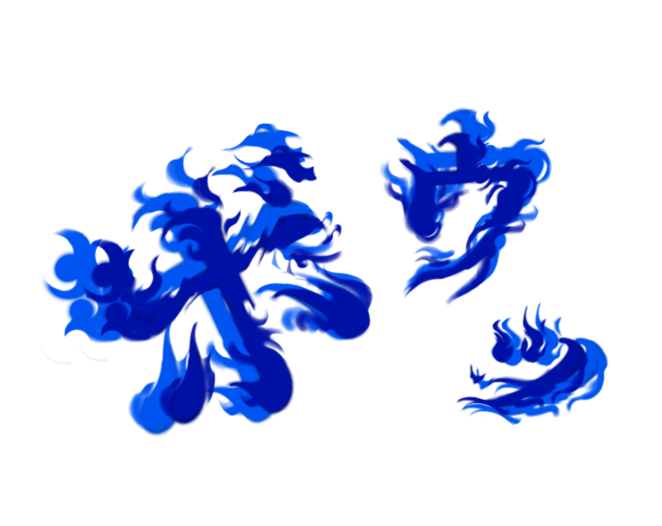

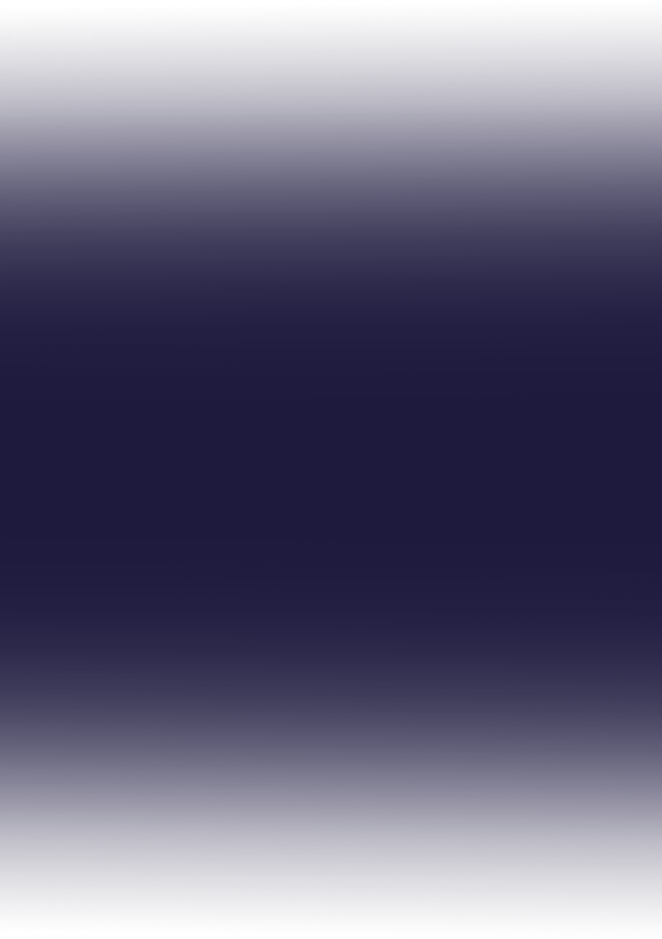




う……ぅん。


蛟鬼は途切れ途切れの意識の中、これで何度目か目を覚ました。
不思議なことに体の痛みが和らいでいる。それになんだか温かい。誰かの背におぶられているのだと分かると、とその相手が誰なのかも分かった。
広くごつごつとした背の主も、蛟鬼が目を覚ましたことを察して言う。



……今度は自分で助けを求めたんだ。その身体は小屋に戻ったら直させてもらう。文句は言うなよ。


鬼王丸の言葉に蛟鬼は、また自分は命を落としかけたのだと思い出した。すると昔の記憶が頭をかすめる。それを振り払うように蛟鬼は身じろぎをした。



どうした。





……師匠……血なまぐさい……あと、獣くさい。





我慢しろ。





……あと遅い……。





助けてもらっておいてその言い草か。





……師匠。





……なんだ。





ごめんなさい……。


振り絞るような蛟鬼の声だった。鬼王丸からの返事はなかったが、蛟鬼の怪我に気を使って山道を歩く足取りはゆっくりだった。
山頂の小屋につくまでまだ時間はかかる。蛟鬼は静寂に耳を傾けながら夢の中へと意識を失ったのだった――。
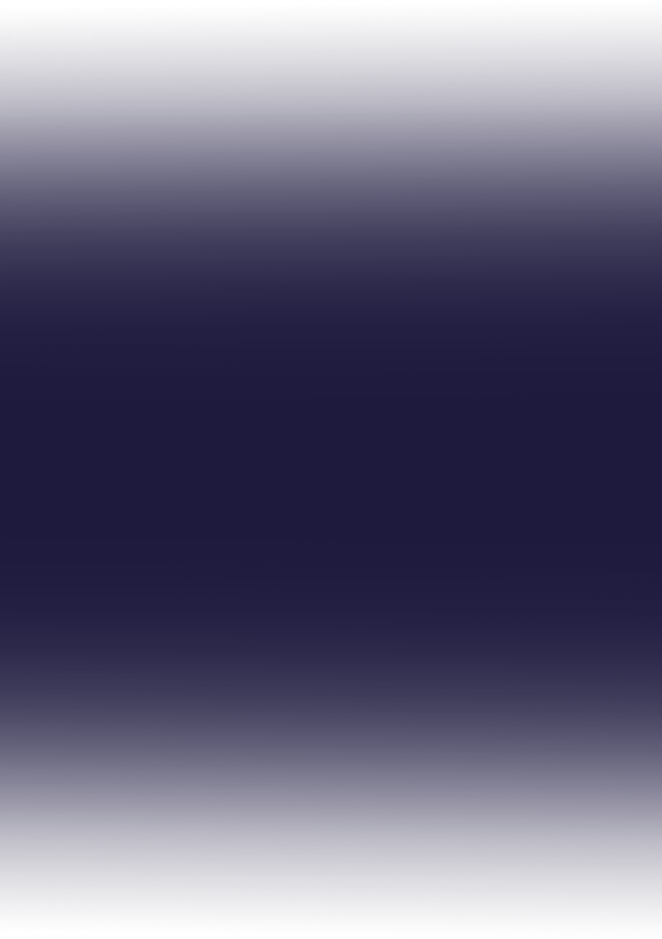
目が覚めると、自分は蛇神の子ではなくなっていた。
それどころか精霊の類からも外れてしまったのだとわかったのは、清ゝしかった精気が禍々しい妖気に変質していたからで。手足の肌に薄い鱗が残っているものの、それより目立って額から角が突き出した自分の顔が川の水面に映っているのを見れば、理解せざるを得なかった。
――これは鬼だ。自分は鬼になってしまった、と。
絶望したかと問われれば、きっとそうだったのだと思う。だって、現実を目の当たりにする自分を見守るもう一人の鬼が、傍らで深々と頭を垂れていたから。



蛇神だったお前を鬼に変えたのは儂の勝手だ。枯渇しかけたお前の魂を鬼火にし、その身体に灯さなければとうにお前は死んでいた。お前の本心が母と同じ死を望んでいたとしても、生き返らせたのは儂の勝手だ。


そう鬼は何度も自分に詫びの言葉を唱えた。
よそから見れば、きっと自分は酷い表情をしていたのだと思う。
鬼は頭に被っていた笠を外していた。上げた顔は、初めて出会ったときに想像したものより恐ろしいものではなかった。笑うことができればきっとその屈強な外見も問題ではなくなる。そんな風にも思ったけれど、自分を見つめる鬼は罪悪感を噛み潰したような顔をするばかりだった。
なぜ鬼がそんな辛い表情をするのかわからない。
わからないけれど……何よりも、聞きたいことがあった。だから問うた。
――蛇神だった自分の最期の言葉はなんだったのか、と。



…………。


問いを受けた鬼は、長い沈黙の後に答えた。



お前は、最期まで母を探していた。目も見えなかっただろう、耳も聞こえなくなっていただろう。そんな中で繰り返し母を呼び続けていた。





いま言うのもなんだが、もしかするとお前は母の後を追いたかったのかと思うと、儂のこの行いはまさしく鬼の所業。死なせてやれなかった。





……死なせてやれなかったのだ。儂自身の醜い情のせいでな。


別れたあの時、気配を感じていたならば、あのまま精霊の子を一人で返さなければよかった。後になって追いかけて来なければよかった。鬼は自分の過ちを悔いていた。
まったくもって鬼らしくないと思った。
だから責める気持ちは一片たりとも湧き起らなかった。
代わりに、ふと煉獄の炎のような情が胸の内に宿るのを覚えた。いついかなる時も、この情は消して消えやしないのだろうと思った。
あの化け猫と再び相まみえる時が来るまで。
だから自分は目の前の鬼に願った。自分を本物の鬼にして欲しい、と。
そう、これから自分は体だけではなく心も鬼になるのだ。鬼として生きていくのだ――。
――母様。
――母様。
――こちら側はきっと地獄なのでしょう。鬼も笑えないほどの地獄なのでしょう。これから私が生きていくのはそんな世です。
――けれど、これはきっと幸いなのです。
――聞けば鬼は魂を操る。私の魂も鬼によって蘇った。ならば私が一人前の鬼になれば、もう一度母様に会うことができるかもしれません。
――私は最期まで母様を探し、憂いていた。それでこうして生きながらえたのなら、これが私の運命。きっとそうに違いありません。
――母様、安心してください。私はいつまでも母様の子です。母様の沼は私が守り続けます。母様が返ってくる日までずっと。
――私は、鬼になるのです。



ほれ、オーライ、オーライ。





頑張れ頑張れ。ほれほれ、うちっと気張ってみろ。






んん~っ。ふんっううぅ~!





力ねえなぁ、ほれもう少し。






オヤブンうるさい~。





よいっっしょ、とぉ!







ふぅ。……うーん、ちょっと曲がっちゃってるかな?


ここは魑魅魍魎、八百万の妖怪と精霊が勢力を二分するカクヨノ山の麓にある小さな沼。
猫又が姿を消した盆祭りの後、十数日と時間が過ぎてしまったが、蛟鬼は荒れた沼を直しにやってきていた。
沼には一人で来たのだが、一体いつからいたのか、親分が先に来ていたのには少し驚いた。蛟鬼の意図は知っていたが、別に手伝いに来たわけではなく。ただこうして、出不精の鬼王丸の代わりに蛟鬼を見守っている。




うう~疲れた。


地面の土をならし、枯葉や枝を払い、石碑をもとの位置に戻してようやく沼がきれいになった頃には、蛟鬼はへとへとだった。足を沼の水に浸し、体は無防備に地面の上に倒して腕を開く。
化け猫の気配はもうない。ついでに盆祭りも寝ている間に終わって下界も静か。片付けが終われば途端に暇を感じる。



あーぁ、終わっちゃったな……。





!





……まあ、そんなくよくよするな。





え?


苦労して繕われた着物が汚れることも気にせず地面に寝転ぶ蛟鬼に、親分が言う。



祭りなんてのは夏が来れば人間たちがまた催すだろう。今そうやっていじけてなくても、季節が変わるのはあっという間だ。俺達には時間はまだある。





……ふへ


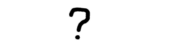



ん?


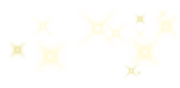



ふへへへ~。


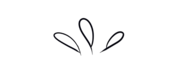



な、なんだなんだ。そのだらしのねえにやけ顔は。


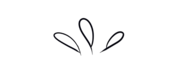



蛟鬼、お前まだどっか治ってないんじゃねえのか?頭とか。


悪いところが似てしまったとつくづく思う表情の硬い蛟鬼が、恐ろしいほど頬を緩ませて笑いを漏らしている。親分は不気味に思うと、蛟鬼は着物の袖に手を入れて、しまっていた物を取り出し親分に見せた。
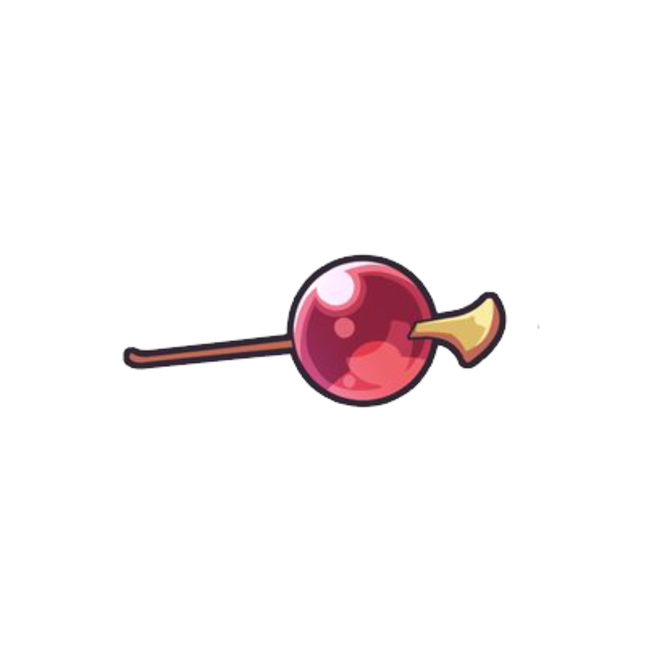
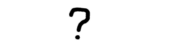



――蛟鬼、お前そのかんざし……どうしたんだ。





師匠がね、代わりに山を下りて夜店で買ってきてくれた。


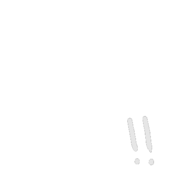



鬼王丸がか!?出不精のあいつが!?


親分の驚愕の声が沼の水面を震わす。
あの鬼王丸が小屋どころか下界まで下りるなんて。最近では酒の買い出しも蛟鬼に任せて一層外に出なくなったというのに。たった一本のかんざしを求めて外に出たと聞けば驚かないわけがなかった。
けれど、その理由を聞かずとも、親分はすぐに納得する。



ああ――でも、お前の為だからなぁ……。






ふふふ。


蛟鬼はご機嫌な様子で、かんざしについたガラス球を覗いては目を輝かせる。
しばらく寝たきりのうちに今年の祭りは終わってしまったことは残念ではあるが、悲しいことはない。むしろ楽しみの方があった。



来年は一緒に行こうって約束もしたの。





そうかい。じゃあさっきのいじけた一言は話聞いてほしいだけのかまってちゃん発言かい。





まあ、仲直りもできたようで安心したよ。お前の機嫌が悪いと話し相手も気を遣うからな。


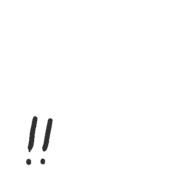



あ


やれやれと息をつく親分だが、それを聞いて蛟鬼は何かを思い出したようだった。
ジャバっと水面を蹴り上げて体を起こす。文句を言うように親分に言った。



そういえば、オヤブンに教えてもらったオマジナイの言葉、全然効かなかったよ。





ん?あ――ああ、あれか。なんだ、鬼王丸喜ばなかったのか?





喜ぶ?ううん、怒ってた。


蛟鬼は首をひねる。マジナイとは、蛟鬼が鬼王丸と喧嘩したあの日、親分が教えてくれた仲直りを助けてくれる言葉のことだ。
けれど、教えの通り言葉を唱えたのに、鬼王丸は怒りだしたのだと蛟鬼は訴える。
訴えられた親分はというと、マジナイが効かなかったことに謝るわけでも不思議がるわけでもなく、ただニヤニヤと聞いてきた。



それで、え?鬼王丸は一体どんな反応だった。どう怒ってたよ?





ええ……どうって、呑んでたお酒を口からも杯からも零して、すごく慌てながら怒ってた。






ひぃーひひひっ。そうか、そうか。そんな狼狽えてたかあの野郎。


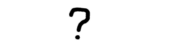



なんでオヤブン笑ってるの?本当に師匠が喜ぶオマジナイの言葉だったの、あれ?





おうともさ。蛟鬼こそちゃんとマジナイ唱えたのか?





言ったよ!ちゃんと!





『パパ』って!






ひぃーひひひひっ。





ねえ、なんで笑ってるの。あのマジナイの言葉、一体どういう意味なの?


親分はひっくり返って脚をわちゃわちゃと絡ませながら笑い転げている。
鬼王丸も親分も、なぜこのマジナイの言葉にそんな反応をするのか、外海に出たことがない蛟鬼には意味が解らない。
なんだか騙された気分でむっとする。




いいよだ。誰に教わったって師匠に凄まれたとき、オヤブンだって告げ口しておいたから。





なんだと、それはまずい。当分会合には顔を出さない方が身のためだな。


親分は掌をひっくり返すように起き上がると、くわばらくらばらマジナイを唱える。
やっぱり変なの、と蛟鬼は首をかしげるばかりだった。



さてと。そろそろ昼飯の時間だから俺は帰るか。





蛟鬼は?どうする。


気も済んだわけで、飛び上がった親分は蛟鬼に尋ねる。蛟鬼もうんと頷いた。



師匠のところに帰る。ご飯作らないと、師匠、お酒とつまみしか口にしないから。





そりゃ帰らないと心配だな。


羽がある親分は言うと、一足先に沼から続く獣道を戻っていく。蛟鬼もその後ろを追いかけてかけて、足を止めると、一度だけ後ろを振り勝った。そこには元通り整地された小さな沼がある。




またね――母様。


微笑んで、子鬼は棲み処へと帰っていった。
――昔々とある国のとある地方に、人々が霊峰と崇める山がありました。
山の麓には人々の信仰を集めた沼があり、人間の生活に欠かせない水を山から分け、時に雨を降らせる蛇神様が棲んでいました。
しかし蛇神は山を越えてきた化け猫に食われてしまい、消え去ってしまったものの、なぜか沼は荒れることなく水を澄ませて今もある。
山の精霊と妖怪を恐れて滅多に足を踏み入れない人間たちは、とても不思議に思っていたが、それもこの山の力なのだろうと納得するばかりでした。

