そう言って緋瀬は買ってきたペッドボトルの水をおずおずと差し出した。
オレはベンチに座ってぐったりとしながらもそれを受け取る。
なぜこんな状況に陥っているのかというと、
その理由はとても簡単で、単純で、明快であるが、
オレないし「俺」はこのジェットコースターという高低差のある斜面を高速で駆け下り、ある時には回転し、ある時には旋回するという奇天烈極まりない乗り物が極端に苦手だったのだった。
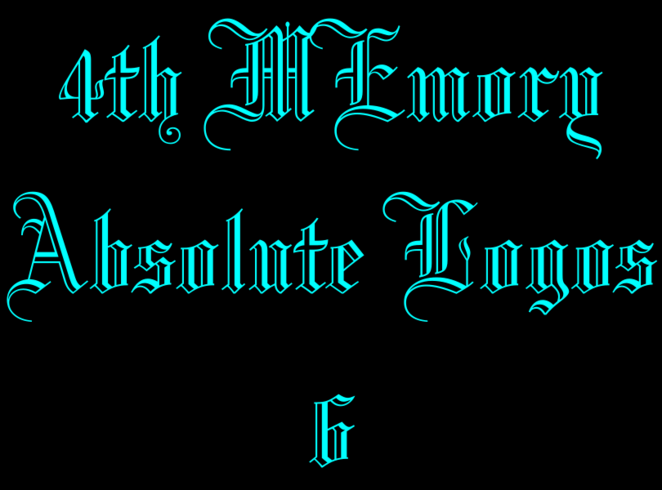



ゆ、悠十くん、だ、大丈夫?


そう言って緋瀬は買ってきたペッドボトルの水をおずおずと差し出した。
オレはベンチに座ってぐったりとしながらもそれを受け取る。
なぜこんな状況に陥っているのかというと、
その理由はとても簡単で、単純で、明快であるが、
オレないし「俺」はこのジェットコースターという高低差のある斜面を高速で駆け下り、ある時には回転し、ある時には旋回するという奇天烈極まりない乗り物が極端に苦手だったのだった。
しかもさらに不幸なことに、そのことをオレが自認したのはつい先ほどのことで、気づいた頃には時すでに遅し、オレの三半規管はパニック状態、気分は最悪という現在の状況に至ったわけだ。



悪いな、ちょっとだけベンチで休んでていいか?


オレはベンチの背もたれに頭をもたせかけて言った。
今日は少し日差しも強く、汗ばむほどではないにしろ、かなり気温が高くなっていた。
幸いにもオレが今座っているベンチは日陰に入っていたので他に比べればいくらか涼しい。
ここで10分も休んでいれば回復するだろう。



う、うん、全然大丈夫だよ。


そう言って、緋瀬はオレの隣に座る。
完全にノックダウンされたオレとは対照的に緋瀬はジェットコースターを存分に楽しんだらしく、最初ほど緊張はしていないようだった。
そもそも彼女は緊張しいというか、おどおどした性格の持ち主であったので、それを差し引いても機嫌が良さそうなのは明らかなのだ。
緋瀬が楽しんでいるところに水を差すような真似をしているというのは非常に気が引ける。
早いところ復帰して次のアトラクションに行かなくては……。
そんなことを考えているとおもむろにアイツが話しかけてきた。



なんというか、情けないねぇ。


チッ、と心の中で舌打ちをする。



うるせぇぞ、クロ。
お前は引っ込んでろ。





なんだい、ユウ。
ワタシが出てくるなりいきなりうるさいとはご挨拶じゃないか。





お前が出てくるときってのは大抵、
不平不満と愚痴嫌味を垂れるときか、
最低最悪の緊急事態が起きるときだからな。





そんなことはあるまい?
そんなに嫌な四字熟語を並べるなよ、ユウ。





そうかよ?
じゃあなんの用件か言ってみろよ。





いやなに、些細なことだよ。
……さっきからあのピエロがこちらを見ている、というだけさ。


オレは背筋の凍るような感覚に襲われ、そして恐る恐る顔を起こした。
オレたちが座っているベンチの向かいには噴水のある小さな池があった。
おそらくそこから出てくる水も、このあけぼの遊園地の場合はMERのスタッフが生成した水なのであろうが、そんなことは今はいいのだ。
そこには白い人影があった。
もっと正確に描写するなら、黒いシャツの上に白いスーツを着込んだピエロの姿があった。
その素顔を伺うことは出来ない。
オレはその姿を、知っていた。
拭いきれない既視感があった。
《分離実験(ディバインディング・プラン)》が実行されたあの巨大な空間で宙吊り、否、逆さ向きに立っていたあのピエロである。
クロノスの結晶を奪い、そこに《世界樹(ユグドラシル)の鍵》を突き立てたあのピエロである。
そのピエロがじっと、身じろぎもせずに、こちらを見つめていたのだ。
その姿はオレにとって不吉以外の何物でもなかった。



緋瀬、そろそろここから動こうか。


オレはまだ完全回復とまではいかない体を持ち上げて言った。
ここから離れなくてはならない。
一秒でも早く、一歩でも遠く。



え?
で、でも、ゆ、悠十くんまだ体調がよ、よくないんじゃ……。





オレならもう大丈夫だよ。
ほら、全然余裕で動けるし!
次はそうだな、あれ、あの観覧車に乗ろうぜ。


オレは緋瀬の手をとり、そして適当に目についた観覧車を指差す。
すると、緋瀬は若干不満そうというか決まり悪そうな顔つきになった。



え、えっと、あ、あ、あれはもう少し暗くなってから……。





そうなのか?
えっと、じゃあ他のアトラクションに――。


とにかくここから離れる口実が欲しいオレは当たりをぐるりと見渡す。
――この時、オレは口実なんて探さずさっさと緋瀬の手を引いて移動するべきだったのに。
緋瀬にこの事態を悟られたくなかったというのが本音かもしれない。
いずれにしろこの判断の過ちこそオレが最も悔いるべきことだろう。
そして最悪の、災厄の、道化師(クラウン)の大道芸(ショー)が幕が上がる。
* * * * *
気づけば、夜だった。
こういう表現は非常に突飛に聞こえるかもしれないが、本当に気づけば夜だったのである。
別にオレが気絶していたわけではないと思う。
オレは正常な意識を維持し続けていた。
そして異常な世界を目撃し続けていた。
オレが目撃したのは周りの人々が凄まじい速さで、
それこそ認識できない速さで行き交い、
そして太陽が早送りのごとくするすると沈んでいくという光景だった。
もしくは、そんな光景を異常と思うオレこそが異常なのかもしれない。
つまり、オレが異常になったから正常な世界も異常に見えた、と。
まぁそれは大した問題じゃない。
問題の中核はオレと世界の間に乖離が生じているという一点に尽きる。
すなわち、オレの認識内における時間の経過するスピードに比べて、世界における時間の経過するスピードが速く進んでいる、ということだ。
遊園地の中にあるアナログ時計は11時50分を指していた。
そして、オレがあの無彩色の不吉なピエロを見た時間もまた11時50分頃。
しかしこの場合、時間が経過していないというよりも、ちょうど一周、すなわち12時間だけ“世界側”の時間が経過したのだと考えるのが自然であろう。



こんばんわ、気分はいかがかな?


後ろから不意に声をかけられて、オレは勢いよく振り返った。
そこには黒いシャツの上に白いスーツを着込んだピエロ、《道化師(クラウン)》が立っていた。
やはりその顔にはピエロの仮面をつけているので表情を伺い知ることは出来ないが、それでもはっきりと感じ取れる――
――明確な、敵意。



気分……ねぇ。
あんまりよくはないな。





そうかい?
君はどうもジェットコースターが苦手なようだからね。
今後乗る時はもう少し用心して乗ることをおすすめするよ。
ああ、それと、君はもう少し女性のエスコートというものを学ぶべきだよ。
普通、デートでの観覧車は夜に、それも最後に乗るべきさ。
真昼間から、しかも序盤に観覧車というのも、ロマンスにかけると、私は思うね。


格好にふさわしいその口調でピエロは言った。
話している内容からすれば、こいつはオレと緋瀬がこのあけぼの遊園地に来てから、あるいはそれ以前からオレたちを監視していたことになる。



で?
ご忠告ありがとうございました、とでも言えばいいのかよ?


オレはピエロから視線を逸らさないようにしながらゆっくりと、MINEを耳に装着した。
そして、そのまま執行システムを起動する。



忠告?
そんな大それたものじゃないさ。
彼女とうまくやるためのアドバイスといったところかな。


執行システムの起動に伴うセンサーアシストにより五感が研ぎ澄まされていく。
しかし、少なくともオレの目に入る範囲に緋瀬はいない。



緋瀬は……どこにいる?
家に帰ったのか?





ああ、彼女かい?
いや、彼女ならまだこのあけぼの遊園地にいるよ。
正確に言うと、あれの中央部分にあるスタッフルームだけれどね。


そう言って、ピエロはオレの後方を指差す。
振り返ると例の観覧車があった。
無論、観覧車を含めアトラクションは止まっている。
それは今の時間が午後11時50分であることを、
そして見渡す限りこの場にいるオレたち以外の一般市民やスタッフは一人もいないことを考えれば自然なことであった。
しかし、完全に眠りについた真っ暗な遊園地の中に取り残されているというのはどうにも不自然な感覚だ。
観覧車の回転する中心部分にはカプセルのようなものが存在していた。
それは、このあけぼの遊園地が、MEを最大限に活用している遊園地であるということを特徴づけるものでもある。
すなわち、ピエロが言った通りスタッフルーム、もっと的確に表現するならば、動力源をMEによって動かすMERが駐在する部屋ということになる。
なぜ緋瀬がそんなところにいるのか、
否、
なぜピエロがそんなところに緋瀬を閉じ込めたのか、
そのときのオレには分からなかった。
――しかし、すぐに解答が示される。



ああ、そうだった。
彼女の能力は私の計画の障害となるから、封じ込めておかなければならないのだったね。


そう言ってピエロはパチンと指を鳴らした。
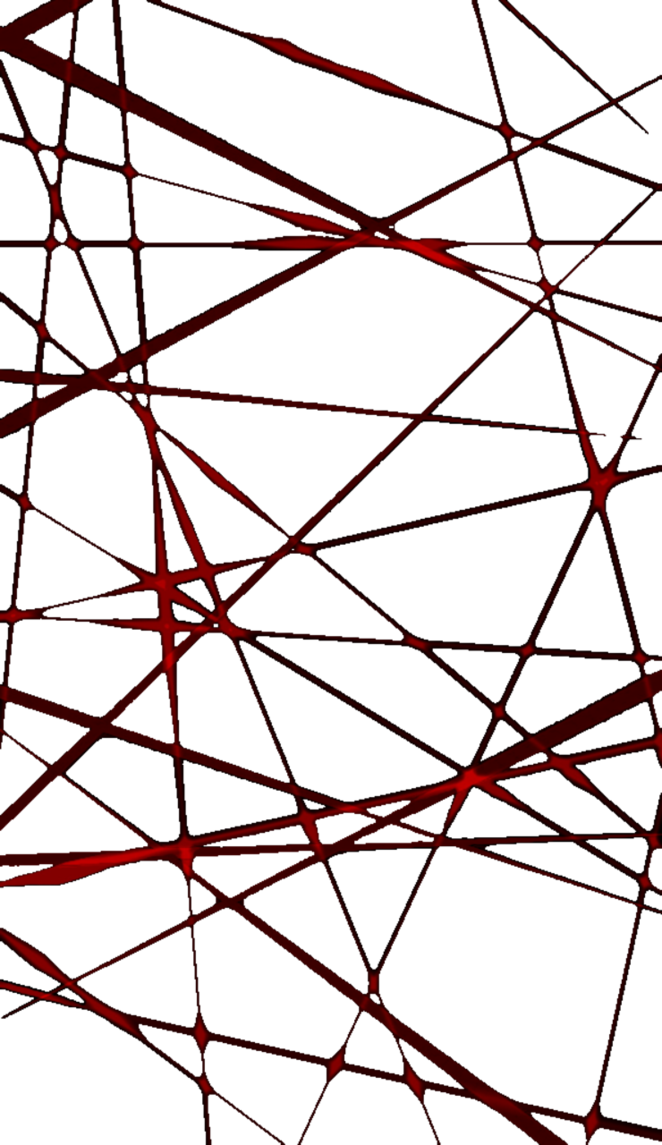
すると次の瞬間、カプセル状のスタッフルームからいつか見たあの赤い光が迸り、そしてその光は観覧車の骨組みを伝ってゴンドラまで届く。
ゴンドラまで辿り着いた光は隣のゴンドラに行き着いた光と合流して、巨大な円を浮かび上がらせた。

浮かび上がったそれは、
赤い光によって刻まれた魔方陣に見えた。
