慣れない花の香りで目が覚めた。それだけでここが自分の部屋のベッドではないことを理解して大翔は急いで起き上がる。
慣れない花の香りで目が覚めた。それだけでここが自分の部屋のベッドではないことを理解して大翔は急いで起き上がる。




今日は、どこだ?


夢の中で目を開けた大翔が最初にすべきことは周囲を確認することだ。今までならともかく、脅威があると知ってしまった以上やらないことにはろくに動き出すこともままならない。カベサーダの姿がないことを一番に確認してとりあえず息をつく。
ここは夢の中だ。それに気付いてもまだ夢からは抜け出せない。つい数日前はそれだけで心が躍ったというのに今はただ頭が恐怖に満ちていた。
昨日のショッピングモールではなさそうだ。今日落とされた空間はどこも白い光に照らされて暗闇など見当たらない。足元はふわりと柔らかい絨毯で、きれいな模様が入っている辺り高価そうに見えた。
なんだか修学旅行で見たような気がする。と思って、大翔はここがホテルのエントランスだと気がついた。人の気配はほとんどないし、クロークはソファやロッカーで埋もれていた。物が散乱するのは夢の世界ではよく見た景色でそれに大翔は動揺することもない。



光さんと橋下。どこにいるんだろう?


待ち合わせ場所でも決めておけばよかった、と後悔する。三人とも仲間が出来たことへの安堵感からそういうことをすっかりと忘れてしまっていた。それに決めていたとしてもこうして自分たちの知らない場所に落とされては合流のしようもない。



とりあえず人がいるところに行こう


大翔は辺りを見回してなんとか先がありそうな昇り階段を見つけて、足をかけた。
階段、というとなんとなく昨日見た果てしなく続いていそうな部屋を思い出して嫌な予感がしたが、大翔の想像はありがたくも外れて螺旋階段はすぐに終わりを迎えた。
また柔らかい絨毯に大翔は足を乗せた。それと同時に目の前に立っていた男に声をかけられる。



ちょっと、君


二階に上がってきたというのに見えた風景は階段の下と少しも変わらなかった。同じ空間が繋がっているのかとも思えたが、大翔は正面から声をかけてきた男の存在に安堵する。



俺、ですか?


尊臣ほどではないが、それでもクラスの男子ではちょうど中間くらいの大翔よりも五センチは高いだろうか。さっぱりとした短髪に細い眼鏡をかけた男は大学生くらいに見えた。



君、ここは何回目?





何回目ってたぶん一週間くらい前からですけど





奴を見たか?





あのカベサーダって奴ですか?


男は大翔の答えを聞いて深く頷いた。



それなら話は早い。俺は、氷室衛士だ。どうだろう、君。俺たちと手を組まないか?





え?





あのカベサーダ。危険ではあるけど、多人数で互いを守れば何とかなる相手だ。だからネットで仲間を集めていたんだ


自分たちと同じ考えの人間がいたのか、と大翔は衛士の顔を見た。まっすぐな目はどこか自分に似ているとおこがましくも感じてしまう。



俺も友達と合流するつもりなんです





そうか。君もか


衛士は落ち着いた様子で答える。大翔たちが簡単に思いつく作戦だ。大翔より年上に見える衛士にとっては考えついて当然のことだったのだろう。さして疑問に思うことなく、残念そうに肩をすくめた。



でもきっと仲間は多い方がいい。俺たちと合流したいって言うなら、その友達も連れてくるといいよ。歓迎する





ありがとうございます。それじゃ


衛士が人だかりに戻っていくのを大翔は見送った。遠めに見ても三十人は下らないほどいるだろうか。確かに人数が多ければそれだけ心強いだろう。少しだけ大翔にも合流したい気持ちが芽生えたが、それよりもまずは二人を探すことが先決だ。
ホテルの二階をぐるりと周回してみたが、二人の姿は見当たらなかった。まさかどこかの部屋でのん気に眠っているということもないだろう。もう一度、大翔は目が覚めた一階に戻ってくる。
やはり二人の姿も、他の人間の影もない。おそらくさっき見た衛士の集団にみんな加わっているのだろう。いきなり現れた大翔に躊躇なく声をかけたところからしても仲間を値踏みしているようには思えなかった。
どうしたものか、と考えていると、大翔はクロークに積み上げられたソファたちの間に人が一人通れそうな隙間があることに気がついた。



ここなんか怪しいな


偶然出来ただけかもしれないが、ここは夢の中だ。何かが意図的に仕組まれている可能性は十分にある。大翔が隙間を覗き込む。先はクロークの裏側。本物のホテルなら従業員の詰所にでもなっていそうなものだが、細く光が見えていた。



行ってみよう


確証もなかったが、ホテルは全部見てまわった。それならこの先に行ってみる価値は十分にある。体を小さく折りたたみ、大翔はゆっくりと絶妙なバランスで組み上がったソファの中に潜り込んだ。
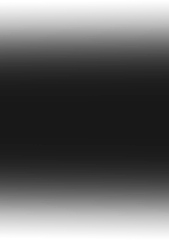
ソファ二つ分を抜けた辺りでちょうど正方形の狭い廊下に辿り着いた。大翔がしゃがみこんで少し頭に余裕があるくらいで尊臣なら這っていかないと通れそうにない。ソファの足が邪魔をするのをなんとかすり抜けて大翔は通路の中に潜り込んだ。
同じ高さ、同じ幅の空間をしゃがんだまま少しずつ進んでいると、なんだか違う世界に迷い込んでいくような感覚がある。せめて光が見えているだけ、気分が楽だろうか。
