枕元に置いた目覚まし時計は深夜零時を越えていた。
枕元に置いた目覚まし時計は深夜零時を越えていた。
明かりを落として黒に満たされた部屋に青白い光だけが浮かんでいる。
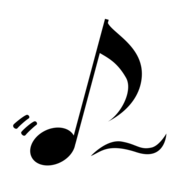



よし、難関ステージクリア!


神代大翔(かみしろひろと)はベッドの中で小さくガッツポーズを作って、ゲームアプリをスリープする。
やがてスマートフォンのバックライトも消え、部屋は完全な暗闇に包まれた。



そろそろ寝ないとな


明日も学校がある。しかし、それとは別に大翔はこの毎日の休息を楽しみにしていた。



今日はどんな夢を見るだろう?


それはまるで子供のような好奇心にきらめく瞳。
今しがた遊んでいたゲームの世界を見つめるような心地。
ベッドの上から降りることもなく冒険に旅立つような気分で、大翔は目を閉じた。
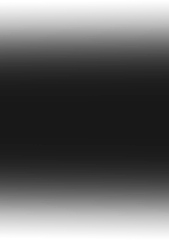



今日は、どこだ?


大翔は目を開けた瞬間に素早く周囲を確認する。
薄暗い世界に少しずつ目が慣れてくると、ざらついた壁を支えにゆっくりと立ち上がった。いつもと同じ高校の制服に身を包んで、大翔は学校とは関係のない場所に落とされる。



なんだろ。ショッピングモールっぽい感じ?


通路にはシャッターが等間隔で閉められているが、その一つ一つに看板が掲げられている。円柱状の空間は真ん中がすっぽりと吹き抜けになっていて、大翔がいる場所が三階であることがわかった。



それにしてももう少しいい夢は見れないもんかな


ここは自分の夢の中である。大翔はそれをはっきりと自覚していた。
自分が夢を見ていることがわかると、いつもなら急に視界が暗転して簡単に目が覚めてしまっていたが、一週間ほど前からこうして夢の世界を自由に動き回ることができるようになった。
それに気がついたときから大翔は毎日夜が来ることを心待ちにしていた。自分の欲しい世界を作り出せないか、と寝る前にマンガを読んだり、ゲームをしたりしてみるものの、いつも放り込まれるのは誰もいない潰れたアミューズメントパークや廃校になったような校舎ばかりだ。



今日も外れだな


口ではそう言ってみるものの、夢の中を自由に歩くことができる。その一点だけで大翔の心は期待に昂ぶっていた。
何かが起きるかもしれない。誰かがやってくるかもしれない。なぜならここは自分の夢なのだ。大翔が願ったことがいつ訪れるやもしれないと思うと、目が覚めるその瞬間まで動き回りたくなる。
周囲の状況も少しずつ理解できるようなった。いつも夢の中は空っぽという言葉がよく似合った。今日も誰もいない場所でショッピングモールだろうと思ってはいるのに、店はどこも閉店で潰れてしまったと言われても納得がいく。本来なら人で賑わうはずも場所に誰もいないのは余計に寂しさが増すものだ。
誰か本当にいないのだろうか。大翔は人影を探して吹き抜けの下を覗き込んだ。普段なら絶対にやらない小学生のような身の乗り出し方。それともいっそここから落ちてしまえば空を飛ぶような力がめざめるかもしれない。
向かい側、二階と頭を動かして人の姿を探してみるが、照明の少ないモールの中ではよく見えない。さらに頭を下に向けると、一階の中央にイベント用のステージが置かれていることに気がついた。簡素な白い舞台に無地の背景が立てられているだけだが、控えめにスポットライトが落とされている。周囲が暗いせいもあってそこだけ違う世界から切り取って持ってきたような魅力があった。



あそこに行けば何かあるかも


テレビの向こうでしか見たことがないアイドルに会えるかもしれない。いや、夢ならマンガの中のヒロインにだって会える。大翔は体の半分を乗り出していた手すりから通路に体を戻し、下の階へと続く階段を探そうと振り返った。



うわあああ



階下で響いた大声に大翔はさっきまで覗いていた吹き抜けの下にまた目を凝らした。
白いステージに走りこんできたのはアイドルでもキャラクターでもなく、若い男だった。
自分以外の人間を初めて見た。
見た目は少しばかり不満だったが、この際置いておこう。大翔はさらに身を乗り出して男に向かって手を振った。だか、こちらには気付かない。
息を切らして、ステージの段差に足をとられた男は後ずさるようにスポットライトの真下に到達する。



何やってるんだ?


遥か下で青ざめたような表情で震えている男のことを、大翔は不思議な気持ちで見下ろしている。そこに黒い影が躍り出るようにステージに倒れた男に飛びかかった。




ヒーローショー?


という言葉が大翔の頭に過ぎる。ここから颯爽とヒーローが現れて黒い影を倒して男を救う。ありがちだがシンプルで燃えるシーンだ。
大翔も昔はこんなショッピングモールの屋上や遊園地でヒーローショーを見ていた。誰よりも強くなって弱きを助け悪を倒す。一度は夢見ることだ。今でも時々思ったりもする。目の前に現れた悪を自分が成敗する時は来ないか、と。
その考えは男の周囲に広がった赤い血の跡に一瞬にして消し飛んだ。
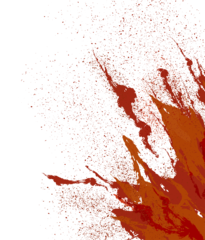



ぎゃああああ!


断末魔が大翔しか人間のいなくなったモールに響く。



おいおい


ショーにしては過激すぎはしないだろうか。今年で高校生になった大翔が本気で頭が真っ白になるほどの叫び。遠目から見てもあまりにもおびただしい血の跡。男が完全に動かなくなったのを見て、黒い影がじろりと大翔を見上げた。
赤い瞳が大翔を射抜くように見つめている。
ステージで起きた惨劇をどこか遠くの景色に感じていた大翔は、腰が抜けたようにその場にへたり込んだ。



落ち着け、これは夢だ。ただ夢見が悪いだけなんだ


ベッドの上で目を閉じた記憶もある。間違いなくここは夢の中だ。
そう自分に言い聞かせてみるが、大翔はもう一度階下を覗き込む勇気も出ず口に溜まった唾液を飲み下した。
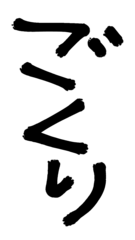
その肩に何かが触れる。
