猫。
猫。
子猫だ。
猫が死んでいた。
道の真ん中。
車に踏み潰されて、下半身だけが砕かれた。猫だ。
猫だった肉だ。
商店街に向かっていた俺の目の前で。そいつは轢かれた。
目が見えなかったのかもしれない。耳が聴こえなかったのかもしれない。
大型トラックのタイヤ。
自重の数千倍に及ぶそれに気付く間もなく押し潰され、骨の形も残らぬほどに臀部から下を粉砕された。
くちゅん、と小気味いい音がした。
幸せなことに、運転手はとうとう最後まで気付かなかったようだ。
走り去る。
黄昏時。裏路地。
影が伸びるいつもの登校路には、示し合わせたように俺と猫しかいなかった。
そう、生きていた。
片手に乗りそうなほど小さかった猫は更に半分になって尚、生きて地面を掻いて。鳴いた。
地獄はこんな風景かもしれない。
お腹を空かせたように鳴く生まれて一年も経たないであろう、その生き物は自分が地面に縛られたように感じたかもしれない。
肉塊はアスファルトにこびりついて、前足では剥がれない。
猫は生きて地面を掻いていた。
自分の肉を集めるように。
そうすれば、何事もなかったかのように母の元へ帰れると思っていたのだろう。
そして鳴かなくなる。
最後まで静かな死だった。
黒い血がアスファルトの表面、夕闇に焦げつき、毛皮が臓腑に食い込み脂が溶ける。
蝿がたかる。卵を産んでいるのだろう。
烏が鳴く。腐肉を啄みに来たのだろう。
高齢の女性が向こうから歩いてきた。
俺が立ち止まっている視線の先を不審げに見遣り、それが『何』であるのか気付くと鼻の頭にシワを寄せた。
キ○ガイを見る視線で、俺を刺して。
そして歩いてきたのと同じスピードで一度も止まらずに彼女は俺とすれ違う。
それだけだった。
それだけだった。
俺は混乱していたに違いない。
ただ酷く、当たり前のはずの光景に肺をもがれたかと思うほど、呼吸が奪われて。
でも当たり前。目の前の情景は、当たり前の日常だ。
猫が死ぬくらい当たり前。
そんなものに足を止めるなんて、哲学者や詩人に任せておけばいい。
埋葬するくらいならホースで排水口に押し流す。
それよりも、残酷な死体に興味を持つなんて気味が悪い子供だ。
教育が、メディアが、社会が。
きっとあの子猫はこの世で一番弱かったのだろう。
弱いのに母親から守られなかったから。
だから殺されたのだ。
弱いやつから自然に死んでいく。
ふいに沙希のことを思い出した。
彼女は何番目に弱いのだろう。
いつ殺されるのだろう。
この道は登校路だ。
俺と沙希の家までそう遠くない。
このままだと、この死体は沙希の視界に入ってしまうかもしれない。
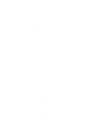


隠さないと


隠さない……と?
そう言って。
そう言葉にしてから、自分の無意識のセリフに吐き気を催し、口元を指が白くなるまでに押さえる。
隠さないと?何のために?
沙希を守るためだ。
弱い沙希の心を守るために俺は、もっと弱かった、死んでしまった猫の死体を隠そうとしたのだ。
たぶん『守る』ってことは本質的にそういうものなんだ。
呼吸が荒くなり、泣いているかのように嗚咽が漏れ、吐息が震える。
頭の毛穴すべてが力づくでこじ開けられたかのように冷える。
日が落ちてから、ようやく俺は決心できた。
弔おう。
乾いた土の下に埋めて小さな墓を作ってやろう。
欠片も残らないように集めてきちんと還れるように。
花を添えて。
車がまた来ないうちにせめて胸から上だけでも歩道に上げないと。
そう思い歩み寄り、俺はそのことに気付いた。
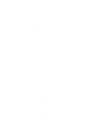


………は?


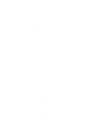


………………


すべてがどうでも良くなった。
これは喜劇だろうか。悲劇だろうか。
笑えばいいのだろうか、憤ればいいのだろうか。
これは仕方ない。
それはそうだ、みんな正しい。これは無視するしかない。
結局俺は何もせずに帰った。
そしてきっと何事もなかったかのように日常を続けるんだ。
『接着剤で目を塞がれ、耳穴から釘の頭が覗く子猫の死体』を綺麗さっぱり忘れて。
