陸と別れてからまもなく、医師の見立て通りに父は意識を取り戻した。
憎らしくも順調に回復する父を祖父母と共に何度か見舞ったが、とうとう男の口からあの話が出ることはなかった。
陸と別れてからまもなく、医師の見立て通りに父は意識を取り戻した。
憎らしくも順調に回復する父を祖父母と共に何度か見舞ったが、とうとう男の口からあの話が出ることはなかった。
しばらくして陸は、何も告げずに転校していった。陸が父にどういう風に話をしたのかは知らないが、わたしや祖父母の生活に波風がたたなかったということは、彼は上手くやってくれたのだろう。
その後の異母弟や愛人の行き先などには、わたしは全く関知していない。けれども、父は退院した後も変わらず彼らのところへ通っていたと思われたから、そう遠くへは行っていないのかもしれないとは思う。
都会の真ん中で、いつか偶然会うことがあるかもしれない――そんな儚い希望を持ったのも、初めの数ヵ月のこと。世間狭いようで案外広くて、運命なんてものがないことを思い知る。
そのうち陸のことを思うことは少なくなった。数年も経てば、思い出すこともなくなった。
いつしかわたしの中で弟の存在は、完全に過去になった。
父の病気が再発したのは、わたしが大学を卒業する間際のこと。再度脳から出血して倒れた父は、あっさりと帰らぬ人となった。
晩年は高校生の頃以上にわたしや祖父母との関わりが薄くなり、危篤の知らせを聞いた時は久しぶりにあの男のことを思い出したものだった。
葬儀の準備を進めていく中で、昔の感情を徐々に取り戻していく。けれど、あれほど願った男の死は、わたしに大した喜びを与えなかった。
もっと早くに死んでくれていれば、感じ方も違ったのかもしれない。結局わたしは、母の無念を晴らすことができなかったのだから。
それでも、まだ四十代での早すぎる死。わたしの祖父母よりも先に死んだ男は、さぞ無念だっただろう。それを思えば、多少の溜飲は下がる。
父の葬儀はそれなりに立派に、しめやかに執り行われた。あんな男、野で焼いて生ゴミにでも出してやればいい――なんて本心は隠して、わたしは父を亡くして悲しみにくれる娘を演じる。
そんな時、参列者の中にひっそりと愛人の姿を見た気がした。
しかし、げっそりと痩せてやつれきったその姿は、人違いかと思うほどに、かつて見た幸せそうな主婦の姿とは全く一致しない。
それを当然の報いだと思うなんて、相変わらず自分は相当に歪んでいると思う。
けれども、かわいそうなのは陸だ。まだ高校生だった彼に、あの父母と暮らす以外の道があったとは思えない。あれからどうしているのだろう――そう思って参列者の中を探したが、とうとう異母弟の姿を見つけることはできなかった。
別に、今更会ってどうこうしようなんて思ったわけではない。
わたしたちが離れてから、既に五年が経った。一つ年下の弟は、既に成人した大人の男。彼女の一人もいるだろうし、わたしにだって結婚を考えている彼氏がいる。
だけど、わたしたちの父親が死んだ。そのお祝いに、顔くらい見せてくれてもいいじゃないか。
陸と別れてから六度目の春、わたしは就職して社会人になった。
それからは仕事もプライベートも充実した日々を過ごしたが、あまり長くは続かなかった。
恋人がいるのに他の男のことを考えた罰か、それともこの醜い心根に対する報いか、心当たりはありすぎて分からないけれど、わたしは恋人にふられてしまった。



その人は運命の人じゃなかったんですよ。だから合コン行きましょう、先輩!


少し夢見がちな職場の後輩は、成人してもなお白馬に乗た王子様が存在すると信じているような乙女キャラ。
話した自分が馬鹿だったと後悔しながらも、強引に誘う彼女に断りきれず、結局参加することになってしまったのだから、わたしも大概である。



ねぇ――ママとパパって、合コンで出会ったの?


小学生になった娘が、そんなことを言い出すようになったのは、更に数年後のことである。
一体誰がそんなことを教えたのかと考えれば、思い当たるのは一人しかいない。
何だかなあ、とは思うけれど、夫も自ら進んで話したわけではないだろう。そういう自分も、嘘でない範囲で答えるには、同じように教えたと思う。
わたしが仕方なしに肯定すると、娘は目を輝かせて更に言った。



ていうか、合コンって何?


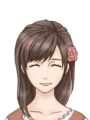


パパに聞いてみたら?





パパはママに聞きなさいって言ったもん!


ああ、夫もめんどくさいことを押し付けてきたものだ。
わたしは適当に「飲み会のようなもの」と言って逃れようとしたが、娘の質問攻撃はそれだけでは終わらなかった。



じゃあ、じゃあ、今までパパ以外には何人と付き合ったの?


先程から相当に際どい質問をしているということを、娘は全く気づいていない。
適当な嘘をついた方が良かったのかもしれないが、娘の無邪気な好奇心に、つい本当のことを話した。
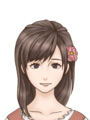


……一人、かな





ふぅん……ママ、その人のこと今も好きだったりして





まさか、どうして?





だって今、なんか間があったもん


そう言った娘に思わず笑ってしまったのは、あまりにも見当違いのことだったから。
元彼のことなど、今の今まで忘れていたくらいだ。かといって、動揺した本当の理由など、娘には絶対に話すことはできない。
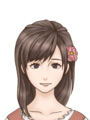


気のせいよ。ママが好きなのは、未希とパパだけだもの





本当にぃ?


夫とは後輩に誘われた合コンで会って、数年付き合った後、籍を入れた。それは紛れもない事実で、わたしは娘と夫を愛している。ただ少し、隠していることがあるだけ。
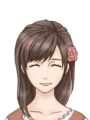


もちろんよ


まだ少し疑っている娘に、満面の笑みで微笑んでみせる。
取り繕うのは得意だった――昔から。
休日の昼下がり、友達の家に遊びに行った娘を見送ると、わたしは一気に手持ちぶさたになった。
夫は急な出勤で、暇な主婦の相手をしてくれる独身の友達もいない。今は隣町に住んでいる泉も、この間三人目の子供が生まれたばかりで、お邪魔するのはまだ気が引ける。
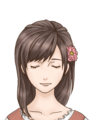


お祝いに何を渡すか、考えておかなくちゃ


結局特にすることがなく、ソファにもたれ掛かったわたしは、ぼうっとしながらそんなことを思った。
どうせ夫はいつもそういうことをわたしに任せきりで、何も考えてはくれない。
だけど――娘の名前だけは、夫が決めた。妊娠したと告げた時から、必ず未希にすると言ってきかなかったのだ。
悪い名前だとは思わなかった。でも、未来への希望なんて、わたしたちが望んでもいいのだろうか、と思った。
神に背き、親を、家族を、友達を、今も裏切り続けているわたしたちに、そんなことが許されるのだろうか、と。
不意にわき上がった不安を口にすると、彼は「いいんだよ」と言って、あの時と同じように微笑んだ。
――先輩。もしも父さんが俺を認知しなかったら、その時は俺達の勝ちです。
彼がそう言って、わたしの元を去ったのは、互いに高校生だった頃。
結局、父はわたしたちが別れたのに安心しきって、彼を認知しないまま死んだ。
どこまでが偶然だったのか、わたしには分からない。もしかしたら、彼は……と考えたこともあるが、それは多分知る必要のないことだ。
父の大切なものを奪って、のうのうと暮らしている、この日常がわたしの幸せ。
復讐は形を変えて叶ったのだ。だから、それ以外には何も知らないふりをする。それでいい。
わたしたちの結婚式の一月前に、彼の母親は自殺した。だからもう、わたしたちの秘密を知る者はない。
わたしたちはどこにでもいる普通の夫婦であり、家族。
たとえ地獄に堕ちようとも、この秘密は墓の中まで持っていくと決めている。
Fin.
