第9話 闇は下から上へ喰む

第9話 闇は下から上へ喰む
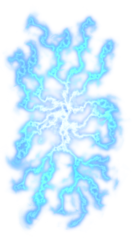



くそっ……よるな、寄るな――っ!


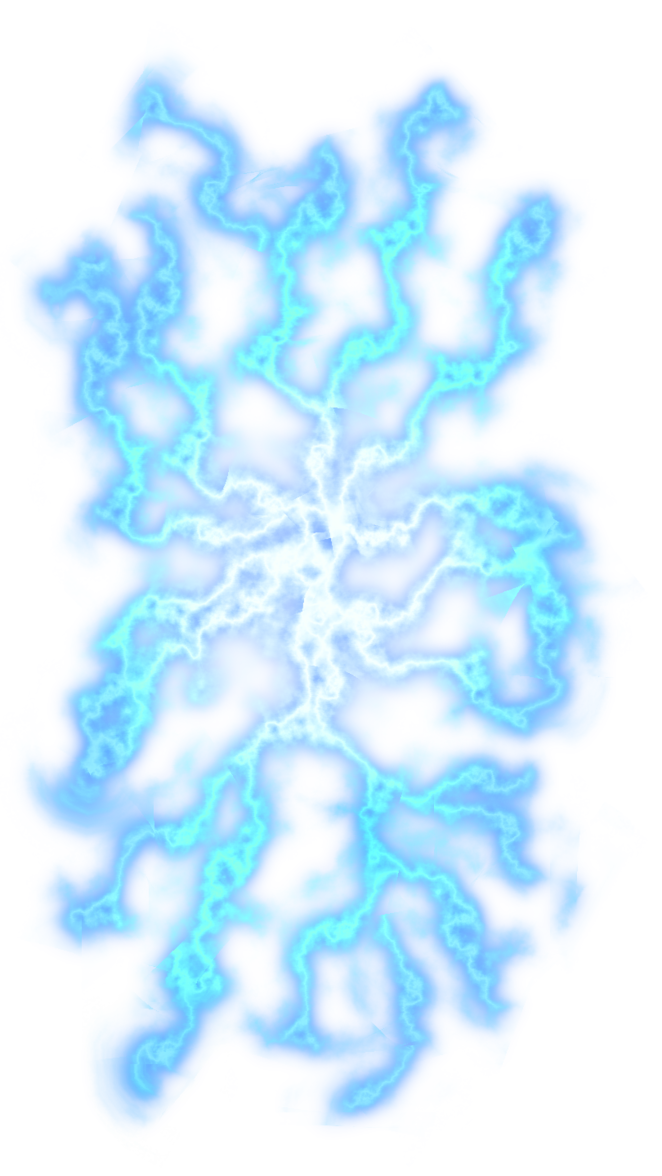
想定外の危機に顔を引き攣らせ、ミスティはパラライザーガンのトリガーをがちがちと指ではじく。
電磁の青いマズルフラッシュが、独房棟の暗く狭い通路を何度も白く打つ。
細い稲妻に貫かれるたび、ミモル型アーデルの白い肉が焦げ、一度は呻きその足を止める。
だがややもすれば、再びそれらはべたりと歩みを進め、じりじりと間合いを狭める。



おい、誰か! 手を貸せ、いないのか、誰か!


声を限りにミスティは助けを求める。
マーメイを拘留したこの地下独房棟に、三人はムルムルの見張り兵がついていたはずだ。
だが、がに股のすり足でにじり寄るアーデルは五体。
うち二体の口が、赤黒い血と半液状の肉片でべっとりと汚れている。



いつ侵入を許した。何故、どこから。


ミスティは後退りしながら必死に思考を巡らせる。
さっきまでインカム越しに届いていた戦況の把握に、誤りはなかったはずだ。
西側の大群も、南側に出現した小型の群れも、まだ防壁にすら到達しないはずではなかったのか。
デナ旧河川跡を西側に、南北に268メルテ、高さ96メルテ。
バーシムCAT西ボリア支部は、百数年以上前からこの地にあった古城を改築、拡張して造られている。
七百近い部屋のほとんどは、外見を維持しつつ電装だけを最新のものに置き換え、居住ブロックや兵器研究開発棟として活用されている。
兵器庫やエアポート、ロボニャー訓練フィールドに造り変えられた広大な中庭を囲むように、アーデルの毒液に耐性を持つ複合金属で高さ40メルテの防壁が新造された。
天へ伸びる二十余の尖った屋根は、そのすべてが武骨なバイタルレーダーに換装されている。
最も高い中央の棟が管制塔指令室となり、各地の防衛レーダー塔を使って西ボリア各地に目を光らせ、神出鬼没のアーデルとの戦いに備えていた。
地下からの大型アーデル襲撃を想定し、基地の真下を覆うようにも防壁は敷かれている。
この防壁を敷設する工事の際に、城の地下構造はほぼ造り変えられたが、ごく一部、地上の建造物を支える重要な構造については、およそそのままの形で残されている。
そのうちの一つがこの北側研究棟地下、懲罰房が並ぶ独房棟だった。
地中を潜る術を手に入れた特殊なミモル型アーデルは、この構造の隙を突いてルクスベースへの侵入を果たし、今ミスティの前に現れたのだ。



こちらミスティ・ブルー!





し、施設内にすでに小型アーデルが侵入! 誰か、は、早く!


捕獲命令違反で拘束したマーメイを尋問する為に独房棟を訪れたミスティは、アーデルとの遭遇などまるで想定していなかった。
加えて、元は北ボリア支部のレーダーオペレーターであり、その後ムルムルの情報管理官を経て西ボリアへ転属してきたミスティだ。
ルクスの面々とは比較すべくもないほど、彼女の実戦経験は皆無に等しかった。
マーメイの独房へ向かう途中、どこかから響いた悲鳴を耳にし振り返った同伴のムルムル兵は、銃口を持ち上げる間も無くびくんと動きを止める。
兵の首から上の部分はすっぽりと、背後から跳びついたミモル型アーデルの口の中に納まっていた。
予想し得なかったその衝撃に、ミスティはよろめき倒れる。
目の前に落ちていた、まだ暖かいぬるりとした血に濡れたパラライザーガンをたぐりよせ、目をぎゅっと閉じたまま、自分の背後に向けて無我夢中にトリガーを引く。

鼻先まで迫ったアーデルの手に電流が走り、びくんと怯む。
血と肉の焦げる悪臭が鼻を刺す。
まだ生きている。
ミスティがそう確かめたのは自分自身のことだった。
石床にできた血の河川に手をついてミスティは立ち上がり、廊下を走った。

背後のアーデルたちをすんでのところでしのぎながら、ミスティは階段を駆け下りさらに地下へと向かう。
この独房棟の構造はあまり把握していなかったが、その目的からして、地上への出口がそういくつもあるはずがないと察してはいた。
マーメイの独房へたどり着いて彼女を解放し、アーデルを撃退する。
それが今生き残る為の唯一の選択肢だった。
カラカルに反抗する力を削ぐべくマーメイ拘束を目論んだ、その張本人であるミスティにとって、この選択肢は不本意ではあった。
だが今は他に手がない。
彼女を解放し――



んあう……ッ!


突然脚に走った激痛に、ミスティは悲鳴を上げ倒れる。
その拍子に、肘を床にしたたかに打ち付け、銃を取り落とす。
脛から下を、太い針であらゆる方向から抉られるような痛み。
自分の脚を見たミスティの全身から血の気が引く。
細胞性粘菌型、ネブァ型アーデル。
床に滞留し待ち受けていた半液状のそれが、走り抜けようとしたミスティの脚に食らいついたのだ。



こ、こんな……うぁあぁあああッ!


乳白色と黒ずんだ紫が混ざった粘菌に包まれ、肌が、肉が、少しずつ削られていく。
ストッキングを貫いてぎじぎじと脚を侵す痛みが、脊髄を抜けて脳をねぶる様に刺す。
喉の奥から呻きながら、ミスティは床の上で悶える。
喰われる。
肉体をじわじわと侵されながら捕喰される、そのおぞましい恐怖に、ミスティは喉も裂けんばかりに絶叫し続ける。
何とかして振りほどこうと、脚を壁に必死に擦り付ける。悶絶しながら床を這いまわる。



い、いやぁ、嫌ぁ、やだ、いやあああ!





カラカルさま、カラカルさまあ――ッ!




恐怖に泣き腫らすミスティの視界を、一瞬、赤い光が灼いた。
涙を焦がし蒸発させるような熱風が、ミスティの顔を煽る。



顔覆ってください、顔!


聞き覚えのある声の後、再び眩い熱と光が、炎が弾ける。




うあああぁっ! あっ、ぅあぁっ!





やだああ、やめてええっ!





もう嫌ぁああああッ!





うるさい! じっとしてないと、全身黒こげですよ!


ネブァ型アーデルをミスティの脚ごと焼いているのは、複装支援銃火器(マルチーズ)の火炎放射だ。
さらに増幅した激痛に、ミスティは床を、髪を、顔をがりがりと掻きむしり身を捩じらせる。
時間にして、十数秒。
それでもミスティにとっては、永遠に続く拷問にも等しい時間に感じた。
ミスティを捕えていたネブァ型アーデルは、隅まで黒ずんだ炭と化し、ぼろぼろと床にこぼれた。
喰われかけ、炙られたミスティの右脚も、見るも無残な赤いケロイドになり、未だじくじくと疼き痛む。



もうひと息、我慢してくださいね


息を切らしながら薄目を開けたミスティは、さらに自分の脚に銃口を向けたその人物を見る。
ピクシー・ボブ。
まさに彼女も、非常事態に乗じて囚われのマーメイを解放にしに来たところだった。
脚の激痛で起き上がれないミスティの傍らに、ピクシーはそっと膝をつき、そして。




うがあああああっ!


再び全身を貫いた強烈な痛みに、ミスティが背を曲げてびくんと跳ねる。
あろうことか、ピクシーは火炎放射で熱された銃口を、ミスティの火傷の脚に直接押し当てたのだ。



アーデルの肉片がまだ残っています!
放っておくと、ここからまた少しずつ喰われますよ





もういい、もうっ! やだああっ!


癇癪の子供のように泣きわめき、力の入らない両手でピクシーを押しのけようとするミスティ。
だが、ミスティは続けて、銃口をミスティの脚に押しつける。
アーデルのそれとはまた異なる、肉の焼ける悪臭と薄い煙。
ピクシーが銃を置いた頃には、ミスティは激痛に泣き果て、気を失っていた。
血と涙と煤でどろどろになったミスティの顔を見ながら、



あなたのカラカルさまとやらが、いったい何を企んでいるかは知りませんが





お互いここを生き延びなければ、上司に顔向けできませんよ


ピクシーは彼女の肩をよいしょと担ぎ、自分の肩に彼女の力の無い腕を回させる。
だらりと重心の落ちたミスティの身体を、壁面に手をついて支えながらようやく持ち上げたその時、ピクシーの背を凍らせたのは、階上からひたひたと、ねたねたと降りて来る、いくつもの足音。
