住処で彼の帰りを待っていた少年は想定より早すぎるそれに驚いた。
住処で彼の帰りを待っていた少年は想定より早すぎるそれに驚いた。
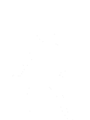


この前お前の目の前で殺されたやつといい、リウといい、あの一族は揃ってそうなのか





馬鹿言え


合流した後、夕飯を買いに屋台へ向かう。いつも通りヤクの売人と顔を合わせる。



まさか俺らが来るまで、いつもここで見張ってるのか





まさかネ


ははっと笑いながら、



その程度の労力、惜しむほど馬鹿じゃないネ





……そうか


急にトーンを変える。



すり替えたか?





まだだ


眉を潜めた。それに応えるように言葉を続ける。



三日後にあいつと一緒に、顔を出すことになった





……三日後か。確かか?





あぁ


足元の砂にしずくがぽたぽたと吸い込まれた。



……マズいネ





え


見上げた視線は脂汗を顎から垂らす彼の顔を捉えた。普段から緩みきった表情にしては珍しく、一層の不気味さを覚えさせる。



何がマズいんだ





……いや、俺の考えすぎネ





おい、言えよ





言ったって仕方ない。そうデショ?





……


それは確かにその通りであった。たとえ何らかの悪い情報が与えられたとしても、彼はその役割をただひたすらに果たすしかない。



――それでも





用事がある、行くネ


しばしの逡巡の間に、逃げられた。よほど都合が悪かったのか。それとも二つの椀を抱えてきた彼と顔を合わせたくなかったのか。
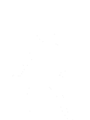


今の売人?





あぁ


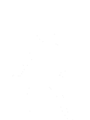


残念だ。会ったらこれを頭からぶっかけてやろうと思ってたのに


そう言って片方を少年に手渡した。ぶちまけられ損ねた汁物を啜りながら、少年は今見た男の挙動を伝えるべきかと悩んだが、結局やめた。本当にどうしようもないほど、彼らには行動を起こすだけの力がなかったのだから。
そしてその日がやってくる。少年たちはその日、目覚めてからしばらくのまどろみの中で半ば無意識に手を握り合った。日が沈む頃には屋上に出て、何をするでもなく夕陽を眺めて過ごし、その沈むまでの赤い色を目に焼き付けた。
夜の帳が下り街の明かりが空を照らし返す頃、彼らは地上に降り、人と人の合間をくぐった。相変わらず彼らは誰の記憶にも残らない、忌み嫌われるだけの浮浪児でしかなかった。路傍の草のように、勝手に産まれて勝手に死ぬだけの命。
そんな存在であることも、きっと今日が最後だ。
成功して救われるか、失敗して殺されるかの二択。それ以外の道はないだろう。
しかし彼らはどちらの想像をも片鱗さえ脳裏に思い浮かべることはなかった。何故ならどちらの道にしても、その先の未来を何も見ずに描けるほどの知識や教養を彼らは持ち合わせていなかったのだから。それ故にとても生き死にのかかったの大博打を打つ直前の子らとは思えないほどの落ち着きぶりを見せ、逆にそんな自分らの有り様が、彼ら自身に忘れていた不安を呼び覚ますほどであった。
握り合った手が今更になって失われた現実感を取り戻そうと互いを確かめる。都市のざわめきにひたすらに自分の欠片を見出そうとする。歩くリズム、流れる射光、濁流する文字。
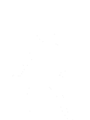


僕はヤクザだ


片割れがそう呟いた。隣の子に聴かせるつもりもない囁き。されど聞こえてしまっていた彼は、ならば自分は誰なのだろうと思った。声に出さずに思いつくままに動いた口の形を言葉に代えた。
俺は無意味だ。
彼らの言葉は彼ら自身に後ろ向きの勇気を与えた。
そしてそんな小さな行軍も終わりを告げる。
ビルを上り、人の見当たらない廊下を訝しみながら、最上階への扉を開けた。
彼らは暴力の嵐に迎えられた。
それは一瞬にして一方的な蹂躙だった。呆気にとられるまもなく二人の子どもは手足の関節を抑えられ、床に押し付けられていた。
自分の視点の場所を認識する間に縛り上げられ、ようやく見上げた先の視界で、その実行者がたった三人の大人でしかなかったことを知る。
一番奥の座椅子には先日と同じようにリウが座っていた。



三日もの間。俺が何をしていたかわかるか?


その言葉が向けられているのは自分一人だけなのだと彼は今更に気付いた。隣では先刻から止まらない殴打の音が聞こえ続けている。



お前の言葉は最も俺が懸念していた可能性を示していた。つまりお前らが愚かしくも向こう側に寝返ったという可能性だ


自分がその暴力から除け者にされたのは、ただ男娼であるからだという事実にすぎないことに思い至って、安堵の笑みを漏らしてしまう。
隣ではスリの子の顔面に革靴がのめり込み、骨ごと陥没するところだった。
泣いていた。



我々の縄張りを犯すことを見逃してやっていたつまらない薬売りは、簡単にお前たちを売った。二束三文の金と三本の肋骨と五本の歯を引き換えに、俺への忠誠を誓った。黒人の皮は高く売れるはずだったのだけどな。残念だ


リウは退屈そうに自身の爪を眺めていた。まるでそこに手があることを不思議に思うかのように。



無論、想定通りだ。元国連の人身売買機関が代償なく我々の影響下に入った。お前たちは予想通りのとても良い働きをした。だがそれで褒美をやるわけにはいかない、そうだな





……


隣の子どもの啜り泣きがリウの合図で瞬時に悲鳴に変わった。



返事をしろ。お前が返事をしない場合、関節が壊されるのはお前じゃない





はい、リウさん





よろしい。ケジメというやつが必要だ。あったものをあった場所に戻す。本来ならそれは簡単なことなのだが、お前らは貴重な俺の財産だからこそ複雑な手続きが必要になる


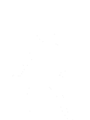


や、嫌だ……嫌、やや、や……やめてやめて……やめてください、お願いします!!!!!


隣の悲鳴に認識できる言葉が混ざり、とうとう少年は逸らし続けていた目をそちらに向けた。
顔から腹に至るまで、全身を青黒く染められた小さな肉塊が、右手首を布切れで固く縛られ、男に馬乗りにされた指先を短刀で切り落とされるところだった。
甲高い絶叫が響き渡る。



やくざという組織では指を詰めるという罰があったらしい。旧時代的で野蛮な方法であるが、スリから仕事を取り上げるにはこの上ない


馬乗りになった男は鶏肉でも捌くかのように、次の指をも簡単に切り落とした。音とも判別つかない声だけが響く。それでもリウの低い声だけは耳まで届いた。



お前は男娼を続けながら詐欺の訓練も始めろ。否とは言わせない。その元スリが人質だ。そいつは顔が良くないが、そういう好みの下衆にあてがうこともできる。今後のお前の働き次第だ


そして計五回、骨が叩き切られる音がしたあと、もう悲鳴は聞こえなくなっていた。気絶したのだろう。指のない右手だけが妙に活き活きとして見えた。
その時になってようやく彼は、部屋に響く唯一の音がもう泣くこともなく女のように淫らに笑う自分の声であったことに気付いた。
・
・・
・・・
・・
・
少年は階段を降りていく。汚物の臭いがむっとこみ上げて、薄暗いコンクリート隅に埃が玉になって固まっているのを視界の端に見つける。簡易な事務室の片隅に不自然にある地下室への階段を、そこにいた男たちはわざと見ないかのように仕事をしていた。
地下にたどり着く。扉を開ければもう一層臭いが強まり、思わず彼は眉をしかめそうになる。されど必死に、扉の先の者にそれを悟られないように力を込めた。
彼はちらりとこちらを認めただけで、本に視線を戻した。子供向けの簡単な日本語で書かれた小説だった。
先日はなかった車椅子に腰掛けたまま片手で器用に持ち替えて、たまに漢字辞典を繰る。それらは少年が金を払った書物のうちのいくつかであった。彼が暇を持て余しているのを見かねて、文字を学ばせるためにリウに購入を頼んだ。



いい便器だな


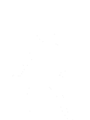


とうとう足がさっぱり動かなくなっちまってよ


彼は諦めたように、重い辞典を投げ出した。
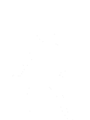


なぁ、なんでジャップはわざわざ種類が覚えられないくらいに多い中国語を使うんだ。プライドがないのか?





自分らの名前にも使ってるくらいだからな


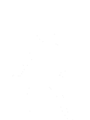


夜露死苦って漢字で読めるか?就学してから六年かけてもこの国の子どもはまともに壁の落書きも読めないらしいだろ。馬鹿じゃん


『宜しく』くらいは流石に読めるだろうけどなと首を傾げた。



良いから、早く書けるようになって俺に教えろ。婚姻届が書けないと結婚詐欺もできないんだ


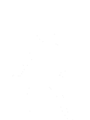


わかってるよ


車椅子の上で伸びをした彼は、この闇金融事務所で他の社員と隔離されたまま電話番をしている。言葉が喋れるなら誰にでもできる簡単な仕事。三日と食料が運ばれなければすぐに死に絶える、リウに生かされている命だった。
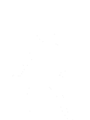


ずっと外に出ずここにいると、色んなことを考えるんだ





……例えば?


それは昔、彼らが同じ場所で住んでいた頃と同じように。
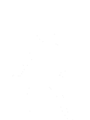


どうしてこうなったんだろうって





……


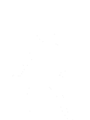


何を間違ったのかって考え続けたんだけどさ。やっぱり誰かに頼って助けてもらおうとしたのが間違いだったんだ。しかも自分から求めてすらいない救いに乗っかっちまったのがさ





やめろとけよ、そんな後ろ向きなこと考えるの


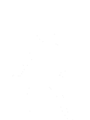


やめないよ。考えないとずっとこのままなんだから。それでさ、僕は思うんだよ。やっぱり僕たちが本当に手に入れるべきだったのは助けでも他の人の手でもなく、ただ強さだったんじゃないかって。誰にも負けないくらいの力だよ。そういうのをきちんと自分で手に入れて、その力でリウに立ち向かうべきだったんだ





……そいつにはとんでもない時間がかかるよ


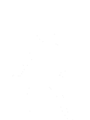


待つさ。ただその時を待つんだ


彼は指のある方の拳を突き出した。
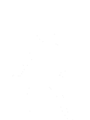


絶対、一緒に大人になるぞ





……それで強いヤクザになるってんだろ、わかってるさ


拳を突き合わせた。
車椅子の少年も彼も、自分たちが二人揃って大人になれる可能性が限りなくゼロに近いことを知っていた。どちらもいつ死んでもおかしくない命だった。
それでも、彼らは約束したのだ。
賢くなって金を貯めて技術を磨いて、いつかこの泥沼から逃れるだけの力を手に入れようと。いつか絶望の淵から自身らを救い出そうと。
・・・
・・
・
多額の借金をした酔漢が事務所に乗りこんできて、そいつの撃った流れ弾でその子が死んだと、もう片方が聞かされたのはそれから数ヶ月もしない頃の事だった。
