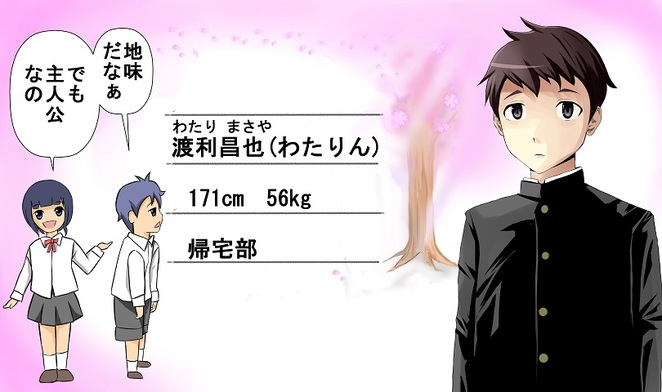眠いわけではないのだ。
ただ、どう時間を潰せばいいかわからないから、机に突っ伏して目を閉じてるだけなのだ。
楽しそうなクラスメイトの雑談が耳の中に飛び込んでくる。
楽しいはずの休み時間を、みんなはちゃんと楽しく過ごしている。
一旦机にうつぶせてしまうと、チャイムが鳴るまで動けなくなる。
目を閉じた暗闇状態で、なんの刺激も与えられない苦痛。
変わりたい。
充実した日々を過ごしたい。
誰かと普通に遊びたい。
あわよくば、彼女が欲しい。
僕はいわゆる、ボッチというやつだった。
それが数日前までの僕である。