第4話
第4話
遣らずの雨。
雨が降ると
あの店を思い出す。
最初に訪れた日が雨だったから、
かもしれないけれど。
雨の日にやってくるお客様のせい、
かもしれないけれど。
バイトの日には何故か
雨が降っているから、
かもしれないけれど。
この雨は
私の住んでいる世界と
あの店のある世界とを
隔てていて
雨をくぐって
私はこちらの世界に辿り着く。
……そんな気がする。
店に入ると
ふわりと空気が変わる。
コポコポとサイフォンの奏でる音が
沈みがちな気分を誘う雨音までも
別のリズムに変えていく。
あの猫のことと
あの紅い傘の少女のことを
オーナーに話すと
彼女は



それは「想い」よ


と呟いた。



「想い」?





ここはそういう街だと
言ったでしょう?


出来あがったコーヒーのひとつを
硝子のポットに移し替えながら
オーナーは歌うように言う。



あなたは本当に
気に入られているのね





……


オーナーの話は要領を得ない。
どうやら、先日
早退させられたのは
そのことに
関係あるようなのだけれども。



彼女らはいったい
なんなんですか?





迷っているのは私だと





……実際、
迷ってるでしょう?





……なにを





あなたの心の揺らぎが
彼らを呼ぶのよ


わからない。
硝子ポットを氷の中に沈めながら
オーナーは宙に視線を漂わせた。
コロコロと
氷がぶつかり合う音が響く。



でも
外で会うなんて……ね





……


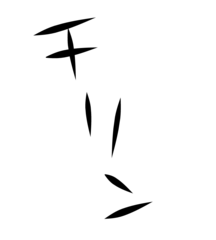
来客を表す音に
止まり木で揺られていたフォグが
わずかに身じろいだ。
鳥籠がキィ、と音を立てる。



営業、してる?





ええ。どうぞ


マスターが私に目配せする。
彼女は、カウンターの端の席に
腰掛ける。
外は雨。
雨の日は
「訳あり」のお客様がいらっしゃる。



……


このお客様は魔術師コスだろうか、
などと
思っている場合ではないのだろう。
彼女も、
あの「彼女たち」と同じかも
しれないと
そう、思うと。

大丈夫。
私は心の中で呟く。
ここは店の中だし
マスターも、フォグもいる。



ねぇ





「遣(や)らずの雨」って
知ってる?


彼女は窓に打ちつける雨を
眺めながら言う。
「遣らずの雨」とは
ここから帰ろうとする人を
帰らせまいとして
降って来る雨。
この店の周囲で降る雨に
どこか似ている。



雨はひとを閉じ込めるものよ


そうかもしれない。
私は彼女に倣って窓の外を見る。
雨で足止めを食う、と言う言葉もある。
傘があれば出ていけるだろうけれど
多かれ少なかれ
濡れるとわかっている場所へは
わざわざ出ていきたくは
ないものだ。
それを
「閉じ込められた」と称するのかは
人それぞれだけれども
雨を喜ぶのは幼い子供か

……フォグくらいだろう。



あなた、この雨に閉じ込められていると思ったことはない?


彼女はひそり、と声を落とす。



閉じ込、め……?


今回もまた
厄介なことになるかもしれない。
私は
つ、とマスターの姿を目で探す。
それを見咎めるように
彼女が私の袖を引く。



あなた、ここに来る時
なにか思い詰めてはいなかった?





それ、は


何故それを
知っているのだろう、なんて
もう
聞くほどのことでもないのだろう。



このままここにいると
元の世界に戻れなくなってしまう





雨に
行く手を阻まれてしまう





そんなことは……ないわ


私は頭を振った。
蝶を模したかんざしが
耳元でチリチリと音を立てる。
そんなことはない。
現に私は毎日ちゃんと
家に帰っている。
家に帰って、また朝が来て、
フォグが迎えに来て
そしてこの店に来る。
仕事が終われば
フォグを連れにしながら帰る。
その繰り返しではあるけれど
帰れなくなったことはない。
どちらかと言えば

帰れなくなりそうだったのは
彼女らに会った時だ。



……


あなたもそうなんじゃないの?
私を惑わせに来たのではないの?
私は彼女の紅い目を見る。



あの人は、
帰って来るって言ったのに





……


彼女の言葉に蘆屋を思う。



……音がするの


彼女は珈琲をくるりと掻き混ぜる。
カップの中で白と黒が
くるくると渦を巻く。



ああ、帰って来た、って玄関に行っても
誰もいないのよ。
風が窓を鳴らしているだけで





風か、って窓を見ると
そこに月があって


あの月をあの人も見てるのかな、
なんて乙女なことを思うじゃない?
月はあたしたちのことを
慰めてくれるわけでもないのにね。
誰かが遊びに来ることもない。
ひとり
ずっとあたしひとりだけ。
耳を澄ましても
せいぜい犬の遠吠えか
あとは、
枝から葉っぱが
パラっと落ちる音くらいで
人の気配など、まるでしない夜。
そんな中で思うの。
あの人は東京で
なにをしているんだろう。
あたしがこうして考えてるなんて
あの人は
思ってもいないんじゃないか
……って。



……


ああ、私と同じだ。
カップの中の渦を見つめたまま
私は彼女の言葉を
心の中でよみがえらせる。
私も
アメリカに行ったきりの蘆屋を
何度思い出しただろう。
彼も私のことを
思い出しているだろうか、なんて
淡く思う反面、
私のことなどすっかり忘れて
いるんじゃないか、と……。



向こうは忘れてるのにね


共にいようと言った誓いが
こんなにも簡単に
崩れてしまうものだったなんて。
それなのに
あの人が元気でいるのなら
あたしは明けない夜のまま
ずっとこの暗い夜のままでもいい
……なんて
月を見ながら
そんなことを思っちゃうの。



馬鹿でしょ





……いいえ


私も同じ。



それに、私たちだけじゃないわ


別れの歌や雨の歌が
いくつも歌われているように
別れを悲しむひとは
他にいくらでもいる。
雨の日にさまよった私のように
喫茶店に辿り着いた私のように
昔から
いくらでも……



七夕のふたりだって
年に1度しか会えないでしょう?





昔から、そうなのよ





……


彼女は、ふっ、と顔を曇らせた。
彼女が想う「誰か」を
話している時とは違う、



よくあること、で
済ませられるの?


まるで
そう思い込もうとする自分を
自分で諫めるような、
そんな顔で。



……


七夕のふたりは
年に1度しか会えない。
でも。
年に1度会える彼らは、



……私たちよりも幸せだわ





……


外は雨。
私の「想い」を閉じ込める雨。



私も雨だったら
あの人を閉じ込めておけたのかな


彼女の言葉が
じわりと私の中に染み込んでいく。



……私が、雨だったら


蘆屋をアメリカになんか
行かせずに済んだのかな……。



ねぇ


そう呼ばれ、袖を引かれて
私は彼女のほうに視線を向けた。
先ほどまでの暗く沈んだ彼女ではない、
どこか思い詰めた顔の彼女が
私を見上げている。



やっぱりあなたも私と同じだわ





ここにいたらあなたも
雨に閉じ込められてしまう





この街は、そんな「想い」の
吹き溜まる街だから





……





だから、


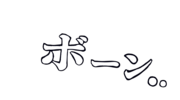
彼女がなにか言おうとした時、
時計が鳴った。
彼女の言葉を遮るように。



あ、





朔夜、時間よ


するりとマスターが
私と彼女の間に入って来る。



……え、でも





あとは任せて
あなたはお帰りなさい


マスターの声に
彼女が慌てたように席を立った。



あ……長居しちゃったわ
あたしも帰らなきゃ


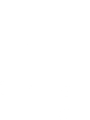


ごちそうさま


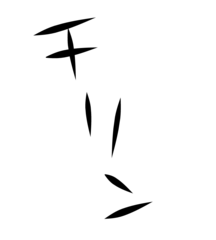
そそくさと立ち去るように
彼女は店を出て行った。
扉が開けられ、また閉まる。
湿った冷たい風が一瞬流れ込む。
吊り下げられた鳥籠の中で、
フォグが小さく鳴いたのが聞こえた。
あんな、追い立てるように……。
いいのだろうか。
私はカウンターを振り返った。
マスターは何食わぬ顔で
アルコールランプの火を消している。



他人(ひと)の想いに
流されちゃだめよ





……


彼女は初めて会った時と同じ笑みで
私を見る。
『この街は想いの吹き溜まった街』
それは、どういうことなのだろう。
ここは
いったい……
