翌日。
ヲロシヤ国が南カラフトに侵攻を開始した。
ヒノモト政府は、停戦命令を出した。
女監察官と研究員たちは、それを食堂のラジオで聴いた。
が。
研究施設は、そのことよりも、もっと身近な危機に直面していた。
翌日。
ヲロシヤ国が南カラフトに侵攻を開始した。
ヒノモト政府は、停戦命令を出した。
女監察官と研究員たちは、それを食堂のラジオで聴いた。
が。
研究施設は、そのことよりも、もっと身近な危機に直面していた。
ヲロシヤ国の特殊部隊が、研究施設を包囲したのである。



戦車もある! 揚陸艦でやってきたんだ!!





きっと痴女の腕を追ってきたんだよう





ちくしょう! 徹底抗戦するぞ!!





みんな下の階に移るんだ!





おっ、おう


一同、地下3階の研究室に移動した。
しかし、いきり立ってはみたものの、移動しているうちに冷静になってきた。
この勝てる見込みのまるでない、絶望的な状況を理解した。



集団自決しかあるまい


ひとりが言った。
みなが、うなずいた。



しかし、ただでは死なぬ





目にもの見せてくれる





みんなで痴女になろう


机の上に注射器が並べられた。
そのとき、天井から重い衝撃が走った。
特殊部隊が、警告の砲を放ったのである。



ヤツら、終戦のドサクサに紛れて、なにがなんでも痴女を奪う気だ





絶対に渡さん





痴女になって一網打尽にしてくれる


いや、よく考えれば、痴女になってしまえば研究成果を守ることがなおさら難しくなるのだが、しかし、彼らはすでに冷静な判断力を失っている。両者を無理に結びつけようとしたのは、このなかば狂った思考であった。
やけっぱちと言ってもいい。



1、2、3で、みんなで注射しよう!





おお





うん


女監察官も注射器を握りしめていた。
彼女も彼らと命運を共にする気でいた。
たった数日の滞在期間だが、研究に没頭し、祖国のためにと共に尽くした日々が、彼女を研究施設の一員にしていた。



いくぞ!





せーの!





1、2、3!


全員が注射器を自らの腕に刺した。
研究員は、徐々に痴女となった。
体がなまめかしくくねり、くちびるの奥からまるで別の生き物のように舌がのぞき、媚びた瞳となり、果実酒のような吐息をもらし、そしてじわじわと理性を失っていった。
が。
しかし。



そんなあ……


女監察官だけは変らなかった。



めんえきだ





こっ、うげん、こうたいはんのう、だっ





キミには、めんえきが、あった、のか


研究員が、あえぐように言った。
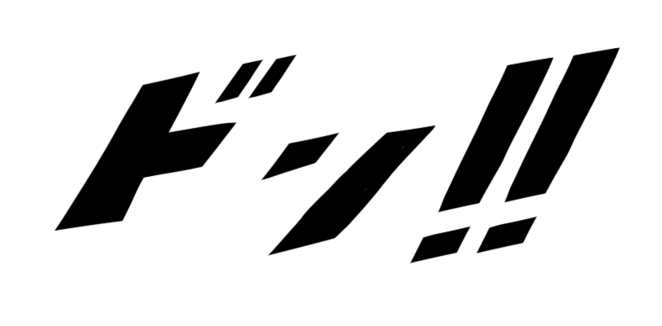
砲撃がした。
そして、ヲロシヤの特殊部隊が突入してきた。
女監察官は、ツバを大きくのみこんだ。



生きろ!


研究員が渾身の力をふりしぼり、女監察官を突き飛ばした。
突き飛ばした先には、エレベーターがあった。



い、き、て、くれ……


研究員たちは、痴女になりながらも、なんとか理性をふるいたたせ、女監察官を無理やりエレベーターに押しこんだ。
尻もちをついた女監察官の前で、扉がしまった。



…………


女監察官は、ただひとり、エレベーターで深く深く地の底へと降りていった。
※
女監察官は、鉄の壁に囲まれた最下層で、計器盤を眺めていた。
その中心にあるボタンを凝視していた。
それは厳重に保護された、赤くて大きなボタンだった。



このボタンを押せば、この層より上は爆発する。すべての研究成果が灰となる


女監察官は、ぼそりとつぶやいた。
それから、ひとり重々しくうなずいた。
大きく息を吐いた。
天井をあおぎ見た。



………………


女監察官は、またボタンを見つめた。
しばらくすると、その片ほほに、凄い、悪魔のような笑いが浮かびあがった。
彼女は冷然としてボタンを押した。
そして奥の『お召し寝台』に入った。
人知れず、冷凍睡眠によって完全に凍りついたのである。
※
その頃、地上では——。
真っ黒な雲が太陽をおおっていた。
瓦礫と化した研究施設に、雨が降っていた。
死体となった特殊部隊を、雨がうっていた。
そう。研究施設が爆発して、痴女ウィルスが気化し、雲となり雨となった、その滴が。
甲信越地方には、いつまでも降り注いでいた。
女監察官-終戦編 【完】
