乱暴な強い日差しが瞼を焼き尽くす。ああ、カーテンを閉め忘れたまま寝たっけとぼんやり思考を巡らせていると、近くでちっという舌打ちが聞こえた。
……舌打ち?
乱暴な強い日差しが瞼を焼き尽くす。ああ、カーテンを閉め忘れたまま寝たっけとぼんやり思考を巡らせていると、近くでちっという舌打ちが聞こえた。
……舌打ち?



寝坊する気かよ、メルド(糞)


低俗な罵り言葉に意識が覚醒する。いくら感情の起伏が少ないわたしでもひやりとしてしまう声であった。
慌てて瞼をこじ開けると、そこには昨夜持ち帰ってしまったサディスティックなビスクドールのアベルが腕組をして佇んでいた。たいそうご機嫌斜めなようで、外の空よりも鮮やかなスカイブルーの瞳は細められている。
――ああ、やっぱり夢ではなかったんだ……! どういう原理で動いてしまっているのだろう。もしかしたら人形を器に、悪魔が入り込んでしまっているのかもしれない。まあ、もしそうだったらわたしはもう死んでいるはず。
それにしても骨董品屋で見た時は儚げで悲壮感を漂わせていたというのに、今となっては真逆な印象である。小憎たらしい子どものようだ。
わたしは無言で後ずさるものの、ベッドから転げ落ちてしまい、その様子を見てアベルは噴出した。



はははっ、真顔でベッドから転げ落ちてだっせぇ!





ひ、酷い


消え入りたい気持ちが押し寄せる。
もう知らないと言わんばかりにアベルの存在を無視し、学校へ行く準備を始めた。水を吸った本をつぎはぎだらけのバックへ入れていると、アベルは眉をひそめてみせた。



どうしたんだ、このおんぼろ本
蚤の市で売ってる古本とか貸本屋の本以上に年季が入ってるけど?


下唇を噛み、勝手に本をいじりだすアベルを無言で睨みつける。
するとアベルは挑発するような笑みを浮かべてこちらを見くだす。



なんだ、言いたいことでもあるのか?





……なんでもないわ


……知ってる。こういう時、何を言っても変わらないということを。
生きてきて蔑まれることが多いと、相手を説得させるために労力を割かなくなる。
半ばあきらめたようにため息を漏らして部屋を後にすると、後方でアベルが針のように鋭い口調でこう言った。



アリシア
お前はそんなんだから”こう”なるんだぞ


力なく振り向くと、アベルは机に置いてある他のみすぼらしい本を手にとっていた。
まるでその痛み切った本がわたしだと、そう言いたいのだろう。
端から知っていることを指摘され、血が出そうなくらいに下唇を噛みしめた。

――ああ、反論できなかった。何て情けない。
ぐるぐると頭が回る。思考がかき混ざられる感覚は、いつ以来だろう。
昨日初めて会話したアベルという強烈な存在がわたしの頭を占拠しているのだ。
そもそも、ヴィスクドールと会話するという体験自体がおかしなものであるが。
授業もままならず、暇があれば空ばかり見ていた。
すると案の定、ニヤニヤとした意地悪い表情をした女の子の集団がこちらへ来て、取り囲まれる。
いつもであればびくつき、身を縮めるところだ。
されども今日のわたしは違う。自分とは真反対なアベルにどう対処すればいいか、そればかり考えているからだ。



あーら、今日は度胸があるじゃない?
『ママ―』って泣き出しそうな顔しないだなんて


口火を切ったのは、リーダー格である双子の妹・エリゼであった。彼女は肩につくかつかないかくらいのウェーブのかかったブロンドを揺らし、舌を出した。



あ、そっかぁ
貴方には『ママ』なんていないものねぇ?


ズキッと心に突き刺さりそうになった矢を、いつもは気にしないふりをしていた。しかし今日のわたしは違った。その矢を掴み、エリゼに矛先を向けたのだ。



……あなたとわたし、どこが違うの


これは素朴な疑問であった。
双子なのに、そこらの姉妹よりも同じが血が流れているはずなのに、どうしてわたしはいつまで経っても惨めで……。
今まで何も考えないようにしていた。思考停止をすることによって自己防衛をしていた。
わたしは人形でいることを望んでいたけど、そもそも人形は思考はなくともその美しい容姿で愛されることは可能だ。わたしは、違う。人形のように麗姿でもないし、思考は希薄――こんなわたしはもう、捨ててしまいたい。
エリゼは、座ったまま見上げるわたしを睨みつけて



はぁ?


と言うが、わたしは構わず続けた。



あなたが否定したくても、わたしとあなたは血がつながった姉妹なのよ


その言葉に、周りで聞いていた野次馬たちがざわつきはじめる。
どうやら、周囲の皆はわたしとエリゼが姉妹であることを知らなかったらしい。ずっとわたしが黙っていたから、エリゼもうまく他人のふりをしていたのだろう。
エリゼは腕を組んだまま固まっていた。
もともと大きかった彼女の目が更に大きくなっていて、よく見ると眼球は震えていた。



…る、さい





エリゼ、もう……





うるさい! あんたなんかと私は違うの……!


それは今まで聞いたことのないほどに怒気を含んだ声だった。
エリゼの整った顔がみるみるうちに歪んでいく。
ああ、わたしがそうさせてしまったんだ。
ちくりと罪悪感がよぎったものの、事実を述べただけであるからどうしようもない。
行き場のない手をエリゼに伸ばすと、エリゼは思い切りそれを振り払った。赤くそまっていく自身の手の甲をじっと眺めていると、エリゼは今までで一番低い声を出した。



あんた、首にかけてるそれ……





え?


胸元を見ると、今まで気にも留めていなかったものが首にかかっていた。
昨夜、アベルがくれた時計型の鍵であった。
まるでわたしの鼓動と連動するように、その鍵の秒針も進んでいて、あるのが当然なくらいに一心同体となっていたのだ。
エリゼがいきなり、鍵のチェーンを掴みかかる。心臓がとまりそうなくらいに驚愕し、ワンテンポ遅れて返してと言おうとする。しかしその必要はなかった。

エリゼが声にならない悲鳴を喉奥に飲み込み、手を引っ込めた。エリゼは口を空けたまま、こちらと鍵を交互に見て現状理解に努めている。よく見ると、チェーンにつかみかかったエリゼの指が少々赤みを帯びていた。



あ、悪魔!





え?


よく分からない罵声を浴びせられた後、彼女たちはそそくさと走り去った。わたしはただただ、小刻みに震えるエリゼの肩を眺めることしかできなかったのだ。

夕暮れ、刻は4:30。
ふぅと息を吐きながら、ブルジョワであろう美しい女性が子犬を連れて歩く様子を見ていた。子犬を慈しむ女性は聖母のようで、正直無条件の愛を注がれる子犬が羨ましい。少々険しい表情になっていたのか、子犬がこちらを見て怯えたように後ずさった。
――ああ、結局わたしは惨めだ。
誰からも愛されない人なんていないと神父様がおっしゃってたけど、わたしは誰からも愛されていない。
神父様だって柔和な微笑みを浮かべていたけどもそれは事務的なもので、目はとても冷たかった。これが厳しい現状だ。
少しでも気を緩めたら激しい慟哭が口から洩れそうで、ぎゅっと口元を引き締める。そのまま地面を見て歩いていると、視界の隅に黒い何かがよぎった。
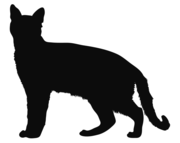



黒猫……?


ミィアウ、と返事をするように黒猫が応える。毛に埋もれつつある金の眼が夕陽よりも眩しい。
黒猫は首輪をしていて、そこに小さな紙が挟まれていた。
黒猫は逃げようとしないので、興味本位でそれを引きぬく。すると、紙の近くにあった鈴がチリンと鳴った。
青空のような空色の紙に金文字で
『Lettre d'invitation de la Sérénade<セレナーデ(夜曲)への招待状>』
という走り書きがある。
もしかしたら金持ちの家の猫で、これは夜会の招待状みたいなものかもしれない。



とんでもないことをしてしまったかも……


そうだとしたら、勝手に見たらまずい!
慌てて招待状を猫の首輪に挟みなおそうとするものの、猫は素知らぬ顔でさっと避ける。



あ、ちょっと!


猫は気高い表情を浮かべ、首をくいっと動かした。それがなぜかついてこい、と言われているように錯覚してしまう。



どうしよう……あ


すると不思議な現象に気づく。
持っていた招待状の色が変わっているのだ。先ほどまでは空色一色だったのに、下方が茜色のグラデーションになっているのだ。よく見ていると、今度は上方が空色から群青色に変わり、点々と星のような金粒が浮き上がってくるではないか。



すごい、何これ


金粒が集い、今度は粒同士をつなぐ金の線が浮き上がる。星座かと思いきや、それは文字であった。
Vite! <急いで!>
と、書かれている。ハッとして先程の黒猫を見ると、ちょうど前方の曲がり角を左に曲がったのか、黒いしっぽがふらりと見えた。



待って、あの、これ返したくて!


猫に話しかけてどうすると自らつっこみを入れつつ、走り出す。何もないところで躓いて地面とこんにちはしながらも、スカートと招待状を握りしめつつのろまな足を酷使した。
猫は楽しそうに尻尾を揺らしながら、わたしとの追いかけっこを楽しんでいるようだった。
何分間走っただろうか。
ちょうど空が招待状と同じようなアイリス、ラベンダー、マリーゴールドの花が咲いたような舞台へ変わる。
華やかな舞台に、高貴な黒猫と、冴えない少女というちぐはぐな奇譚ができあがると、最後は――。



あ、やっと堪忍したのね。もう!


やっと立ち止まった黒猫をキャッチすると、黒猫は満足そうにミャーウと鳴いた。
何がミャーウだ、全く。
その場でへたりと座り込んで息を整えていると、地面に色とりどりの影が映っていることに気づく。



あれ、ここ……サン・セヴラン教会じゃない


いつの間にかわたしの住まう5区にあるサン・セヴラン教会に辿り着いていたようだ。ゴシック建築の小さな教会で、パリ最古の鐘がある。
なんという芸術!
夕陽が美しいモダンなステンドグラスと共演して、地面というスクリーンに芸術作品を映し出しているのだ。あまりの美しさに背筋が凍り付きそうだった。
そういえば、わたしっていつも今まで綺麗な景色に目を留めることが少なかったっけ。見渡せば、日常にはこんなにも絵画的で綺麗な光景が転がっているのに。



猫さん、どうしたの?


黒猫は慌ただしくその場でぐるぐる回ると、地面をカリカリとひっかき始める。
いったい全体どうしたというのか。
よく見てみると、そこには小さな穴がある。そこをなぞると、胸元がじりじりと熱くなる。熱くさせている正体は、アベルがくれた時計状の鍵であった。針は4:43を指している。



もしかして……


ステンドグラスの映る地面、それがまるでドアの形のようで、本来ドアノブがあるであろう場所に穴。きっとこれは、鍵穴なのだろう。
人間らしく胸が高鳴り、緊張していた口元が緩む。
左手には夕暮れ色の招待状、右手には夕暮れ色の鍵、そして頭上には本物の夕暮れ。まるで物語の始まる条件が揃ったようだ。

カチッ。
恐る恐る鍵穴に鍵を入れ、回す。そして抜く。
すると、ガーゴイルを引きずるようなゴゴゴという重音が轟き、足をよけようとしたその時だった。



あれ?


これはおかしい、と思った時にはもう遅かった。地盤沈下したように少し下がった地面に冷や汗が流れる。



猫さん、これ……!


そこまで言いかけた時、自身が座り込んでいたところを中心として5m四方の地面がいきなり沈下したのだ。つまり、穴があいた状態と同じ状況である。



や、やっぱりいいい!


ひゅううっという冷たい風を全身に受け、深い穴へ落ちていく。
一足先に落ちていく地面を見つめながら、生まれてこの方あまり感じたことのない恐怖感を味わった。
黒猫は斜め上で同じく落下しており、慣れた表情でこちらを楽しそうに見ている。慌てて黒猫を抱き留め、せめて黒猫は助かりますようにと祈る。



神様、いらっしゃるのならお助けを!


と十字を切りながら、敬虔なカトリック信者であることを表していると、徐々に下方から淡い橙色の光が近づいていることに気が付く。
まるで最近読んだ『不思議の国のアリス』のような状況だが、運の悪いわたしがアリスのように助かる確率は低いだろう。目をぎゅっと瞑り、絶望でガクリとうなだれていると。



おわ!


まばゆい光に包まれると、体に柔らかい衝撃が走る。どう考えても固い地面ではない。
腕の中から猫がすっとすり抜ける感覚が伝わり、恐る恐る瞼を持ち上げた。
視界に広がる広い空間――数多の本が本棚に収められていたり、床に散乱していたりしており、全体的に懐かしさを感じさせるセピア色に包まれている。
天井は高く、自分がさっき落ちてきたであろう穴が不自然にぽっかりと空いていた。下を見ると、衝撃を和らげてくれたであろう、雲のような柔らかい羽毛絨毯があった。ありえないくらいにふわふわで、自分の体重で20㎝以上も沈んでいる。
カツン。
突然響いた靴音にびくっと肩を揺らす。
目線を前方に向けると、誰もいなかったはずなのに目の前には品のある美男子が立っていた。服装は黒色のフロック・コートの下に白いシャツ、ネクタイで少し明るい色のズボンを着用している。大きめのトップ・ハットが彼を更に紳士らしく仕立て上げていた。身長の彼を見上げるには首が痛くなる。



き、れい……


自然と口から洩れた言葉にはっとして両手で口を覆う。その際、持っていた招待状をひらりと落としてしまった。
少し童顔である青年はふわりと微笑んでしゃがむと、落としてしまった招待状を拾い上げる。



お嬢さん、招待状を受け取ってくれてありがとう。歓迎するよ


艶のある黒髪を揺らし、眼鏡越しから見える金色の瞳が輝いた。思わず見惚れていると、カシャンカシャンという不気味な音が後方から聞こえる。音に誘われて振り返ると、そこには何と……。



おいオズウェル!
久しぶりに人間の女の子が来たって本当か!?





が、骸骨!?





失敬な! 俺はれっきとした英国紳士だ!


そう、文字通り肉も皮もない骸骨がこちらへ歩み寄っていたのだ。
心臓が口から出そうになっていると、オズウェルと呼ばれた美青年が呆れたような表情でたしなめた。



おいおいスケル・トーン、女性を怖がらせてはいけないよ。
少し引っ込んでてくれないかい?





ひ、ひっでぇ奴!
俺だって生前はお前より優れた容姿で……


何が何だか分からない状況で頭がパンクしそうだ。いきなり地面に穴があき、落ちたら本の世界。そして目の前で美青年と骸骨が口論を繰り広げている。
ああ神様。わたしが何をしたというの! 涙目でまた十字を切っていると、クスクスという押し殺した笑い声が斜め後ろから聞こえる。



今の気持ちはどうだ、アリシア


歌うような旋律で言葉を紡ぐその声に聴きおぼえがあった。



な、何でここにいるのよ。アベル!


そこには、本の山の頂上に座り、悠々と読書に耽るアベルがいたのだ。アベルは読んでた本を投げ捨てると、両手を広げて滑稽に笑う。わたしの質問を無視し、凛とした声で語りだす。



さあ、アリシア。
『情念論』によると、人間には驚き・愛・憎しみ・欲望・喜び・悲しみが基本情念にあるらしい。
今の気持ちはそのうちのどれかな?
もしくは、どの情念を併せ持っているかな?





……驚き。あと、たぶんだけど……


ちらりと周りを見渡す。すると他にもちらほらと人(?)がいて、こちらへ好奇の目を向けていた。



『たぶんだけど』、何?


アベルはにぃっと怪しく微笑み、目を細める。アベルの催促に、子どもっぽく大きめの声で答えた。



喜び


すると、アベルが待っていましたとばかりに手を叩き、カラカラと笑った。



Super!<素晴らしい>!


それにつられて周りも和やかな雰囲気となる。口元をもごもごさせながら少し微笑んでみせると、スケル・トーンと呼ばれた骸骨がわたしの手をとって立ち上がらせると、いきなり爆弾発言を口にした。



アリシアだっけ?
お前を見てると俺の胸骨が震えるんだがどういうことなんだ……もしかして、死後初めての恋かもしれない





はい!?


その場にいた皆が口揃えてそう言う。わたしももちろんそのうちのひとりだ。
わたし、今……生まれて初めて骸骨に告白されたよ。どういうことなのかしら。
めまいを覚えていると、スケル・トーンさんの頭に重そうな本がクリーンヒットし、



いだ!


と悲鳴をあげる。今、ゴキッていったけど大丈夫かしら。



おい骸骨野郎。アリシアは俺の操り人形なんだからとっとと失せろ。
その骨、犬のおやつとしてしゃぶられてもいいのか?





んだとゴラァ! ただの古臭い人形のくせに……お前は貴族のままごとにでも使われてろ!





ほーう、言うじゃないか


アベルからはフランスのスラング、スケル・トーンさんからはイギリスのスラングが飛び交い、本格的な喧嘩が始まる。何て喧嘩っ早い人(人ではないけど)なのだろうか。だが、オズウェルさんの咳払いひとつでシーンと静かになる。



アベルとスケル・トーンは敬遠の仲でね。あれは日常茶飯事なんだ。
それはそうとアリシアさん、だっけ?
アベルから話を聞いてるよ。
『セレナーデ(夜曲)の鍵』に魅入られた存在――とても興味深い


オズウェルさんがわたしの首にかけている鍵を指さすと、わたしの前で優雅に跪いた。



ここ――サン・ゼヴラン教会の庭は、中世の時代ではシャルニエ(死体置き場)だったんだ。
ちなみに僕は生前黒猫で、アベルはヴィスクドール、スケル・トーンは英国紳士だったんだよ


改めて紹介に預かったアベルは口をすぼめたまま肩を竦め、スケル・トーンさんは紳士という単語を聞いて背筋を伸ばした。



改めて――ようこそ、異形が集う秘密の図書館『セレナーデ(夜曲)』へ


怪しく笑ったオズウェルさんは跪いたままわたしの手をとり、手の甲へ口づけを落とした。
※ダイジェスト版はここまでです。ご精読いただき、ありがとうございました。
