二つ並べた布団の上に初音は座り込んでいる。
隣の布団に入った久成を見下ろし、そっと声をかけてくる。
二つ並べた布団の上に初音は座り込んでいる。
隣の布団に入った久成を見下ろし、そっと声をかけてくる。



おやすみなさいませ、久成様





……ああ


久成は妻に背を向け、布団をかぶる。
毎晩のように、初音はこうして布団の上に座っては久成が寝入るまで眠ろうとしない。
しかし隣で黙って見つめられていればなかなか寝つけぬものだ。初音が嫁に来てから一月の間、久成は少々寝不足だった。
それは初音も同じことのようで、佐和子の話では久成が学校へ行っている昼の間に眠ってしまう日もあるらしい。全く本末転倒である。



お前も今夜は早めに眠ったらどうだ。
今朝は小豆飯の為に早起きをしたのだろう?


妻に背を向けたままそう告げると、すぐに答えが返ってくる。



でも……。
久成様に私の寝姿を見られるのは恥ずかしいですから……





お前がどんな顔でも気にしないと、以前も言ったはずだ





……それでも、です。
どうか私のことはお構いなく、お休みになってください


このように、初音は頑なに寝ているところを見られるのを拒んだ。
夜は久成が寝つくまで布団に入らず、朝は久成が目覚めるよりも早く起床して布団まで片づいているのが常だった。
それで何か重大な不都合があるわけでもないのだが、久成は初音が無理をしてまで寝姿を隠す気持ちがいまいちわからない。



……まあ、好きにするがいい


寝かせるのを諦めて目を閉じると、すぐに妻の穏やかな声が追い駆けてきた。



ありがとうございます、久成様。
また明日……


また明日。
初音はそう言ったが、明日の朝はまた違う顔をしているのだろう。
ふと久成は今朝方目にした、小豆飯に目を輝かせる初音の顔を思い浮かべていた。
あの顔をいつまで覚えていられるだろうか。
明日、違う化け方をした妻の顔を見たら、すぐに忘れてしまうのではないだろうか。
そう思うとわずかな寂しさが胸を過ぎったが、初音の為にも口にはするまいと決めた。きっと気に病むことだろうから。
翌朝。
久成が目を覚ました時、隣にはまだ布団があった。
珍しいこともあるものだと、久成は寝ぼけ眼で隣を見やる。
実を言えば、そのうちにこんな朝がやってくるのではないかと思っていたのだ。初音も毎朝早起きをするのは辛いだろうし、その上夜は遅く寝つくのではそのうち起きられない朝もあるだろうと予想はしていた。
たった一月でその日が訪れたのはさすがに予想外だったが、寝顔を見たと知れば初音はいい顔をしないだろう。なるべくなら見ないようにしてやろうと、久成は恐る恐る隣の布団の様子を窺った。
だが隣に敷かれたままの布団に、当の初音の姿がなかった。
代わりに、久成の布団の中にいた。



すう……すう……





は……初音!?


なぜかこちらの布団に潜り込んだ初音が、久成の身体にぎゅうとしがみつく格好でいた。そのまますやすや寝息を立てていた。
久成が色を失くしたのも詮無いことだろう。



初音、起きろ





ううん……


取るものもとりあえず布団の中の妻を揺り起こすと、初音は唸って鼻をひくつかせた。朝の光の中でそれが人間の鼻であることに気づき、一層決まりの悪い思いがした。
ここにいるのは化けている初音だった。
昨日と同じ顔をしているようだった。昨夜、眠る前に思い起こしていた、記憶の中にある顔立ちとつくりがよく似ていた。
昨日の妻の顔を覚えていたことに、久成は自分で驚いていた。見慣れぬ顔だと毎日のように思っていても、なかなかどうしてよく見ているものらしい。
思えば初音が昨日と同じ顔をしているのも初めてのことだ。
普通の女ならば当たり前の話なのだが、初音が相手だとかえって奇妙に思えてならない。
何にせよ、このまま初音を起こさないように布団を出るのは至難の業だろう。それほどに強く抱きつかれていた。



これは、どうしたものか……


久成が布団の中でそわそわしていると、やがて初音の閉じた瞼が震えるように動いた。ゆっくりと開いた眼が二度、三度と瞬きをした後、唐突に大きく瞠られた。
次の瞬間、初音はがばっと飛び起きる。



ひ、久成様、これはどうしたことでしょう


寝起きのかすれた声で初音は言い、その後すぐに自分の顔へ両手を当てる。
撫でるように頬と、崩れた髪と、それから顔の横にある耳を確かめて、途端に深い吐息と共に呟いた。



私……ちゃんと化けたままで……





それは大丈夫だ


久成が頷くと、初音は表情を和らげた。胸を撫で下ろしている。



よかったです。
みっともないところをお見せせずに済んで


残念ながらそうとも言い切れぬようだった。髪は崩れてあちらこちらが解れていたし、頬にも数本張りついている。着物も前がはだけていたので、久成は目を逸らしながらかいまきを押しつけた。



とりあえず、これを着ろ





……?
ええと、かしこまりました


初音が怪訝そうにしながらもかいまきを羽織ったのを横目で窺い、ようやっと視線を戻す。初音も久成を見て、小首を傾げてみせた。
新米夫婦の閨に、一時の沈黙が落ちる。



全く、どうしたことかと尋ねたいのは俺の方だ


久成は布団の上に胡坐を掻き、腕組みをして妻を見据えた。



なぜお前は俺の布団の中にいた。
お前の布団はそこにあるのに


隣にある空っぽの布団を顎でしゃくる。
向かい合わせに座った初音は、言い訳をする子どもの口調で答えた。



昨晩はことさらに冷えましたから、つい……





それで俺の布団へ入ってきたと言うことか





はい……申し訳ございません、久成様


初音が項垂れる。
素直に詫びられると、それはそれで居心地悪いものだった。
大体、久成も初音を女房と呼ぶくらいなら、一つの布団で寝るくらいどうということもないはずだ。しかし共に暮らし始めてから一月以上、久成は初音と衾を同じくしたことがなく、それゆえに今朝の出来事には何とも言えない戸惑いを覚えた。
初音のことを妻だと認めているし、あどけないふるまいにも健気さにも愛着を持っている。だが初音は毎日顔の変わる女だ。普通の女と同じ扱いをしてよいのかもわからぬまま、今日まで同衾する気はつゆとも起こらなかった。初音の方もこの家での暮らしにすら慣れていないふうで、特に何も言っては来なかった為、これ幸いと放ったらかしにしておいたのだ。
どう言って聞かせるべきか、そもそも言い聞かせておく必要などあるのか。久成は一人煩悶した。



……お前にはまだ教えていなかったが、夫婦は同じ布団で寝ることもある。
お前は悪いことをしたというわけではない





そうなのですか?


久成が切り出した言葉に、初音は目を瞬かせた。
物問いたげなそぶりにも見え、話の腰を折られる前にと語を継いだ。



しかしお前は、まずこちらの暮らし方に慣れるべきだ。
夫婦らしくするのはそれからでいい。
さしあたっては、毎日同じ顔に化けられるようになるのが先だ





はい、久成様


もっともらしく初音が頷く。
その後でようやく思い至ったようで、崩れた髪に手を当てている。
久成はぎこちなく手を伸ばし、眼前にいる妻の頬を撫でた。



今朝は、化けたままでいられたな。
それはよい兆しだ





はい……私、初めてでございます。
こうして朝まで化けたままでいられたのは


大分慣れてきたのだろう、そう思い、久成も口元を緩めた。
今までは一度寝付くともう化けたままではいられなかったとのことで、それゆえに初音は久成よりも早く起き、身支度に手間を掛けていたのだから。



では、身支度を整えてくるといい


久成は妻を促した。
かいまきを羽織ったままで立ち上がった妻へ、もう一言添えておく。



だが顔は、出来ることならそのままでいるようにな。
俺もそろそろ、お前の顔を覚えておきたい





この、顔でございますか


怪訝そうにした初音が、自らのふっくらした頬に触れる。
顔つきは昨日小豆飯を前に輝いていたものと、勝なことを口にしていたものと同じだった。



久成様は、この顔がお好きなのですか





前にも言った通りだ。
俺はどういう顔の女房でも頓着しない、ただ毎日同じ顔でいてくれたら、それでよい





承知いたしました、精進いたします


ぴんと姿勢を正して答えた初音は、かいまきを羽織ったままで部屋を飛び出していった。
布団を上げるのを忘れていったので、久成は苦笑しながら二人分の夜具を片づける。片方の布団にだけ温もりが残っているのを、決まりの悪い思いでしまい込む。
実のところ、久成は初音の『みっともない』姿を知っている。
初音が嫁に来てすぐの頃、明け方にふと目が覚めて、何気なく隣の布団を覗き込んだ。



……初音、か


そこにいたのは化ける前の初音だった。
女ではなかった。
人でも、なかった。
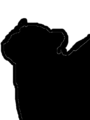


すう……すう……


雨戸からの隙間明かりに見た姿を、久成は厭うことも恐れることもしなかった。



どんな姿であっても。
お前は確かに、俺の妻だ……


どんな顔をしていても、どんな姿をしていても、初音は初音だと思っていた。もっとも、当の初音が頑として見せたがらないのだから、その思いも本人に対しては黙して語らずにいた。
いち早く身支度を済ませた久成は、囲炉裏端へと足を向ける。
そこでは佐和子が朝餉の用意をしていて、兄に気づくと心なしか安堵した様子を見せた。



おはようございます、兄上。
今朝はのんびりしていらしたのですね





ああ、初音が寝坊をしていたからな。
起こす手間がかかった


相手が妹と言えどありのままを打ち明ける気はしなかった。簡潔に答えると、佐和子も腑に落ちた様子で微苦笑する。



やはりそうでしたか。
昨日は日が昇る前から起きていらしたんですもの、私も案じておりました





先程起きた。
今は身支度の真っ最中だろう


久成は言い、何気ないそぶりで付け足した。



昨晩は珍しく、化けたままで寝入っていたようだったからな


飯杓子を持つ佐和子の手が止まる。
はっとしたようにこちらを向く。
久成が顎を引くと、佐和子は顔をほころばせた。



初音さんも、だんだんとここの暮らしに慣れてきたのでございましょう





そのようだな


仕事のある久成が、時間を気にして食事を始めた頃、ちょうど初音は囲炉裏端へと現れた。



お……おはようございます


言いつけ通り、顔は変えぬまま化粧を施してきた。髪を結い直し、着物もきちんと身に着けた姿は、昨日とまるで同じように見える。たったそれだけのことが、久成には無性に嬉しく思えた。
佐和子も同じなのだろう。挨拶をした初音に、明るく声をかける。



初音さん、兄上に白湯を差し上げてください





かしこまりました


初音はいくらかは慣れた手つきで、土瓶から湯飲みへと白湯を注ぐ。そしておずおずと湯飲みを差し出してくる。



久成様、どうぞ


それを受け取った久成は、昨日とまるで同じ顔に対し、照れながら告げた。



今日の身支度は上出来だ


好みの顔であろうとなかろうと、色気があろうとなかろうと。
ただ、初音が昨日と同じ顔でいる。記憶と同じ顔でいる。そのことが何よりも幸いだった。
夫の思いを、新妻はどこまで汲めたのだろう。しかしその時、確かに笑んだ。



ありがとうございます、久成様


それから佐和子と顔を見合わせて、もう一度笑い、二人の様子を眺める久成も、つられるように照れ笑いを浮かべた。
