十二月二十四日がクリスマスイブで二十三日がイブイブなら、二十二日はイブイブイブだろう。
十二月二十四日がクリスマスイブで二十三日がイブイブなら、二十二日はイブイブイブだろう。
そんなことを最初に言い出したのは一体誰なのだろうか?



……ま、それはそれとして


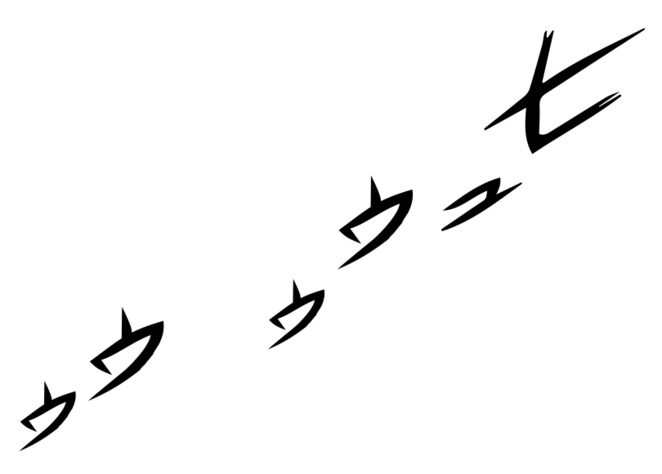



……寒っ!


大学最寄りの駅を出た勇太は、容赦無く襲ってくる寒さに身を震わせ、そしてそっと溜息をついた。
目の前に広がる駅前商店街は既にクリスマス一色に染め上げられてしまっている。まだ二十二日なのにもうクリスマスかと錯覚しそうだ。一方、十一月からこの光景なので見慣れてしまった感も、確かにある。



ま、別に、どうでも良い、か


クリスマスに、特別な感慨は無い。商業主義的な華やかさに踊らされることが生理的に嫌だったし、無宗教の者には関係無い、とも思っている。
勇太の家族も、クリスマスはあまり派手に祝わない主義。幼い頃からの、少し豪華な食事と小さなプレゼントだけのクリスマスに慣れている勇太には、クリスマスの盛り上がりは理解できない。
だが、それでも。



……はあっ


知らず知らずのうちに溜息が出てしまうのはどうしてなのだろうか?
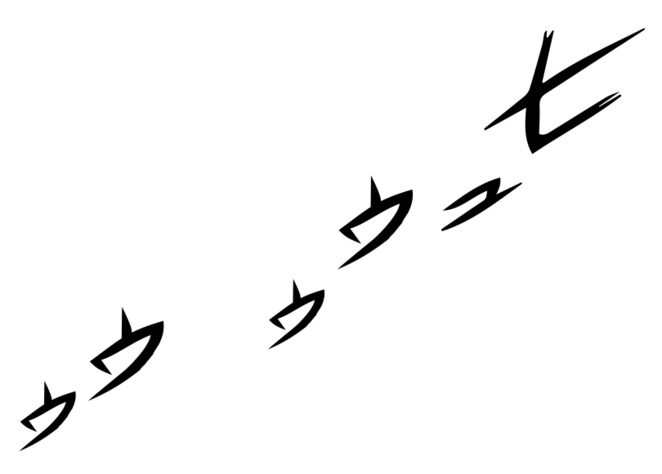



何でこんなに寒いんだ……
冬だからしかたないけど


開店直後の、それでも静かな賑わいのある駅前商店街を横切り、大小のビル群が真っ直ぐ続くオフィス街に入る。
既に始業時間から一時間ほど過ぎている時間だからか、街角は静かな活気に満ちていた。時折、鞄や茶封筒を小脇に抱えたスーツ姿の男女が足早に勇太の横を擦り抜けていく。



しかし


いつも思うのだが、ここを歩く度、自分の格好――カジュアルな上下にリュックとギターケースを肩に掛けている――が殊更奇異に思えてしまう。
それは多分、ここを通る学生の大部分が感じていることだろう。だが、勇太が通う帝華大学理工科学部はこの街の中にあるのだから仕方が無い。綺麗に並べられた石畳の道を、勇太は意識してしっかりと踏み締めた。
自分とあまり年が変わらないようなスーツ姿の人々の目線を気にしつつ、そっと腕時計を見る。まだ十時五分、二限目が始まるまでまだ二十五分ある。



これだったら、もう一本遅い電車でも良かったな


そう思うと急に気が緩む。



ふわぁ……


思わず、道の真ん中で大欠伸をしてしまった。




……


近くでくすりと笑う声が聞こえて、慌てて口を押さえる。
大欠伸を見られたことが恥ずかしかったし、大学生は暢気だなどと思われるのが何となく癪に障る。まあ、勇太のこの状態を見たら誰だって『大学生は忙しい』なんて思わないだろうが。



……


勇太は再び溜息をつくと、なるべく気を張るようにして大学に向かって歩き出した。
だが。



ふわわぁ……


歩いていても自然に欠伸が出てきてしまう。
欠伸の理由は、分かっている。
昨日、高校時代から友人達と組んでいるバンドの今年最後のライブと忘年会があり、勇太は仲間と共に夜遅くまで飲んでいたから。



……何で冬休みにならないうちにやるんだ?


バンド仲間は皆大学に進学している。だからわざわざ学校がある日にやらなくても良いのではないか。このライブの日程が決まった時、バンドのまとめ役であるボーカルの男にそう文句を行った覚えがある。



そりゃあ、
冬休みに入ったらみんな色々と忙しいだろ


勇太のこの問いに、そいつはしれっとした顔で答えた。



バイトとか、
カノジョとデートしたりとかでさ


そうだった。勇太以外のバンドのメンバーには皆『カノジョ』がいるのだ。そのことに気付いた勇太は、心の奥底で知らず知らずのうちに溜息をついていた。
更に。



勇太もカノジョつくればいいのにさ


忘年会と称して居酒屋で飲んでいる時にドラムの男がそう言ってきたときも、勇太は心の奥底で深い息を吐いた。



……


何故、『カノジョ』という大切なものを、皆簡単につくることができるのだろうか? 脳裏に生じたのは、その疑問。だから。



もてるんだろ?





うーん
……何か、面倒


勇太はいつも思っていることをはっきりと口に出した。



面倒~?





何だよ、それ


勇太の言葉に、仲間全員が驚く。
彼らの、驚いたような、信じられないといったような顔を思い出し、勇太は石畳の道を歩きながら一人くすっと笑った。
本当は、『面倒』という言葉一つでは片付かない気持ちを、『カノジョ』という単語に持っているのだが、それを説明することは、勇太の語彙では難しい。
通っている大学に女友達(と言って良いかどうかは正直微妙だが)が居るといえば居る。気になる少女も一人。だか、彼女に自分の気持ちを打ち明けることを、勇太は躊躇っていた。
勇太自身の気持ちを押し付けて、あの優しげな顔が申し訳無さに歪むのは、見たくない。彼女を悲しませてしまうのならば、友達のままで良いではないか。それが、勇太の現在の結論。
だが。



カノジョ、ねぇ……


あいつらは多分、ドラマやコマーシャルや漫画の中の人々のように、クリスマスは自分のカノジョと一緒に過ごすのだろう。そう思うと何だか妙に落ち着かない気分になってくる。



悔しい、のか?


いや、違う。勇太は思わず首を振った。
自分の気持ちを上手く言葉にすることは、今はできない。いや、言葉にしたところで『カノジョが居ない奴の僻み』だと言われるのがオチだろう。だが、今勇太が持っている感情は、確かに、『悔しい』という言葉とはベクトルが違っていた。
暢気で溌剌とした声に、はっとして目を上げる。
昨日のことを思い出しながらぼうっと歩いていた所為か、目的の建物は勇太の背後になっていた。



危ない危ない


危うく通り過ぎてしまうところだった。
勇太は息を吐いて気持ちを切り替えると、見た目は周りにある他のビルとあまり変わらない十四階建てのビルの入り口まで足を戻した。
勇太が通う帝華大学理工科学部の校舎は、都会の街中に静かに、しかし威厳を保って建っていた。
地上十四階、地下二階建ての建物の中には、理工科学部の全ての学科で使われる全ての設備が入っている。講義室や実験室、教員や院生の研究室はもちろん、図書室や情報端末室、大学外の人も使うことができるカフェテリアやコンビニもある。
直方体で何の変哲もない外観に比べ内部が広く見え、更にあまりにも設備が整い過ぎている為、『内と外で大きさが違うのではないか?』という噂が絶えないという、少しの曰くが付いた建築物。それが、帝華大学理工科学部の校舎。
帝華大学理工科学部の建物は、普通の人には関知できない『歪み』を用いて内部空間を広げている。
帝華大学で研究を行っていた橘教授が、幾何学を応用し、三次元空間に連続してn次元空間が存在するような空間を作り上げた。その理論を建築に応用することで、建物の内部空間を広げ、講義室も実験室も研究室も、学生に必要な空間すらも、建物内に余裕を持って詰め込まれている。
橘教授の理論は完璧だったと、勇太の兄であり、橘教授の教え子でもあった雨宮准教授はいつも言っている。
だが、理論通りに、そして注意深く作られた建物ではあるが、それでも時折、『歪み』に囚われてしまう人が現れることは、事実。
その『歪み』を探し出し、『歪み』に囚われてしまった人や物を救出し、『歪み』を修正するのが、雨宮准教授と、『歪み』に関わる力を持ち、彼に協力する、勇太を始めとする学生達、通称『歪みを識る者達』。
