彼女が走るそのスピードを、猛スピードという言葉以外で僕は表現することができない。
彼女が走るそのスピードを、猛スピードという言葉以外で僕は表現することができない。



タイムのびないー!


叫ぶ彼女の声がする。彼女はあんなに速く走るのに、さらなる速さを求めて、毎日毎日走っている。
それを、僕は涼しい教室から眺めている。
放課後に図書委員の仕事がある日以外は、グラウンドで走る彼女を教室から眺めることが僕の日課だった。
ひたむきに走る彼女は、僕の憧れだ。
陸上部の中から、彼女を探しだすことは簡単だった。一人だけふわりと浮いて見えるのだ。
それは多分、彼女の走り方が特別綺麗だからだろう。ひとりだけ、重力を操れるみたいに軽やかに走っている。
才能の塊なのか、それとも努力の天才なのか、はたまたその両方なのか。
……なんだっていい。僕の憧れは、カモシカのように地面を蹴る。浮かぶ。前に進む。
ゴールして、ゆっくりとスピードをゆるめながら、タイムを図っていた人に声をかける。その後、ああ、と空をあおぐ。タイムはのびなかったようだ。



もう少しなのにー!


非凡な彼女は、手を広げてぐるぐると回っている。
僕は、彼女に比べたら平凡な人間だ。
高校生活で自慢できることといえば、おすすめの図書という学校の図書室主催のコンテストで、僕の推薦文が佳作をとったぐらい。
彼女は僕を知らない。当たり前だ。部活も委員会もクラスも学年も、何もかもが違うのだから。
僕だけが知っている。一方的。



ストーカーではないよな……


少し心配になるけれど、多分大丈夫。
彼女をぼんやりと眺めているだけ。彼女に迷惑はかけていない、はず。
爽やかな風が吹く、雲が少ない日だった。
その日の彼女は、皆が帰った後も、残って練習を続けていた。熱心だなあ、と思っていると、突然教室のドアの開く音がした。

慌てて手にしていた本に目を落とす。部活終わりのクラスメイトが、疲れたと口にしながら、荷物を取るとすぐ、教室を後にした。
足音が十分に遠ざかったあと、僕はゆっくりと顔をあげる。



あぶなかった


ここで彼女を眺めているという日課は、僕だけの秘密だ。
クラスメイトにとって、僕は読書好きで毎日教室に残って本を読んでいる人であってほしい。
さてと、とグラウンドに目をやると、走っている彼女はいなくなっていた。
もう練習を終えたのかな、と思ったが、違うことにすぐ気がつく。
グラウンドの隅に影が見えた。彼女が片膝を抱えるようにしてうずくまっている。
何があったのだろう。文字通り右往左往する。
つったのか、肉離れか……怪我? 血の気が引いた。グラウンドにはだれもいない。



怪我だったら


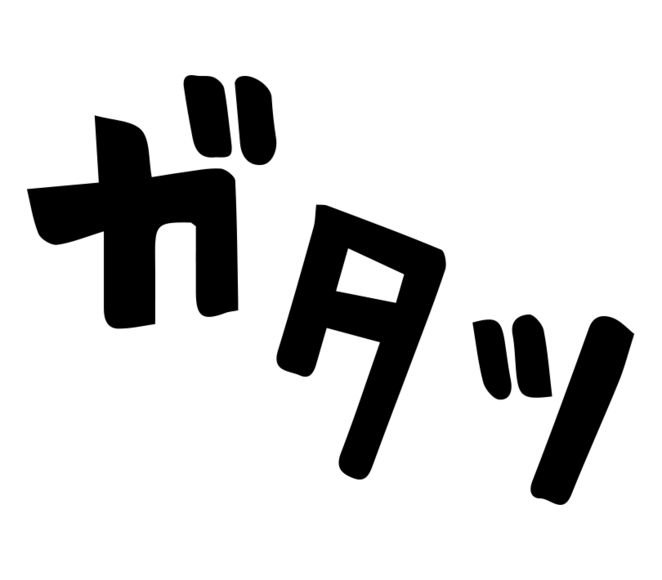
僕は机にぶつかりながら、教室を飛び出した。
階段を何段飛ばして駆けおりたか分からない。
体を思い切り斜めにしながら角を曲がり、先生の怒鳴る声を遥か後方に置き去りにする。
上履きに変えもせず外に飛び出すと、夕闇の中、グラウンドに目がけて一直線に走っていった。



大丈夫ですように、大丈夫ですように


何度も唱えながら、地面を蹴る。彼女みたいに軽やかにいかないのがもどかしい。
どたどたと、情けないスピードで、それでも僕のできる限りの力を振り絞って、前に進む。
足がもつれそうだ。彼女もこんな気持ちになる日があるのだろうかと考えて、泣きそうになる。



走れなくなったらどうしよう


勘弁してくれ。神様か誰かに祈る気持ちだ。



そんなの、やめてくれ


グラウンドは広かった。体育で何度も使用しているはずなのに、そこは果てがないような気さえした。
僕はそれでも、グラウンドの端にいる彼女めがけて走っていく。ぐったりと力尽きているように見え、思わず



おい!


と叫んでいた。



はい!


と彼女が勢いよく飛び起き、僕は驚いた。その途端、足が絡まり、前につんのめって派手に転ぶ。



あだっ!


情けない声が出る。恥ずかしさで耳まで赤くなる。



大丈夫ですか!


彼女が叫ぶ。



君こそ!


僕が起き上がると、目の前に彼女の顔があった。心臓が飛び跳ねる。彼女は



あ


と白い歯を見せて笑った。なぜだか、ますます頬が赤くなる。



もしかして、私が倒れていると思ってすっ飛んできてくれたんですか?


彼女の声をこんなにしっかりと聞いたのは初めてのことだった。
思ったよりも高い声が、だれもいないグラウンドにひびくようだ。



田辺先輩?


返事をせずにぽかんとしている僕をのぞきこんで、彼女はいった。
いった、えっと、なんて?



え?


耳を疑う。彼女は僕の名前を知っていた。



なんで……


