――シーエッグ 瑞留の部屋――
――シーエッグ 瑞留の部屋――



……何やってんだ、お前


感情のこもっていない声に、わたしは絶望した。
もう、終わりだ。
テトともお別れだ。
わたしが硬直して一言も答えられずにいると、瑞留は部屋の電気をつけてわたしの横を通り過ぎる。
そして床に落ちた人形を確かめたと思えば、そっと拾い上げた。



…………


何も言わないのが、怖い。
そして彼が拾い上げたことでようやく気付いたが、落ちた人形は足の関節が外れていた。髪の毛は絡まり、引っ掻いたような痕がある。



(テトだ)


絶望感が身体の隅々まで満ちる。
唇は震えて上手く動かない。
せめて何か言い訳をして、謝ったほうがいいと思うのに。
わたしはもう、何もかもが恐ろしくなった。
瑞留が。人形が。この状況が。
すべてが。



――ごめんっ!!


悲鳴のようにかすれた声で叫んで、わたしは瑞留の部屋を飛び出した。
そしてそのまま部屋には戻らず、商業施設のほうへただ走った。
――シーエッグ ショッピングモール――
なるべく人気のない通りを選んで歩いた。テトは服の中に隠し、顔だけは襟元の隙間から覗かせていた。
シャツはモコモコと妙に盛り上がり、慌てて靴を履かずに部屋を出てきてしまったので靴下で歩いている。人に見られればおかしく思われることは分かっていた。
だから無人の場所を探したけれど、この狭い施設の中では無理な話だった。



ねえあなた、服の中に一体何を入れてるの? まさか動物……?


声をかけられそうになれば、とにかく逃げた。
強く抱きかかえればそのたびに、服の中でテトがにゃあと泣いた。
――シーエッグ 公園――



ごめんね、テト


周りに誰もいないことを確認して、わたしはテトを服の中から出す。
ようやく解放されたとテトは逃げようとしたが、わたしは無理矢理それを捕まえた。



ダメだよ。誰かに見つかったら、ここから追い出される


腕の中に収まることに嫌気がさしたのか、テトはわたしの手を軽く引っ掻いた。
さほど痛くはなかったけれど、涙が出そうだった。



テト……なんで部屋から出ちゃうのさ。なんで瑞留の部屋に入ったりしちゃうの……


そんなことを言っても仕方がないのは分かっている。動物は自由に動き回るものなのだから、わたしが注意しなければいけなかった。
分かっていたのに、出来なかったのはわたしだ。



バカなんだから……


声を震わせて手の力を抜いた瞬間、するりとテトは地面に降り立ってしまう。



テト


わたしは遠くを見たテトの背中に、声をかける。
けれどいつものように、にゃあと返してくれることはない。
テトはとたとた、と駆け出してそのままどこかへ行ってしまった。一度も振り向かずに。



…………


気がつくと口の中はパサパサに乾いていた。目の周りが熱く、足の裏が痛む。



なんで……


理由なんか分からないし、知りたくもなかった。
けれどこのままいけば、どのみちテトはわたしの腕の中から取り上げられてしまうだろう。
そう思えば、追いかける必要もないような気がした。



テトぉ……


それでもわたしはあの白い猫が、彼女がいないと生きていける気がしなかったのだった。
――シーエッグ 教室――
翌朝。
わたしは誰よりも早く教室に来た。夜遅くに部屋に戻ったのであまり寝ていなかったが、眠気どころの話ではなく、ガチガチに身体を固めて椅子に座っていた。



(なんて言われるだろう)


わたしは昨日から、あらゆるパターンを想像しては奥歯を噛み締めていた。
先生に報告しておいた。
まずは弁償しろ。
なぜ禁止されているペットを飼っている。
あの猫はどこだ。
あらゆる罵倒の言葉も想像して、その時に備えた。どちらにしても、もうテトはいないけれど。
何度も何度も想像の世界と現実を行き来したところで、教室のドアが開いた。
入ってきたのは想像通り、冷たい目をした瑞留だった。



…………


しかし瑞留は無言のままに自分の席へ向かい、着席する。
わたしの掌は汗でぐっしょりと濡れていたが、結局瑞留は幸也が来るまで一言も発さなかった。



おはよう。今日は二人とも早いね


幸也がやってきてもそれは同じで、ただただ瑞留は押し黙ったまま机に座っていたのだった。



(一体、何なんだろう……)


教室で話すことでもないと思っているのだろうか。それともわたしとは口もききたくないということだろうか。
しかし部屋に勝手に入られて、大切にしているであろう人形を壊されて、黙っていられるものだろうか。
あれほど毎日わたしの言葉に突っかかり、文句ばかり言っている瑞留が。



(一発殴られるかなくらいに思っていたのに)


瑞留とは特殊学校の入学時に知り合った。今から二年前のことだ。
パートナー候補と学校から告げられて、わたしは当初瑞留に対して特段変わった感情は持ち合わせていなかった。



(どうせパートナー候補は変えられないんだから、仲良くしようと思っていた――最初は)





(ただ、瑞留がわたしを毛嫌いしていたから)


挨拶をしても返さない。会話をしようとしても嫌がられる。ペアで授業の作業に取り組めば文句ばかり言われる。
徹底した嫌われように、こちらもイヤになっただけの話だった。



(でも……それだけと言えば、それだけだった)


例えば暴力を振るわれるようなことはなかったし。口論もするものの、無視して返事を返さないようなことはなかった。
口も態度も悪いが、言うなればそれだけの人間で、根っから冷たい人間というわけではない。
それは、わたしが一番知っていた。
知っていたが。



(それでも今は……瑞留が、怖い)





それじゃ今日の授業は終わりだ。お疲れさん、私





僕らにじゃないんですね





君らはただ私の話を聞いてるだけなんだから適当に力を抜いてるだろう。それより、結局椿は来なかったな


そう先生が言った瞬間、勢いよくドアが開く。



寝坊しちゃいました、すみません


噂の主はいつもの可愛らしい笑顔で頭を下げる。



寝坊っていうかな……まあいいや、あと十秒で終わるが十秒だけでも座ってろ





はーい


十秒と言われた話は五秒で終わり、その場で解散となる。
しかし先生は去って行く前に一言だけわたしに告げた。
わたしと、瑞留に。



あ、そう言えば今日は大水槽の餌やりだからな。忘れるなよ、玉慧と瑞留





……え





…………


このまま一日が過ぎ去るかと思っていたわたしを、どん底に突き落とす言葉だった。



(大水槽の、餌やり……)


学生の間で定期的に回ってくる作業だ。この特殊学校は海の中にありながら、施設内にもたくさんの水槽がある。
なんとかセラピーというのだそうだがまったく覚えていない。とにかく、その水槽の餌やりや掃除を日常的にやっているのは学生達だった。



(何もこんなタイミングで)


パートナー候補であるペアがその作業を担当するのは何もおかしいことじゃないし、いつものことだ。
けれど今日のわたしは、絶望的な気持ちで席から立ち、恐る恐る瑞留のほうへ視線を向ける。



…………


すると瑞留は無言のまま教室を出て行った。



(……わたしも、行かなきゃ)


陰鬱とした気分のままとにかく足を動かす。
するとそのわたしの背中に、やけに明るい椿の声が届いた。



玉慧、餌やり頑張ってね





う、うん


それだけ答えるのが精一杯だった。
――シーエッグ 大水槽上部――



…………





…………


無言。
ただただ無言。
二人で作業といっても何を協力するでもなく、いつもの作業を進めていく。
バケツ一杯の餌を、二十メーター四方はある大水槽の上部にばらまく。
すると魚達が寄ってきてそれをパクパク食べていく。
少し場所を移動してもう一つのバケツを開ける。
魚達が寄ってきて餌がなくなっていく。
その繰り返し。
大量の魚の餌は言葉にしがたい匂いがし、重い。汚れものを好むわたしは特別何も感じないが、綺麗好きな瑞留はこの作業を毎回嫌がっていた。
そして結局わたしが作業のほとんどをすることになり喧嘩になる、というのが毎度のことだった。
しかし今日の瑞留はわたしに声をかけたくないせいか、文句も言わずに作業をこなす。
わたしのほうを一瞬でも見ることはない。



(もしかして、あれなのかな)





(これが瑞留の怒りの表現の仕方なのかな。一切喋るつもりはないし、目を合わせるつもりもない。これから、ずっと――)


わたしが想像したいくつものパターンよりかは、ずっと穏便なやり方だった。
けれどこれはこれで胸が痛み、今後を考えると目がくらみそうだ。



(怖い……)


そしてわたしのすべての思考回路はそこに収束した。
怖い。
わたしは本当に、瑞留が怖かった。



(どうしたら、いいんだろう)


重い気持ちでバケツを持ち、水面に餌をぶちまけた。その時ふいに、背後に気配を感じる。



おい……


ぞくりとした。すぐ背後で低い声を感じる。
その声は紛れもなくわたしが怖れていたその人の声で、身体が弾かれるように動く。
しかし、動いた場所が悪かった。



あ


バケツを持ったわたしはバランスを崩し、一番まずい方向へ倒れ込んでいく。
水面がのぞく、大水槽のほうへ。



(落ちる)


ゆっくりと世界が回転し、わたしの視界はいつのまにか泡で埋もれた。
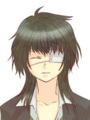


(ああ……)


妙に冷静な気持ちで、ひとたび目を閉じた。
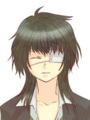


(わたしは本当に、ばかだ)


泡に包まれながら沈んでいく身体を感じながら、そう思う。
つまらないミスで水槽に落ちてしまうことも。
びくびくと謝ることもせずに瑞留を怖がっていたことも。
一人で隠しきれると高をくくってテトを飼っていたことも。
……汚れが落ちてしまうことを嫌って、泳ぎを習ったことがないことも。
すべて、今さら後悔しても仕方のないことだった。



(ばかだなぁ)


そう思いながら目を開くとそこはやはり水の中で、わたしは服の重みもあってずんずんと底へ沈んでいく。
水面を見上げるが泡だった光が明滅するばかりで、そこに人影は見られない。



(瑞留が……助けてくれるはずもないか……)


分かってはいたが、そう思った瞬間身体はさらに冷たく重くなる。
そしてそのまま果てしなく、水の底へ落ちていくのだった。
