発信。コール音。留守番電話応答。
発信。機械応答。着信拒否。

発信。コール音。留守番電話応答。
発信。機械応答。着信拒否。



参ったな……


どうやら話しあうつもりはないみたいだ。
家に押しかけても居留守を使われてしまうし、電話にも出ようとしない。メールアドレスも変えたみたいだ。返ってくる。
木が移植され開放された屋上で、僕はフユコにしつこく電話をかけていた。



まるで別れた女をストーカーしているみたいだな、コレ……


あれから三日、フユコは学校に来ない。担任には本人から風邪だと連絡がいっているらしい。



つまり、フユコはまだ『人間』だ


僕は制服の内ポケットに財布が入っているのを確認する。携帯電話は今持っているし。教科書とかは、まあいいか。今日はこのままサボり決定。
教室には戻らずに、僕は昼休み終了の予鈴にざわめく校内を抜け出した。
高校から家までは徒歩十五分。フユコの家までは更に五分追加。徒歩二十分の道程を僕は小走りにかけていく。



荷物を置いてきたのは正解だったなぁ。教科書を持って走るのはちょっときつい


フユコの家は古びたマンションの一階だ。少しだけためらったけれど、インターホンを押した。また居留守を使われたら、その時はその時だ。
扉の向こう側で、何かが動くような音がした。だけど、扉は開かない。インターホンで答える様子もない。



……フユコ


呼びかけてみても、答えない。
でも、多分扉の向こうがわに彼女がいる。
エデンの林檎症候群の発症から、木への変革が始まるまでどれくらいかかるんだろう。



マユリの時は小さかったからなのか、それともリンゴを食べたせいなのか、丸一日で木になってしまったけれど……


あれから三日だ。フユコがエデンの林檎症候群にかかっているとしたら、もうそろそろ危ないかもしれない。



フユコ、開けてくれ。会いたい


まだ、無言。
でも、扉の向こう側にはまだいる気がする。



ああ、本当に僕はどうかしてるよ。
何で今更こんなに焦っているんだ


誰が木になっても、僕は寂しくて虚しくなっても、涙ひとつ流さずにぼんやりと生きていくんだろうと思っていた。自分が木になるってわかったとしても、特に変わりなく日常を過ごしていくんだろうって。
みんなが木に変わっていくその度に、僕の中で何かが枯れて、腐って、崩れ落ちてしまったって、それで僕が痛みを感じるわけじゃないから平気だって思っていたんだ。
ついこの間まで、本当にそれでも良かったんだ。壊れっぱなしでも、生きているならいいかって、思えていたんだ。



――でも、もう無理だ





聞こえている?


扉に額をくっつけてみる。かすかに、何かが動く音。すぐそこにいるんだ。



学校に行って隣の席にフユコがいないのは嫌だ。キッチンに入ったら役立たずっていって追い出してくれないと嫌だ。僕がぼんやりとおかしなことを言ったら、自分のことみたいに心配したり泣いたりしてくれるフユコともう会えなくなるのは……嫌だ


ああ、だめだな。言いたいことの半分も言えていないのに、声が震えてきてしまった。
涙で顔がぐちゃぐちゃだ。かっこう悪い。
涙腺が壊れたんだろうか。今までちっとも出てこなかったくせに、一度出てきたら詰まり物が取れたみたいにどばどばと出てくる。



……僕には、フユコが、必要なんだ


ああ、なんでもっと気のきいた言葉を思いつかないんだろう。ラブロマンス映画をもっと観ておくべきだったのかな。
そういえば、フユコと観たあの映画、最後は死に際のヒロインのところにヒーローが駆けつけて愛の告白だっけ。



フユコ、もしかして狙ってあのDVD見せたんじゃないだろうな。だとしたら計画的犯行だぞ





だって、今の僕がやっていることってつまり、あの映画の主人公と同じことだろ?





……開ける


小さな、声が聞こえた。
僕が慌てて飛びのくと、青白い顔をしたフユコが顔を出した。



……メグル、学校は?





サボった





……かばんは





置いてきた





……バカ?





うん、バカだ


今くらいはバカだっていいじゃないか。
フユコの身体を抱きしめる。彼女は抵抗しなかった。そうやって玄関先でどれくらいの間いただろうか。



あのさ、メグル。学校、戻りなよ。
そして、ちゃんと授業うけなよ





嫌だ





だって、私、多分そろそろダメだよ? 背中すっごい痛いもん。私、そんなところ見せたくないもん





嫌だ


腕の中で、フユコが泣いている。僕はまだ彼女を離そうとしない。
離したら、もう本当に会えなくなるような気がして。



じゃあ、私をメグルの家に連れて行って





……いいよ


彼女の身体を解放するかわりに固く手を握り締めて、僕らはたどたどしく歩き出す。
僕の家まで本当だったら徒歩五分の距離を、惜しむようにゆっくり時間をかけて。



いつくらいから気づいてた?





マユリちゃんが木になった、二日後くらいから。最初は気のせいだって思っていたけどね





何で言わなかった?





メグルが、これ以上壊れたらどうしようかと思って





……むしろ修理されていた気がするんだけど


フユコのおかげで、僕は色んなことに気がつけた。どれだけ助けてもらっただろう。
彼女は悲しそうに笑っていた。



メグルのことを考えたら、疎遠になっておいた方がいいのかな、とも考えたんだよ。私が木になったって知ったら、メグルは表には出さなくても、やっぱり相当ショック受けるだろうし


握り合った手に微かな力を込めて、今度はなぜか少し穏やかな笑顔を浮かべ、上目遣いに見上げてくる。



この笑顔がもう少しで永遠に見られなくなるなんて、悪い冗談じゃないのか?





最後まで迷ったの。メグルは家事がちっともできないし、オマケに何もかもどーでもいいって顔してて、放っておいたら私なんかよりも先に木になっちゃいそうで、怖かったんだ





僕は……まだ大丈夫だよ





うーんとね、その、エデンのリンゴにならなくってもね。メグルならそのまんまでも木みたいになっちゃいそうで





うーん?





何も見ない、何も聞かない、何も言わない。そういう存在になっちゃいそうで……


フユコの目に、最近の僕はそういう風に映っていたのか。
そして、フユコはこれからそういう存在になるってことなのか。
何も見えない、聞こえない、言えない。そんな存在に。
僕は不意に思い出す。あのリンゴの実のことだ。食べたら、意思の疎通ができるようになるんだって。マユリが言っていた。僕がぐちゃぐちゃに踏み潰したあの実。



だけど、いざ自分が木になる時が近づいてくるって思ったら、やっぱりメグルには見られたくないな、とも思って





会いにきてほしくなかった?





ううん、会いたかった。ありがとう


僕の家についた。思いっきりゆっくり歩いても、僕とフユコの家はちょっと近すぎる。
僕らは玄関から中には入らずに、庭に回りこんで縁側に腰掛けた。
二人で並んで座って、手はつないだままで、ぼんやりとスズメの動きを目で追って。



ねぇ、メグル


ぽつりと、フユコが呟いて。



死にたくないよ





フユコは死なないよ





木になりたくないよ。
メグルと離れたくないよ





僕は、ここにいるよ





怖いよ





ずっと、ここにいてあげるよ


パキ、といつか聞いたあの音が隣で聞こえた。
彼女のすすり泣く声も、一緒に聞こえた。
僕はできるだけ彼女の方を見ないで済むように、じっと風に揺れているキンモクセイの花を見ていた。
パキパキという音が段々大きくなっていっても、見なかった。
すすりなく声はいつの間にか聞こえなくなっていた。
握り合っていた指先の感触はいつしか離れ、余韻も残さずに消えた。
言葉もなくただ、日が暮れるまでずっと座っていた。
縁側には、エデンのリンゴが風に葉を揺らしている。
僕はその実を一つ取って、握り締めて、立ち上がる。
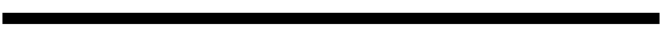
ヒロアキの木は学校の裏庭の奥、目立たない場所にひっそりと植えられていた。
僕は『彼』に軽く手を上げて、挨拶をする。



久しぶり。元気そうだな、ヒロアキ


返事はない。だけど風にざわめく木の葉の音が、何となく人間だった頃のヒロアキの明るい笑い声に似ていた気がした。
オオツカの木は彼の部屋の中。オオツカの母さんに案内されたら、そこに木はなくなっていた。かわりに燃やした灰を詰めたんだっていう、骨箱が置いてあった。



挨拶したかったんだけどな……


こればかりは、家族の感情もあるから仕方がない。あの実を食べた後のことなんて知るわけもないだろうし、言っても信じてもらえないだろう。知らない方が幸せなことも、世の中にはたくさんある。



ゲームの攻略は自分で解決したから
気にするなよ


そう、箱に話しかけて、僕はオオツカの家を後にした。
ついでに通り道だったから、D組のワタセさんがいる公園にも寄ってみた。花壇の花を眺めている最中に木になったと聞いた。柵で囲まれている。
話したことなかったけど、騒がれるだけあって美少女だったと思う。



……ああ、でもその、フユコに怒られそうだからやっぱ行こう……ごめんワタセさん


ワタセさんの木には話しかけず、僕は公園を出た。
公園の裏手から少し回ったところにあるアパート。一階の右端の部屋だったはずだ。



あ、これだ


元担任の木。アパートの玄関前に不自然に生えている。これで間違いないだろう。



すみません、学校サボって来ました。
許してください。


葉がざわめいた気がするけれど、気にしないことにして、僕は次の場所に向かう。
この辺りから、次第に住宅街に入っていく。タケシの家は、犬がいなくなった以外はそのまんまだ。玄関は施錠されていなくって、勝手に入ったら家族並んで生えている木のたもとに、菊の花束がたくさんあった。
新しいのもあれば、すでに枯れて茶色く変色したのまで。



ああ、もう結構経っているんだもんなぁ





でも、家族一緒でちょっと楽しそうだよな。安心したよ


僕の家の三軒となり、おばあちゃんが住んでいた家。。



子供の頃は、ここのおばあちゃんによく飴玉とかまんじゅうを貰ったなぁ。大好きだった


縁側の木の下で、今日も幸せそうな顔でネコが丸まっている。平和っていいことだ。
そして、僕の家。両親の寝室には木が三本。僕の家族だ。
僕はまず、手前に転がっていたリンゴを手にとって、一口かじってみる。
案外酸っぱかった。だけど、味はほとんど普通のリンゴとかわらない。



まぁ、エデンのリンゴが蔓延して以来、どこのスーパーもリンゴなんて売らなくなっちゃったから、しばらく本物のリンゴなんて食べていないんだけどさ


『お兄ちゃん?』
マユリの声がする。ああ、これ、マユリの木から落ちた実だったらしい。



本当に、聞こえた。
マユリ、父さんのと母さんのは?


『うんとね、あそこの根っこに挟まっているのと、
ベッドの下に転がっているの』



ありがとう。
木になってもいいこだね、マユリ


僕はマユリに言われたとおりに実を拾って、それぞれ一口ずつ食べて、酸っぱい果肉を飲み込んだ。
『メグル……どうして』
これは母さんの声。
『この実を食べたらどうなるか、
わかっていたんだろう?』
これは、父さん。
ああ、まだそんなに経っていないはずなのにな。どうしてこんなに懐かしく感じるんだろう。不思議だ。



ずっと一緒にいるって、約束しちゃったから。だから、最後に父さんと母さんと、マユリにだけはきちんと話したかったんだ


『もう、行くのか?』



うん、好きな子のところに行かなくっちゃ


『どこに行くの?』



すぐそこだけど


『お兄ちゃんは一緒にいてくれないの?』



うん、ごめんな


僕は家族に別れを告げて、リビングに荷物を放り投げ、そして縁側に続くガラス戸を開ける。
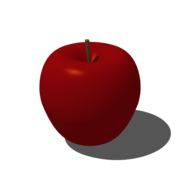
転がっていたリンゴを拾い上げて、かじった。
何だかこれは少し甘い気がするのは、気分の問題だろうか。
芯だけになったそれを庭に放り捨て、僕は縁側を占拠するその木にもたれかかる。



何か話さないか?


『どうして食べたの?』



みんなそればっかだ


『だって、これを食べたら……
メグル、知っていたんじゃないの?』



知っていたよ


マユリで丸一日かからないくらいだったから、明日の昼か夕方くらいには、僕も真っ赤な知恵の実をつけたエデンのリンゴになるだろうか。
この病気にあの名前をつけた人が、この秘密に気づいていたかはわからない。僕は専門家でも何でもないからな。でも、食べたことで全てを知るってことだったら、確かにぴったりな名前かもしれない。
知恵の実を食べて僕は、人間には聞くことができないはずの木の声を聞く。
人間の世界にいられなくなる僕は、木にならなくてはいけない。



まあ、僕がもう完全に心が壊れちゃって、勝手に自分に都合が良い声が聞こえると思い込んでいるっていう可能性もゼロじゃないんだけどさ。ここで言うのは野暮だよな


だけど僕は、何一つ後悔なんてしていない。



一緒にいるって約束したじゃないか。
側にいるよって


『でも……』



だって、もう僕が壊れてしまっても、フユコは修理できないじゃないか。
だから、僕もフユコと同じになるよ。
それならもう、大丈夫だろう?


『……メグルのバカ』



うん。バカでもいいや


僕がやっていることは、数ある選択肢の中でももっとも愚かなものなんだろうなって自覚はある。
見ようによっては緩慢な自殺だ。いや、心中っていうべきなのか。



リンゴ心中……。締まんないな


どうしようもないバカだってわかってはいるけど、それでもこれ以外の選択肢を選びたくなかったんだ。



エデンのリンゴって何十年くらい生きられるのかな? 縄文杉みたいに何千年も生きられたりするかな?


『私にわかるわけないでしょう?』



寿命が長ければ、その分一緒にいられる時間が増えるよ?


『すぐに飽きたりして』



その時はケンカしよう


『どうやって?』



うーん……口げんか?


あはは、と僕は笑う。枝のざわめきはフユコが笑っているからだろうか。
取り留めのない話ばかりをした。夜になって、毛布を縁側に持ち込んで少しうとうとしたけれど、意外と寒くってあんまり寝られなかったな。結局、夜通し起きて話をしていた。
話しながら、僕は手元にライトを置いて手紙を書く。
遺書、というのが適切なのかどうかはわからないけど、僕が人間としておしまいを迎える理由を、ちゃんと残しておかないとと思ったからだ。



木になって即伐採されるなんてごめんだし


エデンの林檎の実を食べた後のことも、一応書き記した。この情報をどう受け止めるかは、手紙を読んだ人に任せよう。
朝日が昇りきった頃には少し背中が痛くなってきて、動くと皮膚がつっぱるようになってきた。



もう少しかな。まだかかりそうかな


『ねぇ、本当に良かったの?』
フユコが今更のようにそんなことを言う。
きっと、良くはないんだろう、普通に考えると。だけどこの浅はかな選択肢は、もう後戻りなんてできない。そして僕はこの結末を自分の意志で選んだ。



あのさ、フユコ


『……何?』



僕のお嫁さんになってくれる?


『バカ』
僕、この一日で何度馬鹿って言われたっけ。まあいいや。
フユコが『バカ』って言うのは、心配してくれている時と照れている時なんだということを、僕はちゃんと分かっている。



一緒にいよう


ずっと隣で。
同じ空の下で同じ風に吹かれて。
枝葉に満ちる葉が幾度となく色を変えても。赤い実が幾度となく落ちて生まれ変わっても。
『本当に、バカなんだから』
彼女の声に僕は微笑む。
背中に軋んだ音を聞きながら。



ずっと、一緒にいよう。


もう一度、心の中で繰り返す。
動かなくなった身体をフユコの幹に預けたまま、光を映さなくなった視界が闇に沈んだ後も。
一緒にいよう。
世界中の人間がリンゴに変わってしまっても。
幹が朽ち、葉が落ち、土に還るまで。
パキン、と背中を何かが突き破った感触を最後に、全ての感覚が閉ざされる。
―― いっしょにいよう
この世界を満たした楽園の実が、全て腐り落ちて消えてしまうまで。
――僕らのこの木が枯れるまで
