広間のテーブルに頬杖をつきながら、僕はけわしい視線を向ける。



……で?
何故こいつが夕飯の席に居るんだ?


広間のテーブルに頬杖をつきながら、僕はけわしい視線を向ける。



だって……この寒いのにずっと地べたで座ってるから、可哀想で





はっはっは!根性の勝利だな!


僕たちの向かい側に座っている男は、憐みの視線を向けられているというのにまるで気にしていない。
ふんぞりかえって笑いながら、ナイフとフォークを両手にアーニャの給仕待っている。



アーニャちゃん、今日の飯は何だい?





チキンのソテーですよ、シドさん


一体どうして何年も前からこの場に居たような顔をして座っているのか、僕には全く理解できない。
眉間に皺を寄せながら、僕は行儀の悪い鎧男に苦言を呈する。



僕は帰れと言った筈だが





そして俺は帰らんと言った。
あんたに話を聞いてもらうまではな


シドはそう言って笑いながらウインクしてみせた。
テーブルの上にはトマトソースのかかったチキンが二枚、皿に乗って並んでいる。



何だ、アーニャちゃんは一緒に食べないのかい?





私はメイドですから





何だい何だい!
君の主人はケチくさいなぁ


……うるさいのが二人いつの間にかすっかり仲良くなってしまったようで、面倒臭いことこの上ない。
僕はひとつ大きな溜息をつくと、渋い顔をしながらアーニャに告げる。



――お前も食事をもって卓につけ





……!!


長い睫毛に縁どられた瞳が大きく見開かれた。
今まで僕たちは生まれてこの方食事を共にしたことが無い。
それは、僕たちが主従の関係であることを当たり前に思う人間しか、今まで周りに存在しなかったからだ。
しかし、僕のような気高く賢い人間がそんなみみっちいことをいちいち気にするはずもない。
従者である彼女が一緒に卓を囲んでいようが何の問題も無かった。
それより、この鎧男にケチだのなんだの言われ続ける方が、よほど不名誉である。



幸い僕が心が広いからな。
だが男、お前は決して二度と僕に『ケチ』などという単語を口にするな





……本当に心が広い人間は、自分のことをそういう風に言わないもんだがな





それ以上何かほざくとそのチキンは没収する





うへー! それだけはご勘弁を!


キッチンから自分の分の夕食を運んできたアーニャが、ぷっと噴き出して笑いながら言った。



二人ともすっかり仲良くなったのね


思ってもいなかった言われように、僕は盛大に顔を顰める。



誰がこんな奴と





それはこっちの台詞ってもんだ


――大きな口をへの字に曲げた鎧男の顔が何だか頭にきたので、僕はテーブルの下にある脛を盛大に蹴飛ばしてやった。
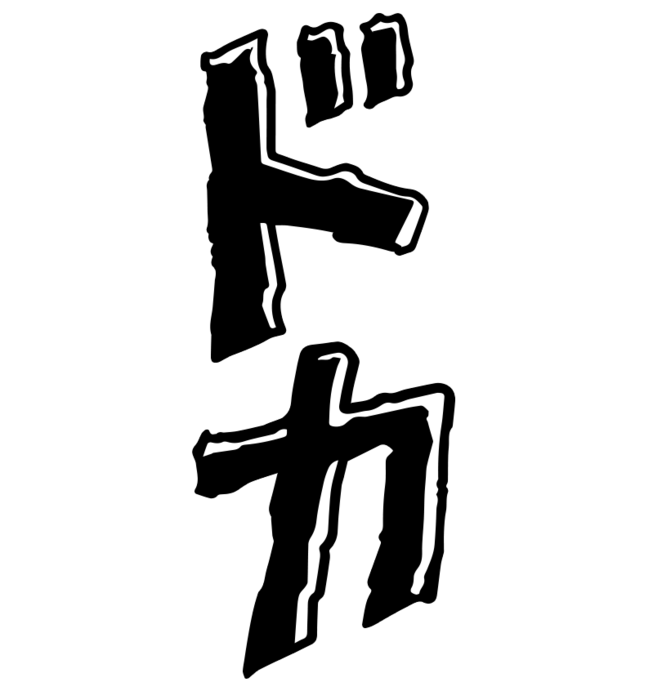



いてぇ!





フン


文句を言いたげな男を無視して、僕はナイフとフォークを手に取りチキンの胸肉を切り分け始める。
奴も空腹には負けるのか、続いてパンを貪りだした。
アーニャはスープをスプーンで掬いながら、穏やかな顔で笑っている。



……にぎやかね


僕とシドは、その声があんまりに優しいトーンだったので、何も言えずに彼女の顔を見つめた。



こんなの何年ぶりかしら


シドは少しだけ躊躇った素振りを見せてから、意を決したように口を開いた。



――あんたの他のコトラの民は?


アーニャが伺うように僕の瞳を見る。
僕は口の中のチキンを飲み込んでから、淡々と答えた。



皆死んだ。
生き残りは僕一人だ


シドがひゅっと息を呑む気配がしたが、僕は気に留めずにチキンの皮を綺麗に切り分けることに執着している。



……悪いことを聞いた





よく意味がわからないな。
僕はただ、事実を述べただけだ


シドがどうしてばつの悪い顔をしているのか、僕には全くもって理解できない。
向けられた質問に対してありのままの事実を答える。
僕がしたのは、そんな当たり前のことだ。



――あんたは……


シドは食事の手を止めて、僕の顔を静かに見つめた。



よくわからないな


僕はナプキンで口元を拭うと、淡々と答える。



そう簡単に、わかられたくはないな





……確かに、そりゃあそうかもしれない


ここで初めて、僕たちの意見は一致したようだった。



色々あるよな。みぃーんな


――広間はしんと静まり返って、時計の秒針がやけに遅い一秒を定期的にしらせてくる。
それは意味のある沈黙だった。
シドの言葉は僕にもアーニャにも届いていたし、だからこそ、僕達二人は何も言わなかった。
いや、言うことができなかったのだ。
シドの言葉は彼自身に言い聞かされたものであり、同時に僕達それぞれへのいたわりの言葉でもあった。
それにうすっぺらい相槌を返すことができるような人間は、一人としてこの場所に存在しなかった。
ただそれだけの話だ。
