嫌な夢を見た朝は決まって雨で、その日の朝もやっぱり雨だった。
嫌な夢を見た朝は決まって雨で、その日の朝もやっぱり雨だった。
ぼくはまだ夢の中にいるような妙な心持ちで目が覚めた。
遠くで耳鳴りのように響く雨音。
憂鬱な気分だった。
顔を洗い着替えると、トーストを1枚焼き、バターを塗って朝食とした。今日は別段やることもない。午後の授業は休講だったから、もう学校へ行く必要はない。誰かが訪ねてくることもないだろう。
部屋の小さな窓から見える切り取られた世界は、曇天をやっとの思いで支えている細いビルの群をかたどっている。冷たい霧雨が辛うじて確認できる。風はなさそうだ。
ぼんやりと景色を見つめていたぼくは、外に出てみようと思いついた。何も期待できそうにないが、同じ退屈なら家に籠もっているよりも少し身体を動かす方がよい。
そこに考えが辿り着いたときには、既に玄関に立っていた。
無彩色の街はただでさえ冷たく感じるというのに、灰色にくすんだ空や降り続ける雨でさらに体感温度は低下した。白のウィンドブレーカーが体温の逃げ場を奪い幾分かは暖かかった。
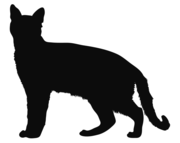
雨を好んで歩く人が少ないのか、知っている人間も見知らぬ他人もたいして見掛けない。商店街の入り口である十字路に到着するまでに出逢ったのはほっそりとした白猫一匹だけで、そいつもちらりと顔を覗かせただけで素早く走り去ってしまった。
真新しいものなど何もない。見慣れた風景が濡れているだけだ。
暇つぶしの散歩と割り切り歩くぶんにはなんてことはない。妙な期待を持って生活をするからがっかりするのだ。端からそんなことを考えなければ、歩きたいという欲を満足させるだけならばこれで充分だ。
ぼくはいつもどおりに信号待ちをした。
この通りは交通量が多い。四車線の広い通りを次から次へと右から左へ左から右へ車が流れていく。単調な一定のリズムを生み出すそれを眺めていると、まるではじめから動いていなかったような錯覚を覚える。同じ繰り返しは不必要なものとして処理され、上書きされてしまうからかもしれない。つまらない一日はやたら長く感じられるが、思い出せるのはごくわずかな情報。そんな感じ。
ノイズにまみれた喧しい街。ぼくはここに来て二年目だが、はっきり言って好きではなかった。数少ない友人たちは便利なこの街にすぐに溶け込んでいったが、ぼくは馴染む気など更々なかった。
この都市は中途半端な優しさで満ちている。
他人のことなんかどうだっていいくせに、話題のためにあれだこれだと引っかき回す。やっと見つけた話題でも、どこか冷めてしまっているのだ。ちょうど温かい料理が冷たくなって目の前に出されたのに似ている。そんな優しさはぼくにとって迷惑だし、誰かを傷つけることになると思う。親切とお節介は紙一重だなんて言葉があったけど、言い得て妙ではないか。
信号が赤から青に変わる。ぼくはワンテンポ遅れて踏み出した。
と、そのとき何かの気配を感じて振り返る。
急な風にあおられて傘は舞い上がり、視界から遠ざかってしまった。諦めて下ろした視線の先に、全身白い色に身を包んだ女性が立っていた。こちらをじっと見つめ、逸らす様子はない。
ぼくの瞳は彼女に奪われたまま自分の体が溶けて失われたように感じられた。輪郭が風に、地に、吸い込まれてしまう、そんな幻想が頭の中で生まれた。
にこりともしないが、日本人形のような整った美しい顔立ち。白い肌に濡れた長い黒髪が映えた。
ぼくが見ている人間は本当にそこにいるのだろうか。彼女も傘を持っていない。



あの……


先ほどから何か言おうとパクパクさせていた口から出てきたのは、弱々しい聞き取れるかどうかわからない声。言葉はこれで精一杯だった。
信号が青から赤に変わった。
車のクラクションに驚き、歩道に戻る。濡れたウィンドブレーカーが気持ち悪く腕にまとわりつく。



こんにちは


彼女はそう言うと微笑んだ。機械的でかたく、冷たいものだった。ふと何かを思いついたように空を仰ぐ。



あたたかいですね


彼女の言葉はそう聞こえた。
ぼくも束縛から放たれ、天を見上げた。



あたたかい?





はい


風が少し出てきた。湿った髪に風が絡まり、体温を下げていく。あたたかいなんて嘘だ。



この乾いた土地には雨は優しい。
温もりを感じません?





……そういう意味なら、ねぇ……


戻した視線の先に彼女の姿はなかった。
焦ったぼくは辺りを見回すが、影すら見当たらない。
信号が再び赤から青に変化した。
横断歩道を渡った先の商店街はアーケードになっているので傘はいらない。
ぼくは何を買うわけでもなく濡れた上着を乾かすために歩いた。新しい傘を買うつもりもなかったから、あまり意味がないということはわかっていたが。
ウィンドブレーカーの撥水加工のおかげで下に着ているシャツはほとんど濡れていなかったが、髪がしっとりとして肌にくっつくのはあまり心地の良いものではなかった。
都会とは世辞でも言えぬ土地から引っ越してきた。
あの町は雑木林や空き地が残る第一次産業を主な職業としている人間の多い町だった。家屋の他にあるのは畑ぐらいのもので、季節の移ろいは露地栽培の野菜の花でわかった。
ぼくはそうして生活をしていたから大概の野菜や果物の旬の時季を言えるが、年中問わずどの野菜も見かけるこの街の人々は正しく答えられないのではなかろうか。
この街は空気が汚い。
決してあの町の空気がきれいだったというわけではないが、人工物質の汚れと土埃の汚れではどっちがよいものだろう。
ぼくはまだ、この街で天の川を確認していない。
あの町は昼に雨が降って夜に晴れたような日は、空から落っこちてくるのではないかと言うくらい天球に張り付いた星を眺めることができたのに、この街はいつもと同じ天を支えるに留まっていた。
何故同じ星の上に立っているのにこうも違うのだろう。
友人たちにとっての理想郷はぼくにはいらない場所だった。
夢の中は雨であることが多かった。
場面が見知らぬ街であったり懐かしい故郷だったとしても、その全体は雨で霞んでいる。そしてそこの空気は嫌悪感を覚えるもので、そのときはっと目が覚めるのだ。
夢にストーリーなど存在しない。否、単に覚えていないだけかもしれない。
夢の中の感情を現実にそのまま引きずってしまうぼくの心と呼応するかのように、夢の中の雨は現実世界でも続いていた。
商店街を彷徨う自分の中にぼくは戻った。
どこをどう歩いたのか、もはや思い出せない。商店街の脇にそれて店の終わりのような場所に出ていた。
見たことのない場所だ。
中心部の現代的な建物が支配している空間とは違い、数十年前の木造建築の家屋が隙間を埋めて建っている。
振り向いて来た道を確かめるが、いまいちこの場所がどこなのかわからない。アーケードの屋根すら見えず、いつの間にか髪から滴が落ちていた。
弱った。
高いビルは遠くに幾つか群をなして立っているも、どれも無個性でランドマークには適さない。さらに遠いところにある建築物なら場所を少しは絞れたのだが、生憎この雨で視界は悪かった。
取り敢えず引き返そうと歩みを向けたとき、交差点で見かけた女性がぼくに対してちょうど横向きに立っていた。ひやっとするすました顔で家のなんの変哲もない壁を見つめている。さっき後ろを確認したときにはいなかったはずだ。
しかもこの道はずっと先まで枝分かれすることなく続いている一本道。向こうからやって来たとすれば気が付かないはずがない。
見覚えのある傘を差している彼女はゆっくりとこちらに躰を向けた。



傘、お忘れになっていましたから、
届けようと追いかけてきました


彼女はあのとき見せた笑みを浮かべ、ぼくの近くに寄ると取っ手を差し出した。
幻想的で、まだ夢を見ているような気がした。傘はぼくが風に持って行かせてしまったものだった。



どうぞ





わざわざよかったのに


諦めていた傘がそこにあって吃驚した。きっとぼくは驚きのあまり目を大きく見開いていたはずだ。



もう充分に雨をお楽しみになったでしょう?
これ以上躰を雨に晒すのは毒ですわ


上品そうに言って彼女は差し出した。



でもあなたも濡れてしまうでしょう?
家か、せめて雨をしのげる場所まで
送りましょう


ぼくは落ち着きを取り戻し、傘を受け取り声を掛ける。彼女は目をしっかりと合わせたまま、左手で拒否を示した。



いえ、もとより傘など必要ないのです


柄を確かに握ったのを確認すると、彼女はふわりと飛び退いた。重力を感じさせないしなやかな身のこなしにぼくは目を丸くした。



私に魂を奪われてはなりませんよ


正面から強い風。水を含んだスカートの端が重たげに揺れている。



夢幻の中を彷徨いなさるな。
この街に合わないとお思いならば、
一度故郷に戻るといい。
きっと夢から覚めることでしょう


彼女の声は風の叫びに溶けた。
ぼくは傘を飛ばされまいとドームを正面に構えた。
風が止む。
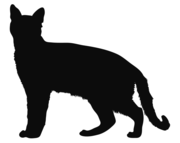
おそるおそるあげた傘の先には一匹の白猫。その猫はぼくが



あっ


と声を出す前に茂みに入って消えてしまった。
よくまわりを見れば、ぼくはまだ商店街へと抜ける道の途中で十字路まででさえ辿り着いていないのだった。
しばらく状況を飲み込めずにいたが、ある考えがぼくの頭を埋めていった。
無性におかしくなってぼくは来た道を引き返すことに決めた。
その先にあるのは雨に浮かぶ見慣れた街だった。
