***
***
――ふらりと気紛れに立ち寄ったその店は、料理の味こそ美食家の私の眼鏡には適ったものの、店員の態度がとにかく最悪だった。



お客様、先程は私どもの店員が大変失礼をいたしました


腹の虫も収まらぬままに私が早々に帰り支度をしていると、店主が一皿のスープを持って私のテーブルを訪れた。途端に、皿から立ちのぼる湯気とともに食欲をそそる芳しい匂いが辺りに充満する。一瞬怒りを忘れ、私はごくりと喉を鳴らした。



お口直しに、こちらのスープをどうぞ。訳あってメニューには載せておりませんが、上客様だけに振る舞っております、当店自慢の一品です。もちろん、今回はお詫びの印としてお代はいただきませんので、どうかご遠慮なさらず……


もう帰る気なのだと断りかけたものの、物腰こそやわらかだが言外に妙な圧迫感のある店主に気押されて、私は渋々とまた腰を下ろす羽目になった。その目の前に、優雅な手つきでスープ皿が置かれる。
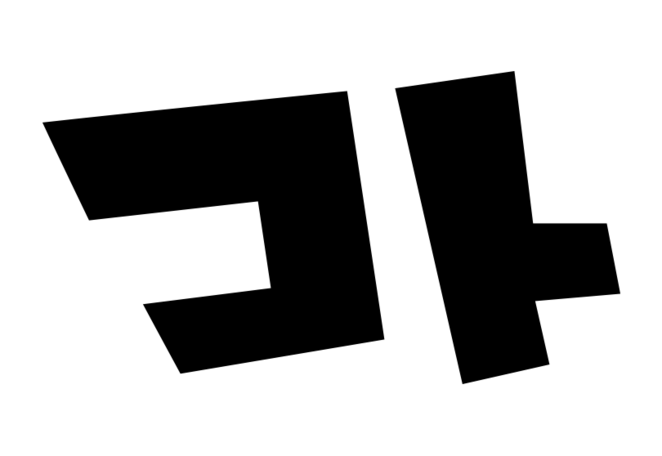

気が進まないながらも琥珀色のその液体を一匙掬って口に運び、喉に流し込んだ私は、思わず唸った。



おぉ、これは……!



未だかつて、私はこれほどまでに旨いスープを口にしたことはなかった。ひとたび口にしたが最後、スプーンを持つ手が一寸も止まらず、あっという間にたいらげてしまった。すっかり空になったスープ皿と私の顔を見比べて、店主はにこりと微笑んだ。



お口に合いましたでしょうか





う…うむ、なかなかのお味でしたな


先刻の騒動の手前もあり手放しで称賛するわけにもいかず、私はナプキンで口元を拭いながら口ごもった。しかしここで如何に取り繕おうとも、空の皿を見れば結果は一目瞭然である。咳払いをひとつした私は、なんとも言い難い居心地の悪さを誤魔化すように店主に尋ねた。



ところで店主殿、こちらのスープには何の肉を使っておられるのですかな


すると店主は意味ありげな笑みを浮かべ、こう言ったのである。



さぁ、貴方は何の肉だと思われましたか


これは、試されているのだろうか。問われると、私もまぁ、美食家として黙っているわけにはいかない。



そうですな……牛や豚でもなく、羊のような独特の臭みもなく……芳醇な旨味を持ち、蕩けるような舌触り……


過去に、このような肉を食べたことはあっただろうか。さながら辞書のページを手繰るように、自らの舌の記憶を探る。あれこれと考えを巡らせながらふと店内を見回したとき、私は少々奇妙なことに気が付いた。――隣のテーブルにいたはずの客のひとりが、いつの間にか姿を消しているのだ。
彼の席にある皿の上には、未だ食べ掛けの印にナイフとフォークが置かれていた。果たして彼は、いつから居なかったのだろうか。思い返してみれば、先刻のスープが私のもとに運ばれてくるよりもずっと前に、彼は席を立っていたかもしれない。となると、とうに小一時間は経っていることになる。便所にしては長過ぎるが、例えばなにか急用ができて、食事も半ばで店を出なければいけなくなったのかもしれないではないか。
いずれにせよ、私には微塵も関わりのないことで、まったく気にすることではない……筈だ。その筈なのだが、なぜか無性に気になって仕方がない。



そういえば……


昨今、我々美食家の間でまことしやかに囁かれている噂があった。
この街のとある料理店では、上客限定で特別な肉を使った料理が秘密裏に振る舞われているというのだ。平凡な人生を送る者は一生味わうことのないだろうその肉の正体は…
そう、ひととして絶対に口にしてはならない禁断の…

――脳裏に浮かんだこの恐るべき想像を、私は頭を振るようにして慌てて振り払った。
気にしてはいけない。
考えてはいけない。
ましてや、口に出しては…。



ときに店主殿……しばらく前から隣のお客の姿が見えないのだが、なにかありましたのかな


私の脳と直感は必死に抵抗し制止したが、時、既に遅し。冷静を装いつつも隠しようもなく震える声とともに、疑惑は私の口から零れ出てしまっていた。店主は一瞬表情を僅かに変えたが、やはりなんということもなさげに微笑んで、こう答えたのだ。



あぁ、そちらのお客様でしたら、先程お客様が召し上がったスープの……


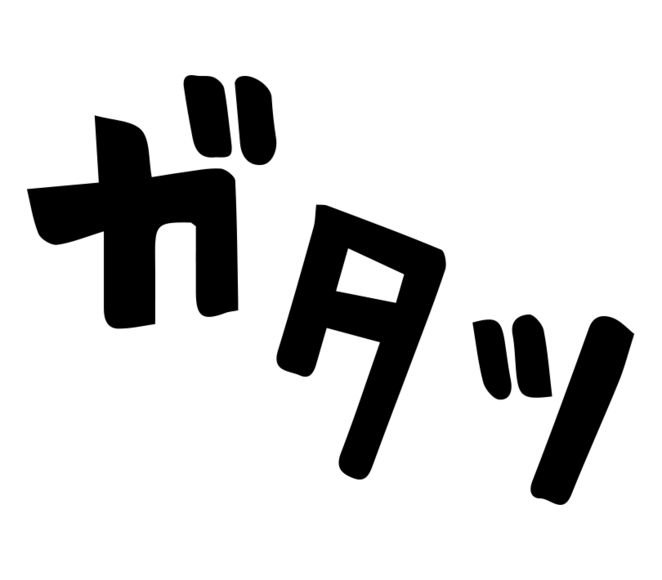
――皆まで聞かずに、私は意味を成さない喚き声とともに、取るものもとりあえず店から飛び出した。こんな恐ろしい店には、たとえ頼まれたって二度と関わるまい。そう心に誓いながら。
***
騒々しい客が、これまた騒々しく店を去っていった後。



あーあ、お隣に居た彼がそのスープを作ったんですよって言おうとしただけだったのになぁ……


オープンキッチンのカウンターにもたれ掛かりながら、この店の主である蔓澤枯風は、わざとらしく大きな溜め息を吐いた。その隣で、先刻の苦情の原因となった接客係の青年――アッシュが、他人事のように呆れ顔をする。



とか言って、オーナーあれ絶対ワザとですよねー。おっさん、可哀想なくらい真っ青な顔して出ていきましたよ


そもそも苦情とはいっても、元は不当な言い掛かりを付けられただけであったのだから、アッシュにしてもとんだとばっちりだったわけだ。とはいえ、世の中にはそんな道理の通じない客もいる。こちらに非があるにしろ無いにしろ、ひとまず無用なトラブルを避けるための対策として、お詫びにいくつかサービスをするなどはこの場合の常套手段である。店主もただ単にそれを行なっただけのことだった……たまたま休暇中に来店していた料理長に手伝わせて、噂話をヒントにしたちょっとした心理トリックを意趣返しに仕込んだほかは。しかしこうも容易く引っかかってくれるとは、さすがの店主も予想はしていなかった。
なるほど、態度が大きいのは小心者の裏返し、そして臆病者ほど無駄に想像力がたくましいというのは、よくある話だ。



いやいや、ちょっとした思いつきだったんだけど、これほど効果があるとは。意外と常識人でらっしゃったみたいだねぇ


苦笑交じりにそう言って、店主はひょいと肩をすくめる。



こんな悪戯は、もうこれっきりにしてくださいよ。店に変な噂が立ったらどうするんです


件の客の隣のテーブルにいた青年――若いながらもこの店の腕自慢の料理長であるセブが、厨房の中で手早くエプロンを外しながら、店主に渋面を向けた。



はいはい、セブ君もごくろうさま。もう戻っていいよ。久々のデート、邪魔して悪かったね





本当ですよ、まったく


ぼやきながら厨房から出てきた彼の背を、店主は労いの意を込めて、ぽんと叩く。



お詫びにアッシュ君が特製デザート作ってくれるらしいから許して、ってリルちゃんに謝っといて





ちょ……なんで俺が……!?


不意を打たれたアッシュが凄まじい勢いで振り向いたが、店主は気にせず、満面の笑みで客席にセブを送り返した。その背を見送り、少々納得いかない様子ながらもアッシュはデザートの仕込みに取り掛かる。



これは決してアイツの為ではなく、リルちゃんの為なんだ……


と呟きながら。
客席では、テーブルに戻ったセブを、リルケが笑顔で迎えいれていた。デートは仕切り直しとなったが、なんだかんだでこの手の騒動にはすっかり慣れっこの彼女である。おまけに、色気より食い気の彼女のことだから、デザート作戦も功を奏したのかもしれない。さほど怒ってはいないのが遠目にも見て取れて、店員一同、ほっと胸をなでおろした。それを合図に皆それぞれの持ち場に戻り、再び、店内に穏やかな時間が流れ出す。
――そんなわけで、料理店『蔓澤』は今日も平和だった。
<終>
