“いま思い出せる事を語ればいい。どうせ時の流れは本当も嘘もつくのだから”
佐藤真一(1994)


“いま思い出せる事を語ればいい。どうせ時の流れは本当も嘘もつくのだから”
佐藤真一(1994)
たぶん1991年のこと。


記憶が確かなら、僕の初恋は小学二年生の春である。
SAちゃんは当時ムチムチに越えていた冴えない僕の机に愛くるしい笑顔でよってきた。



えへへ


微妙にマロ眉だったと思う。
限りなくひな人形の一番上の姫の面影がいま重なるからだ。



はしもとくん、これあげる



セリフはもう定かではないが、
僕の机に差し出してくれたのはオレンジと黄色の優しいグラデーションの表皮で包まれたままの鬼灯(ほおずき)であった。
たしかまだ僕は恋や愛がよくわかっていなかった為、
ただただ清々しくて心の奥で火照る何かに酔いしれていた。
その皮ごと美しい鬼灯を僕のお道具箱の奥底で大事に管理した。

時折様子を伺っては、
日々出し入れする筆箱や色鉛筆等々の強固な文房具達に誤って押しつぶされないようにポジショニングに気を配りながら愛でるように閉まっておいた。







そして夏が過ぎ、
秋が来て、
冬が去り、
また春が来た頃にはクラス替えでSAちゃんとは離れ離れのクラスになった。
その間、
SAちゃんとどんな会話をしてきたのか全く思い出せない。



おはよう


きっともじもじしながら挨拶を二回三回交わした程度だと思う。

たしかいじわるなクラスメイトに机奥底に大事にしまっていた鬼灯の存在がバレて、
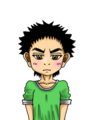


もうお前それ腐ってんじゃね?



と煽られたときにキレて取っ組み合いの喧嘩になった気もするが、それは自分を男らしく美化したい幻の記憶かもしれない。
ただ鬼灯の実がとっくに腐っていたのは事実で、それをどう処分したかは未だに思い出せない。
あれは間違いなく自分の半生の中で五本の指に入る至宝だった。いや、人生最初の宝物といっても過言ではなかっただろう。
少なくとも初めて女の子にもらったプレゼントには違いないはず。
振り返ればあの鬼灯は無償の愛を持っていたに違いないSAちゃんがクラス中のみんなを喜ばせるために配りまわっていて、たまたま太っちょの僕の番に回ってきただけの事だったのだろうと推測する。
あれから約30年。
SAちゃんはどんな風に成長しているのだろうか。
あの愛しのマロ眉はその後伸びたのか。
そもそもあの鬼灯はどこから拾ってきたのか。
きっとその答えは当人も誰も覚えてはいない。
とにかく渡る世間に鬼はない。

終わり
(本作は曖昧な記憶に基づいて構成されております)
