眠ったまままったく動く気配のないアーロンドを見下ろしてバーンはコーヒーに口をつけた。



なんだか嫌ね、ここに泊まるの





仕方ないさ。アーロンドがこれじゃ


眠ったまままったく動く気配のないアーロンドを見下ろしてバーンはコーヒーに口をつけた。



のう、バーリンは魔力の塊だと言っておったな?





え? そうよ。結晶化と呼ばれているけど。魔力とは言っているけど、死体を分解しても魔力エネルギーは取り出せないから、変質してるみたいだけど


そこまで言って、ミニアははっとして言葉を止めた。ぼんやりとした表情で説明を聞いていたサイネアの視線を気にしたからだった。どこか呆けたような空気はいつもと変わらないはずなのだが。



ごめんなさい。物みたいな言い方をしたわね


質問に何気なく答えていて気が付かなかった。ミニアも時々忘れてしまうが、サイネアは白い羽を持つバーリンなのだ。自分たち人間とは違うものだと突っぱねたようで、どこか心が痛む。だが、当のサイネアはそれほど気にした様子もなく話を続けた。



よいよい。しかし、そうだとすると何故わしは魔法が使えんのじゃろうか?





ほかのバーリンはみんな使えたのよね?





そのはずじゃ。群れではわしだけがずっと使えんかった


腕を振っても、念じても、想像しても。何をしてもサイネアの手から魔法が生まれることはなかった。それと同時に同胞が人間を傷つけるのにも疑問を持った。そのうちにサイネアは少しずつ仲間から遠ざかっていった。



バーリンの体を作り、人間の中で生み出されるものか





人間だって百年以上も研究してるのよ。それでもわからないの。やっぱりパンドラの匣を見つけるしかないのかしら?


自分の槍を見つめたミニアはそれを手にとって何とはなしに槍の手入れを始める。魔法技術に優れるミニアもこの槍がなければ無力だ。村正やあのトカゲバーリンの前では共にあったとしても戦うことなどできないだろう。
それでも戦いだけでなく生活の中でも常に扱っている魔法が使えないという不便さは、人間にとって想像に難くない。バーリンの世界では敵である人間を襲う手段でもあるそれが使えないということは存在価値そのものに直結するとも言えた。
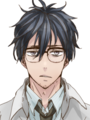


結局ここにはなかったみたいだな





そうね。次の目的地は遠いの?



バーンが研究室から持ち出していた地図を宿の机に広げた。広大な縮尺の地図は今の話題にはそぐわないが、適当に持ち出してきたのだから仕方がない。アーロンドのバックパックの中身を探れば出てくるかもしれないが、勝手に中をあらためるのは三人とも気が引けた。



次に近いのはここで、可能性が高いのはここか





どっちも結構な距離があるわね。やっぱり車が欲しいわ


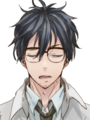


どうせどこもろくに道なんて整備されてないから、ダマスカスほど便利じゃないさ


慰めるバーンの声は少々投げやりだ。アーロンドを背負ってきたダメージが、今まさに彼を襲っているところなのだろう。人間二人を抱えてきて平然としているミニアのほうがよっぽど不可思議な存在なのだが。



そのことじゃが、ひとつ心当たりがあってな


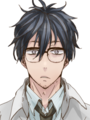


匣の場所についてか?


食い入るようにサイネアを見たバーンに怯えたようにサイネアが眠っているアーロンドのベッドに近づく。それを見てミニアがものすごいとしか表現できない形相でバーンを睨みつけた。



怖がってるでしょ。やめなさいよ





君のせいでこっちも逃げ出したい気分だよ


やれやれ、と肩をすくめたバーンは少しサイネアから距離をとるように椅子を動かすと、そこにゆっくりと座った。



それで何の心当たりがあるんだ? 最近思い出したってことだよな





うむ、おそらくという程度じゃが。やつの出処に覚えがあってな


そう言いながらサイネアは壁に立てかけられた一振りの刀を見た。暴れまわっていた村正も今は鞘に収まり、沈黙を守っている。



やつってこの妖刀のこと?





うむ。わしの思い違いでなければ、何か知っているかもしれぬ、パンドラの匣についてのう


サイネアがじっと村正を見るが、当然何も答えが返ってくることはない。もしかすると何かを言っているのかもしれないが、それを聞き取れるのはアーロンドだけだ。



じゃあ早くアーロンドにはよくなってもらわないとね


最後にアーロンドの頬をそっとなでてミニアは立ち上がった。二人の部屋は隣。相談はサイネアの言うとおり、村正に話を聞いた後でいい。
バーンに後のことを任せ、扉をゆっくりと閉じる。
サイネアが村正を知っている。バーリンとして生きていた頃のサイネアを誰も知らない。ただ、村正を知っていることにあまりいい予感はしなかった。
暗闇に怯えてミニアの手をつかむサイネアと共にいながら、ミニアはどこか自分の胸の奥に広がる苦味のある異物の正体をはかりかねていた。
