久しぶりのダマスカスにあまり落ち着けなかったのだろうか。アーロンドは数時間の短い睡眠の後、目を覚ました。
久しぶりのダマスカスにあまり落ち着けなかったのだろうか。アーロンドは数時間の短い睡眠の後、目を覚ました。



やはり落ち着きませんね


重い体でベッドを抜け出して眠い目を擦る。この時間だと雑貨屋はまだ開店していないだろう。コンビニエンスストアと呼ばれる一日中営業している店舗もなくはないが、アーロンドのお気に入りのハーブティーは並んでいない。
コーヒーを飲むくらいならとりあえず水で済ませてしまおうか。アーロンドはあまり働かない頭を撫でながらキッチンへと向かう。するとサイネアが、何かをカップに入れて小さな口で飲んでいる。




サイネア、お水ですか?





いいえ、野菜ジュースを買ってきたの。気に入ってくれたみたいで良かったわ





ミニア。どうしてここに?


サイネアと同じようにカップを傾けているミニアはたぶんコーヒーを飲んでいるだろう。ゼミの研究の時からミニアは決まってコーヒーだった。もはやカフェイン中毒だ、というのはカフェイン嫌いのアーロンドの言だが。
ミニアは答える代わりにテーブルの上に置いた紙袋を指差した。開けてみるとアーロンドのお気に入りのドライハーブの小瓶が入っている。



誰かが来たからって簡単に扉を開けさせちゃダメよ。ここは田舎じゃないんだから


どうやら先に起きていたサイネアが招き入れたらしい。



そりゃ旧友が深夜にこっそり村を出て、女の子連れてきてたら気になるでしょ





それはそうなんですが、特に面白いこともありませんよ


村に黙って出てはきたものの、特に追い出されたというわけではない。ただちょうど良い旅立ちの日が来たと感じたというだけなのだ。



別にいいわよ。久しぶりにアーロンドに会えたから徹夜で仕事終わらせてきたの





そんなことをしていると体に障りますよ


アーロンドは呆れたようにポットにハーブを入れ、残っていたお湯を注いだ。少し冷めているくらいが香りを損なわずに済むのでちょうどいい。
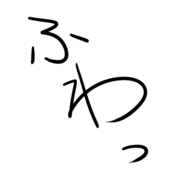



今日もお仕事ですか?





えぇ、有給休暇がどんどん溜まっていくのに全然使わせてくれないんだから





お役所仕事は大変ですね


だらりと机に突っ伏したミニアを見て、アーロンドは苦笑いを浮かべる。こんなミニアは決して防衛省の中では見ることはできないだろう。学生時代を知っているアーロンドの前だからこそこうしてだらけた姿を晒すことができるのだ。
防衛省の主任を務め、炎の魔法を扱いながら焼き払うのではなく攻撃を防ぐ勇ましい姿と身持ちの固さから『不可侵槍壁』の異名をとることをミニア本人は知らない。もちろんアーロンドもだ。
アーロンドの中ではミニアは学生時代の猪突猛進な鉄砲玉のイメージのままで、教授や友人から『炎髪の戦乙女』だの『獅子心女王』だのと呼ばれていた無鉄砲な旅仲間だ。今もキッチンの脇に立てかけられた彼女の三叉槍は戦闘・護身用で、よく手入れされた穂先が朝日を浴びて光っている。



一回突くだけで三か所も穴が開けられるなんてお得じゃない


というのはミニアの言だが、今の彼女しか知らない人間が聞いたところでまさかただそれだけの理由で扱いの難しい三叉槍を使っているなど夢にも思わないだろう。



お昼は何があっても出てくるから。図書館前で待ち合わせよ





そんなに無理をしなくてもいいんですよ





好きでやってることなんだから。あ、その、久しぶりに学生時代の友達に会えて嬉しいってだけよ



ミニアは残っていたコーヒーを一気に飲み干すと、飛び上がるように立ち上がった。



じゃあまたお昼ね。約束、忘れちゃダメだからね!


慌ただしくアーロンドの家を飛び出したミニアをサイネアがカップを片手に見送った。どれほど会話を聞いていたのか知らないが、不思議そうな顔をして走り去っていくミニアを見ているところを見ると、あまりよくわかっていないようだ。



何故あの女は走って行ったのじゃ?





きっと遅刻しそうだったんですよ


本人の名誉のためにそう言っておく。もうアーロンドとて幼く世界を知らない若者ではない。ミニアの気持ちも完全ではないにせよ、少しくらいはわかっているつもりだ。
それでも妖刀の呪縛に縛られた者には簡単に答えられるものではない。



私たちはもう少しゆっくりしてからいきましょう





うむ、ではわしは寝なおすとするか。あの女、開けなければ扉を壊す勢いじゃったからのう


やはりそうでしたか、と納得しながらもアーロンドは言葉に出さずハーブティーのおかわりを淹れる。図書館が開くまでにはまだ十分時間がある。
サイネアにならってもう一眠り、とも考えたが、アーロンドはぼんやりとしたまま椅子に座って朝焼けを眺めていた。
