真鍋(まなべ) 透(とおる)。三十五歳。
身長は女性にしては高めの165センチメートル。内3センチはかかとのヒールを含む。
大学入学を機会に上京し、一人暮らし歴は十年以上。培った家事スキルは可もなく不可もなく。得意料理は鍋。夏でも鍋。理由は、楽だから。

書籍「He is Ms.ゆうき」収録の短編、その試し読みです。
真鍋(まなべ) 透(とおる)。三十五歳。
身長は女性にしては高めの165センチメートル。内3センチはかかとのヒールを含む。
大学入学を機会に上京し、一人暮らし歴は十年以上。培った家事スキルは可もなく不可もなく。得意料理は鍋。夏でも鍋。理由は、楽だから。



江本。昨日の報告書がまだ出てないようだが?





すいません警部!
午前中には必ず…!


職業は警部。
今日も今日とて束になった書類をわしづかみ、事件の前後を探る視線は鋭い。
広いデスクを占める紙の海が透をデスクに縛り付ける。事件の報告が飛び交うオフィスの中で、眼光鋭い女性警部の周囲だけがいやに静かだった。



……。


そして、西日がブラインドをじりじりと焦がし始めたころ。
彼女は不意に視線を投げる。
署内のメンバーを見渡し、無言のまま足を組む。口端を吊り上げる。
流線を描く美しい皺の入ったスーツパンツの上で、がっさがさに荒れた指がゆっくりと絡み合った。
ごくり。誰かが息を飲む音が耳に届く。緊張感が広がる。
デスクチェアに深く身を預けた上司は静かに目を伏せ、噛みしめるように息を吐いた。そして部下の視線に囲まれる中、キッと目を見開く。



被害者にもう一度
コンタクトをとる!
私が行こう。
……江本ついてこい!


室内によく通り、身が引き締まる声色だった。
大阪府警察本部刑事部、第二課統括警部、真鍋 透。―人呼んで、《鬼の真鍋》
肩にかけていたジャケットに改めて腕を通し、足早に出ていく女傑の後姿。残された部下がぽろりとこぼす。



警部、今日もえげつない程かっこいいな……


新人警部補が慌てて追いかける女性は、すでに窓の外、愛用のハイブリットカーに身を投じていた。
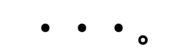
判断が早く、行動力に優れ、常に真剣で真面目。そして自分にも他人にも厳しい。
そんな女上司こと真鍋 透は、もちろんのこと仕事も優秀だった。
巡査からスタートした警察人生も、あれよあれよという間に昇進の舵を取る。ノンキャリア組の警部では最年少に当たるというのも、まごうことなきただの事実。
川でおぼれた子供を助けるためにワニと格闘したとか、暴走族を取り締まるため一人大型バイクで大立ち回りを演じたとか、伝え聞くエピソードは誇張表現だろうが、しかしあながち嘘だとも言い切れなくて。
「真鍋警部だからなぁ」の一言で説明がつくその言外の肯定こそが、透の勇猛果敢かつ大胆不敵な仕事ぶりを表していた。
部下からの信頼も厚い。こと仕事に関しては後輩や新人にも容赦ないが、現場たたき上げで培った『生きた仕事ぶり』はなによりも『警察官』を育てる見本となる。
たばこがやめられないのは玉に瑕だが、窓際で煙を吐き出す姿が見れないと逆に寂しかった。人間性はドライで冷静な印象が先行するものの、実際は部下に人情味ある指導を施し、無関心なようでよく見ている。まさに理想の上司像があった。
……そんな、絵に描いたようなやり手の警部に、唯一の欠点を上げるのならば。



さすがお転婆姫。
本日も現場急行からの事件解決、お見事でしたよ





またお前か、橘。
息するようにおべっかが出るのはある意味才能だな


真鍋 透には、
致命的に欠如していた。



これはこれは、いつもながら手厳しいですね





のちの警視総監様は、こんな所で女の尻を追いかけている場合じゃないだろう?


かわいげ、愛嬌、親しみやすさというものが。
ことごとく、欠落していた。
ひょろりと背の高い優男が真鍋に話しかける。橘と呼ばれたその人物の妙に馴れ馴れしい態度も、透のそっけない塩対応ならぬ、嫌味が効いたスパイス対応もまた、いつもの光景で。



また始まった……


第二課の名物副官、江本が小さく顔を歪ませる。
外回りから戻るや否や聞こえてくるやり取り。周囲の同僚たちから突き刺さる哀れみの目。結局、誰も助けてはくれなかった。
しかし、優秀な部下である彼には、憂鬱にさいなまれている暇すらない。



まぁいい。
本日の結果をまとめる。
江本、来い!





は、はい! 警部!


颯爽とオフィスを抜けていく濃紺のジャケットのあとには、カツカツカツと余韻だけが残る。
真鍋 透。三十五歳。独身。
スカートは高校卒業以来縁がない。髪は毎日梳いてはいるものの整えられているとは言えず、化粧気もゼロ。三白眼。そしてシワひとつない白いブラウスは凹凸の影すらなく。服の上からでもわかるAカップ以下のまな板。
訂正。愛らしさと色気もなかった。
人間的には憧憬の対象である、まさにかっこいいを体現した警部も、女性レベル的にはスライムだった。いや、それはスライムに失礼だ。ミジンコ、いや、アメーバか。性別がないという意味ではおあつらえ向きである。
そんな、世捨て人ならぬ女捨て人の孤高たる後ろ姿を眺めて、にやりと笑う男が一人。



うーん、
今日もいい感じに
かわいくないなぁ


橘(たちばな) 奏多(かなた)。二十九歳。
大学院を卒業と同時に警察庁の国家試験を受け、見事合格を果たしたエリート。俗に言う、キャリア組。
官僚の第二子として生を受けた帰国子女で、英語、フランス語、ドイツ語、中国語を自在に操るバイリンガル。大学は日本国内最高峰を卒業後、アメリカに飛んで博士号を取得した。
身長は190センチメートル。細身の体格から伸びる脚は長い。たれ目の瞼の奥に潜む、すべてを見透かしたような瞳が危なげな雰囲気を漂わせ、日本人離れした顔立ちが周囲の目を引き付ける。
まさに家柄良し、外見良し、学歴良し。おまけに運動神経まで良かった。剣道とバスケットボールに明け暮れた学生時代。今もなお定期的な運動は続けており、体力には自信がある。
カッターシャツを腕まくりし、外灯に照らされ投げた3Pシュートは、見事な放物線を描いて公園のバスケットゴールに吸い込まれていった。



ん? なにか言ったか?


帰り、気晴らしにどうだ? と誘ってきた同僚が、コート脇のベンチでタバコを吹かす。誘ってきた割に早々とバテたらしく、大きな満足感とともに座面についた手のひらは当分起き上がる兆しを見せない。
歳と運動不足を感じさせるその様子に小さく嗤って、橘は再び口を開いた。



真鍋警部ですよ。女を武器に、なんて言うタイプではないのは分かってるんですが、もうちょっと、こう、柔らかな対応をなさったらいいのに、と思いまして


言いながら軽い動作でボールを投げる。ゆるく軌道を描いた橙色のゴムの塊が、パスン、と耳触りのいい音を立てて赤い輪に収まった。
おー、お見事。
同僚の口からこぼれる。
まるでシュートが決まることなど最初から決定事項だったかのように、そのほめ言葉は無感動で味気ない。ちゃぷん、と蓋をしたミネラルウォーターだけが、ボトル内部で騒いでいる。



しっかし、
そりゃ無理ってもんだろ


そして、無味無臭の響きはさらに延長の進路をたどる。精悍なイケメンの顔を見もしないで、同僚の男は決定づけた。
一切疑いのない断定の推量。奏多がせっかく包んだオブラートにも容赦ない。言葉にしないだけで、中身も正確に把握していることを匂わせた。
つまり、それほどまでに真鍋 透という人物は。



あの女は、……アイツは、とっくの昔に女捨ててやがるからな。
もちろん身体能力に性別的な差はあるが、あの態度であの扱いだぞ?
もう性別なんぞ超えて《警部》っていう固有種だ。今更女扱いしたところで本人も喜ばねぇだろ


身をのけぞらせてスラスラと答える中年。疲れが体を襲うのは早かったが、同時に回復も早かったらしい。言い捨てるような口調には力があった。



……彼女は、何か理由があって、そういった対応をなさってるんですかね?


奏多もまたそんな男の様子に頓着せず、鈍い音を立てて跳ねるボールを拾いあげる。
頭の隅には、あの力強い指示を飛ばすたくましい後姿が浮かんでいた。署内ではすでに見慣れてきたあのスパイス対応だが、いつからなぜあんな事態になってしまったのか。



いや、ないだろう。
ありゃアイツの素だよ素、飾り気なさすぎの素の状態。
要するに、なるべくしてなったモンだ。元々そんな美人でもねぇしな。
目つきは悪いわ、口調はきついわ、乳もないわ……





それは確実に名誉棄損かつセクハラですけどね


「あーあ」と息を漏らす奏多に向けて、男は「だがじじつだろ?」と返す。
己の体型は棚に上げてハキハキと答える中年。胸への理想と期待と愛情は深いらしい。言い聞かせるような口調には余裕があった。



まぁ、……


奏多はそこで言葉を止める。まぁ確かになかなかどうして否定できない。
不明瞭な相槌が、夜の冷えた空気にしみこんでいく。
車両が通り過ぎる悲鳴が、近くの線路から重々しく届いていた。次第に大きくなる電車の音。二人は黙って通過を待つ。
そして、生ぬるい風も収まった頃。
同僚はふと、何かを言いたげに目を細めた。いつの間にか唇には次のタバコが用意されている。副流煙が宙に昇り、次いで主流煙が吐き出される。
公園の照明が、ゆっくりと瞬きする。
ま、大したことじゃないんだけどよ。タバコを指に挟んだ男は、観念したように力なく笑った。



……俺は真鍋にあこがれる若造をよく見てきた。
どいつもこいつも最初は『かっこいい』とか言ってたくせに、途中で気付くんだ。アイツの人生の選択肢に恋愛や結婚が一切含まれないことにな。
そんで、実感した奴から勝手に引いていく。
あまりのストイックさに付いていけねぇんだとよ


言葉が途切れる。
続きがあるはずのセリフに、奏多もまた口を挟まない。
語り部は持ち運びの灰皿ケースにタバコを押し付けた。そして、顔を上げた先、深層心理の読めない目が淡々と己を見降ろしているのをチラリと確認して、言葉を続ける。



けどな、それに対して真鍋が何かコメント残したことはねぇし、傷ついたなんて聞いたことがない


アイツにとってはどうでもいいんだろう。他人からなんて思われようが、どんな評価をされようが、どうだっていい。重要なのは、事件の解決と犯人の確保。そうやって仕事にだけ打ち込んできたのが、真鍋 透っていう人間だ。



……だから、アレにかわいげなんて求めるんじゃねーよ


そう締めくくって、男は夜の空を見渡すように視線を外す。ふーと大きな息をつき、灰皿ケースをポケットに入れる。
奏多は見逃さなかった。
教えを説くような口調で、思い出を語るように目を伏せ、うつむく一瞬だけ垣間見えた男の表情。見下すような嘲笑ではなく、どうしようもなさ漂う苦笑でもなく。一切のマイナスの感情が含まれていない、物事を正しく認識した理解の笑み。確かな自信に裏付けされた、知己のための許諾の笑み。
しん、とした空気の中に、トン、とボールの弾む音がする。
同僚の目は、今度こそしっかりと奏多を捕まえていた。さぁ、どう返す? 無言のまま、眼だけがそう言っている。



……なるほど。
下手な期待はせず、そういうものだと認めてやれ、ってことですか


そして青年は、色のない目に黒々とした光を宿して、ゆっくりとうなずいた。
元々、特に不満や不平があってこぼしたわけではなかった。ただ、ほんのわずかな、気まぐれに等しい、世間話の一環としての興味が、最年少の女性警部という人物について口を出していた。
しかし、結果はどうだ。部署替えで数か月前に知り合った自分にとって、同僚が語るあの真鍋 透の紹介は、十分に。



……面白いですね


思わず、こぼしていた。
これが仮に、女を捨て男装して生きる道を選んだなんて言われたら。少々ナイーブな問題だが、心身の食い違いで性別を違えて生きているとでも言われたら。
橘 奏多は理解こそすれ、踏み込んだ興味など抱かなかっただろう。『世の中にはそういう人もいる』と納得してしまえば、それ以上の詮索は余計だと思えただろう。
なのに、真鍋 透には込み入った事情など何もなかった。
そもそも彼女は女を捨てるなんて宣言していたわけではない。男らしくしようなんて気概はもちろん感じられない。毎日当然のように女性用の制服を着ているし、カバンも靴もレディース仕様だろう。
つまり、あれほど色気もかわいらしさも愛嬌も柔らかさも皆無の状態は、いたって自然に形成されたことになる。ただ彼女が彼女らしく過ごしていたら、あんな状態になったというだけだ。



……それなら、なんの気兼ねも要りませんね


何かしらの事情を抱えての生き方がアレだったとしたら、後々面倒なことになるからと諦めもついたのに。
そんなことを考えても、もう、遅い。
理由がないからこその興味。
ほくそ笑んだ口元にボールをかぶせる。
それはまるで、悪戯を思いついた子供が計画を精一杯隠そうとしているようだった。それはまるで、ベンチより突き刺さる追尾性の視線から逃げているようだった。



お、おい……。何をする気だ…?


同僚は焦りを混じらせ問いかける。



宮本さんも見たいでしょう?
あの真鍋警部が、ちょっと大人しくなるところ


橘 奏多は、嗤っていた。
人好きのする、愛想があってそれでいて少しミステリアスな目が、宮本と呼ばれた男を見据えていた。
危険な香りが漂う一方で、妙な安心感を与える微笑を浮かべ、悠然とそこにたたずんでいた。
口にくわえたタバコに火をつけるのも忘れて、男はつばを飲み込む。ざわ、と街路樹が揺れる。吹きすさぶ夜の風が、肌をこする。
……思い出した。そうだ、こいつは。

橘(たちばな) 奏多(かなた)。二十九歳。独身。
容貌、体格、センス、頭脳、地位、所得、将来性。男が欲しがる全てを手に入れ、己の優位性を利用する力に長けた彼は、モテた。おモテになった。むしろモテないわけがなかった。ホルンで呼び出される奈良のシカのように、女たちは集まった。そこに鹿せんべいのごとく口説き文句がふるまわれ、女たちは群がった。入れ食いだった。
しかし、現在に至るまで、橘は誰とも付き合ったことはない。
本気の交際ならば、なおさら。
それもこれも、この男にとっての《女》とは、所詮はただの《攻略対象》でしかなかったからだ。
生まれ持っていたセンスのアビリティをフル活用して選んだアイテム「ほめ言葉」を並べ立て、無限湧きする所持金を湯水のように使い、最後にスイートルームのカギをちらつかせるだけで、女は釣れる。自称≪難攻不落≫のお嬢様も、それならばと少々力を込めて、「キミだけだよ」と「本気なんだ」のの2コンボを繰り出した結果、あっさりと陥落した。
チョロい。チョロ過ぎる。
要するに、彼はスペックにものを言わせて遊びまくっていた。職場を上がると、行きつけのバーを訪れ、最後のシメはおじや、ではなくホテルだった。夏でも鍋は旨い。出汁にもよるが、うどんよりもごはん派だった。毎晩同じウイスキーを頼み、違う女と寝た。
……そんな己だからこそ、奏多には自信があった。
あの真鍋 透を、僕が女にしてやろうではないか。
それはただの思い付きだった。
自信と余裕に彩られた、暇つぶしの計画だった。



ねぇ宮本さん。もしあの人が僕に惚れちゃったら、共犯として一緒に考えてくださいね


とーん、とーんとボールを弾ませ、手に馴らす。



……なにをだ?





告白の上手な断り方


腕が伸びあがると同時に、ボールは宙を舞う。狙いを定めたシュートを、奏多は外さない。パスンと小耳良い音を立てて、ゴムの塊はゴールポケットに収められた。



…………


同僚の男は、返事を煙(けむ)に巻く。発想に呆れ、正気を疑う濁った瞳。不信を煽るその眼には、……しかしうっすらと好奇心の色が宿っていた。
短くなったフィルタを手元の携帯灰皿に押し付けて、黙ってベンチから腰を上げる。
地に落ちたオレンジ色のバスケットボール。一人ぽつんと壁に寄り掛かった。
夜が、更ける。

続きは書籍にて!5/5 COMITIA116「C13b」にて販売します!
