太陽が地平線に隠れる時、わたしはとある等身大のビスクドールと出逢った。
ショーウィンドウ越し見える麗姿、何より氷晶のような瞳に射止められた気がした。

太陽が地平線に隠れる時、わたしはとある等身大のビスクドールと出逢った。
ショーウィンドウ越し見える麗姿、何より氷晶のような瞳に射止められた気がした。
それからというものの、魂を奪われたかのように毎日あのパサージュにある骨董屋を訪れるようになった。
パリにやってきてから衝撃が走ったのは、「あの人」との出逢い以来かもしれない。そんなわたしの心の変化を見ぬいたのは、ただ一人だけであった。
オペラ通り 道路沿い



アリシア、最近、とてもたのしそうね





そ、そうかしら? そんなこと……


花売りのニナがたどたどしく尋ねてきた。
ニナはパリのオペラ通りで花を売って生計を立てている。女の子一人で動かせるのかと疑問を抱くほど大きな荷車に大量の花を乗せて、健気に客呼びをするのが日課となっている。
整った優しげな顔立ちから、声をかけるパリジャンも少なくはないのだとか。
ただ、彼女は耳が聞こえない。
後天的にそうなったらしく、長けた読唇力を発揮させつつもやっと会話ができる状態だった。



アリシアがたのしそうなの、3年ぶりかしら。
ほら、「あの人」の劇を観た時と、似てる。


ちょうど花を受け取った時に目が合い、いたたまれなくなって目を逸らす。彼女はどうやら読唇術だけでなく、読心術もあるようだ。
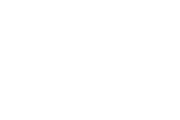
そう、「あの人」は、パリへ来て間もないわたしに光を与えてくれた。
オペラ・コミック座(※)にて、『カルメン』の舞台で深紅の衣装を身にまとい、表情をくるくると変えて踊り歌う花型女優の"あの人"。
突き抜けるような美声がシャンデリアを揺らし、わたしの心も揺らされる。
当時、オペラで出てくる女性像は「着飾った女性」や「貴族」が多かったため、『カルメン』は女性労働者が主人公で聴衆はびっくり仰天で息を呑んでいた。
しかも、主人公のカルメンが刺し殺されて幕が下がるものだから、観客席からは拍手が起きず……。 先鋭的すぎたビゼーの『カルメン』初演は、失敗に終わったと思われた。
※オペラ・コミック座
当時、パリ市が許可した四大劇場の一つ。
その中でも、特に庶民派だった。
他には、「パリ・オペラ座」、
「フランス座」、「イタリア座」があった。



すてき……!


しかし、わたしは違った。
カルメンの自由奔放な姿、袖を振って男性を誘惑する姿、恋に熱く身を焦がしながら刹那的に生きる姿――それらを演じる女優の"あの人"に、鳥肌が立つほど虜にされた。
あまりにも心を奪われたものだから、「あの人」と話をしたくてこっそりと舞台裏へ忍び込んだっけ。
すると偶然にも「あの人」と鉢合わせになり、緊張のあまり声が発せられなかったわたしへ妖艶な微笑みを浮かべてくれたのだ。



あらまぁ、可愛い野鳥さんが迷いこんだのかしら?
だめよ、ここは野鳥さんが来るところではないの。


囀るようにやわらかく注意すると、そっとわたしの手を包み込んで裏戸へ連れて行ってくれた。別れ際に思い切って



わ、わたし!
あなたの舞台に感動したんです。
どうやったらあなたのようになれますか?


と噛みながら尋ねると、"あの人"はブロンドの髪を耳にかけながら更に微笑んだ。



まずは練習が大事ね。
だけど、練習だけでは女優にはなれないわ。
まずはね、あのお月様のように真っ暗な闇の中でも自分から光を燈せるようにならないといけないの。
わかるかしら?


そう言い残し、「あの人」は風のように去って行った。
パリに来てからも絶望を味わっていたわたしに、「あの人」は光を燈してくれた。しかし――。
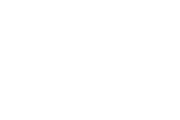



確かに、「あの人」と出逢えて良かったと思ってる。ただ――出逢えなかったら良かったのに、とも思ってしまう。





アリシア……。





暗い視界に慣れていたせいで、強い光が直視できないのかもね。


無理矢理口角を上げてそう呟くが、唇の動きから内容を察したニナは瞳を揺らしながら顔を覗き込んできた。澄んだ新緑色の目が、コルマールの小川を彷彿とさせる。



アリシア。私ね、あなたならオペラ座の歌姫になれるって信じてる……もちろん、私はあなたの声を知らないけど……。





ありがとう、ニナ。
お世辞でもそう言ってくれる人がいて嬉しいわ。


我ながらそっけない口調だったかもしれない。
いや、でもどうせニナはわたしの声なんて聞こえないから大丈夫だろう。
そう思い込み、繕うように口角を上げると、ニナは寂しそうな表情を浮かべた。
アール橋のたもと

今日も今日とてあの骨董屋に寄ろうとしていたが、運の悪いことに女子6人グループに鉢合わせとなった。しかも、彼女らはいつもわたしを虐めてくる意地の悪い集団である。



ちょっと来てくれない?


無理矢理腕を捕まれ、道路沿いからセーヌ川の川岸へ続く階段を降りる。まさか、と思って腕を振り切ろうとしたが、両脇の二人の力が強くてかなわなかった。
ここ、アール橋のたもとでは家畜の水飲み場があり、今のように夕方になると犬の水浴場と化す。
貴婦人の犬を預かった男たちは袖とズボンをあげて、せっせと犬を洗っていた。
そのうちの一人がこちらをちらちらと様子見しているが、助けてくれる気配はない。



今日は、なに?


恐る恐る目の前で腕を組んで立つ集団のリーダーに声をかけた。
正直、こんなことをしている場合ではないのに……と急ぐ気持ちを抑えて、紺色のスカートの裾を握りしめる。
するとリーダーの彼女はふんっと鼻を鳴らしながら鋭い口調でこういった。



あんた、今日もミシェルに媚を売ってたでしょ? あたし、見てたんだから


ミシェルとは、同じ学校に通うブルジョワジーの男の子のことだ。彼の社交性とハンサムな顔立ちから、女の子の間では王子様と呼ばれていることは世間に疎いわたしでも知っている。
そんなミシェルは今日、ニナから買った花を持ち歩いていたわたしを見て、



その花、君に似合ってる


と空世辞を言っただけなのだ。
それに対してそっけなくお礼を言ったまでで、断じて媚を売ったわけではない。



ち、違う! あの人はこの花を褒めてくれたようなもので……。


ニナから買った花を取り出すと、目の前の彼女は瞬く間に目をぎらつかせ、わたしの手からそれを奪った。



あ……!


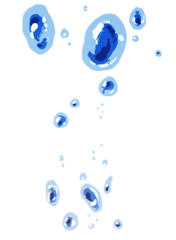

パサッと花がセーヌ川にのまれる。慌てて川に近づいて流されていく花を取ろうとした時、容赦なく背中を押された。



え!?


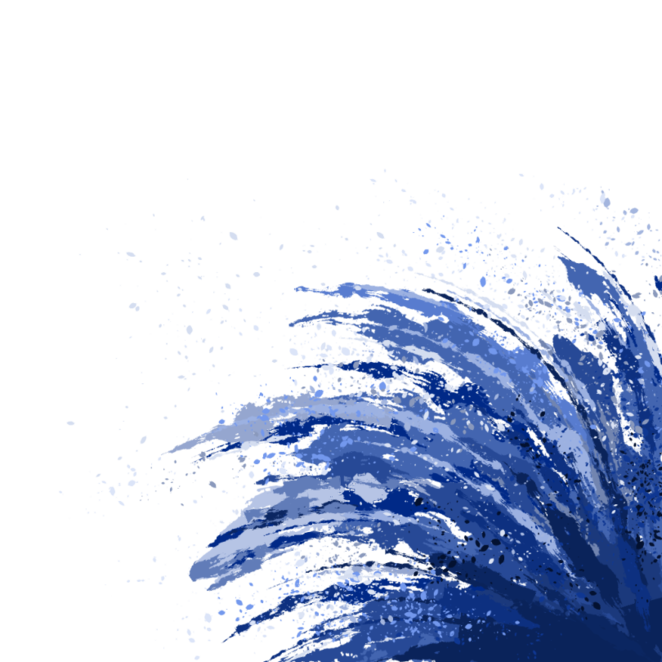
バシャンという音が聞こえる前に、冷たい水が耳に侵入してくる。
全身、針で刺されるような感覚に陥り、刻が止まったように思える。
あんた、気持ち悪いのよ
ミシェルが優しいからって調子乗るんじゃないわよ!
ほんっとう目障りね!! コション(豚)!
罵声が遠くで聞こえる。
なんて理不尽な。
――まあ、いいや。考えたって何も解決しないもの。
ぷはっと水面から顔を上げた時には、既に意地の悪い女子の軍団は、小生意気な笑い声を響かせながら橋を渡っていた。
リーダーの彼女――そう、信じられないことに彼女はわたしの双子の妹のエリゼ。
誰が彼女をあそこまで変えてしまったのか。昔の面影は一つも残っていなかった。



……アリシア、気にしたら負けよ


そう自分に言い聞かせながら川岸によじ登ったところではっとした。
花はどこにいったのだろう? 川下へ視線を追うが、時間から考えるとそう遠くまで流されていないはずなのに花はどこにも見当たらなかった。



お嬢ちゃん、何か探しものか?


小舟を漕いでいた見知らぬおじさんに



花を


と言うと、おじさんは川下を指さしながら甲高い声で答えた。



ああ、さっき若い兄ちゃんが拾ってったぜ。
川に流れる花を拾うとは、物好きなこってぇ。


その言葉に自分が川に落とされた時よりも落胆し、魂が抜けたようにその場で座り込み、水面に映る夕陽を見つめた。
しかし、ずっとこうしているわけにもいかない。
弾けるように立ちあがると、スカートの裾を雑巾絞りして、後ろに一つにまとめた髪も絞り、水気を落とした。



アリシア、大丈夫。貴方はいつもこうでしょう。


と、言い聞かせて感情に深入りしないようにした。頭のなかに骨董屋を思い浮かべ、それだけに専念する。



骨董屋、骨董屋……


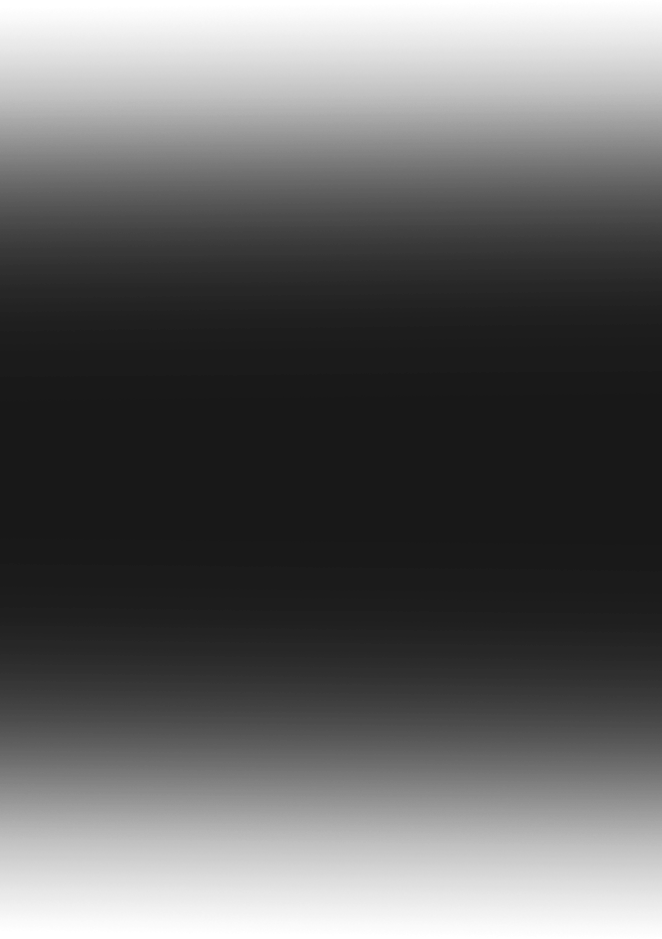
パサージュ・ショワソル

骨董屋を求める生霊のごとく、ずっと骨董屋と呟きながら20分ほど走ると、ようやくパサージュ・ショワソルに辿り着いた。

ガラス屋根には夕陽が反射しているものの、その中の通りはやはり薄暗い。
プティ・シャン通りは相変わらず老若男女問わずそぞろ歩きをしているにも関わらず、このパサージュだけ時間の波に置いてきぼりにされているようだ。
道のガス灯に点灯人が点火棒を伸ばして火を燈しはじめたので、そそくさとパサージュへ入ろうとしたその時であった。



お嬢さん、お嬢さん。


ふいに引き止められる。
わたしと同じ年代の男性点灯人で、こちらを見向きもせずに呼び止めたようだ。
灯柱に棒を近づけ、ぼっと炎がついた途端にくくくと笑いだす彼に身の毛がよだつ。



なにがおかしいのですか?





いやぁ、失敬。
なぁんにも知らないんだなぁと思ってさ。


ようやくこちらを向けた彼の表情は不自然に貼り付けられた笑顔で、ガス灯の光にゆらゆらと映しだされてよりいっそう不気味さが増していた。
彼は刹那、点灯棒を突き出す。
先端にはまだ火がついていて、目前でそれがぴたっと止まる。こちらに突き刺さるのでは、と思って目をつむったのは杞憂だったようだ。



この時間帯から夜にかけては気をつけなよぉ。
パリは「光の都市」なんかじゃない。
俺らがいくら街に灯りをともそうが、いまだに「地下都市(アングラ)」のままだ。


開眼した彼の瞳の眼光におののき、手で口を覆いながらパサージュの中へ逃げた。

心臓がバクバクと早鐘を打ち、手で口を覆ったままパサージュの壁にもたれた。



な、なんだったのかしら


パリには変わった人が多いけども、あんな不必要に笑顔で近づく人なんてそういない。いたとしたら、それは詐欺師だから信用してはならない。
ちらっと来た方向を見るが、どうやら追ってきてはいないようで安堵した。気を取り直して、人通りのない通路を歩き進める。
あたりを見回しながら骨董屋を目指していると、上方から足音が聞こえた。

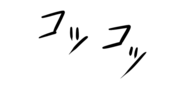
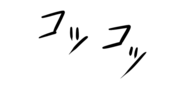
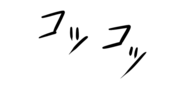



ん? なんの音?


上を見上げるが、もちろん誰もいない。
しかしガラス屋根が微動し、明らかにそこには誰かがいるかのように軽やかな足音が響いていた。
最初は小動物かとも思ったが、それにしては大きな足音だ。
さっきの点灯人の言葉に拍車をかけて不気味に思いつつ、歩を進める。
やっと【Antiquaire(骨董屋)】と書かれた太陽と月が半々に混ざった看板が見えた。
今日も今日とて散々なことがあって疲弊していたが、救いを求める気持ちでショーウィンドウを見ると、



いな……い……?


忽然と消えた彼にすっと血の気が失せた。
ガラスに手を置いて目を凝らしつつ中の様子を伺っていると、ちょうど


と扉が開き、心臓が飛び跳ねた。
出てきた人は、自分より少し年上で身なりの整った女性だった。おつきの人もいる様子から見て、お金持ちの女性だろう。口紅がべっとりついた唇に弧を描き、おつきの人に目配せした。
すると、おつきの人はたいそう大きな荷物を慎重に掲げてへこへこしながら女性についていく。



お嬢様、良いお人形が手に入りましたねぇ。
またコレクションが増えますなぁ。


『良いお人形』の一言で、それがあのビスクドールの彼だと察した。頭が真っ白になっていると、女性と目が合う。女性はわたしの顔を見てぎょっとし、



あなた、顔色が悪くてよ?
大丈夫?


と心配の言葉をかけてくれたものの、わたしは上の空で生返事をして踵を返した。
今日はパリに来て一番最悪な日だ。
帰宅して自室の屋根裏部屋にこもり、日記にそう綴った。その一言以外何も書きたくなくて、ベッドに力なく倒れこむ。
乾かすためにシーツの下に入れたびしょ濡れの服が体温を奪うものの、そのじめじめした感触が今のわたしの気持ちにそっくりに思え、シーツごと服を抱き寄せて眠りについた。
神様はどこまでもわたしを見放したいのね。
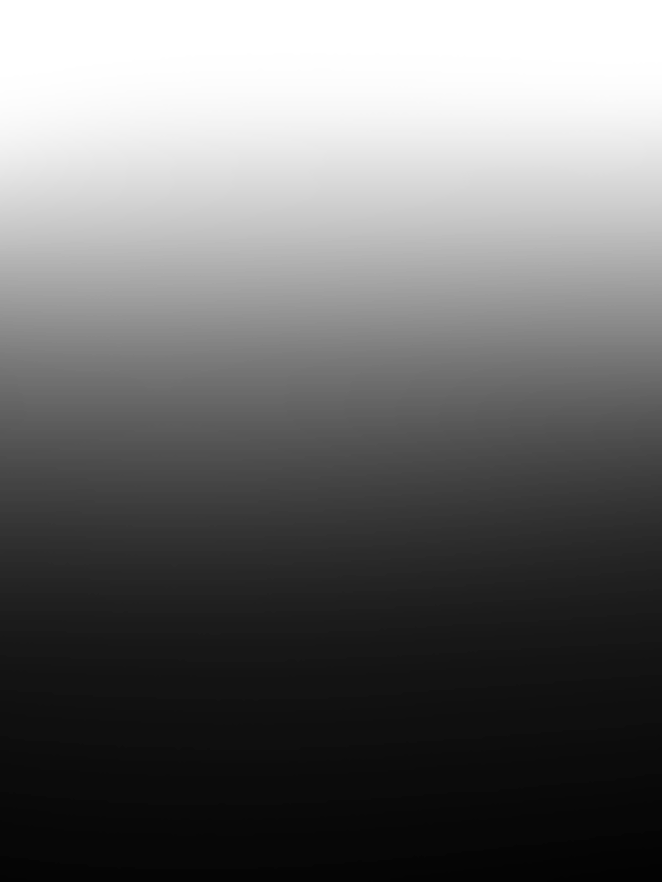
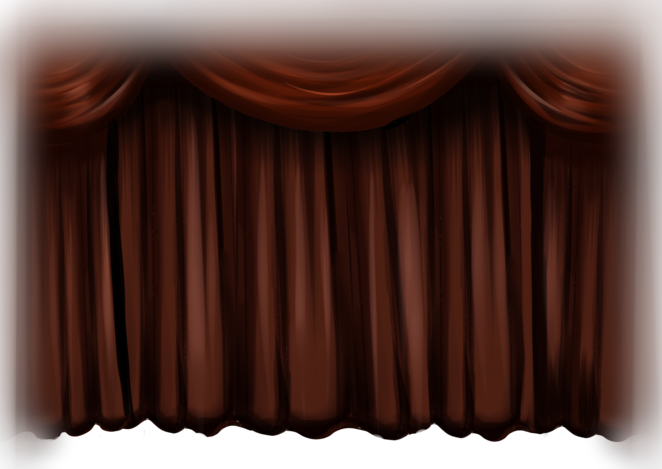

今回も文章に惹きつけられました。
文章からその様子が頭の中で再生されドキドキワクワクハラハラしながら読ませて頂きました。
途中の挿絵の細かさにも、驚きながら
楽しく読ませて頂きました。
またの更新?楽しみにしております。
ゆうさん>>とても励みになるお言葉に嬉しさで胸がいっぱいです。頭の中で想像しやすい文、要所の状況が分かるような挿絵を心掛けているので褒めていただけて大変励みになります!
素敵な感想を綴っていただき、誠にありがとうございました!
最新話読ませていただきました。背景、登場人物の表情、ストーリー、物語の中に引き込まれてしまいます!また地図が加わったことで世界観がとてもわかりやすくなりました。アベルは買われてしまうんですね。これからのお話がどうなるのか気になります。今回も楽しませていただきありがとうございました
星辰さん>>最新話も追って読んでくださりありがとうございます! 画像が付けられるのはストリエ様ならではの仕様なので、地図も入れてみて良かったです。
こちらこそ今回も読んで感想まで書いてくださり、誠にありがとうございました|´∀`)
絵と共に地図もあり、アリシアたちのいる世界が広がって行くにのが目に浮かんで楽しく読んでます。
アベルが買われた後、アリシアがどう動いて話しが進んで行くのか。。
続きをまた楽しみに待ってます。
ゆずかさん>>今回から地図も入れましたが、アリシアの広がる世界を共に感じていただけて光栄です! 今後の話の成り行きも是非ご覧いただければ幸甚に存じます。素敵な感想をありがとうございました!
アベルが買われてしまった…!と、アリシアたんよりも私の方が衝撃を受けたかもしれません(キリッ)
そしてエリゼ…彼女にも何かありそうな気がしておった…。