「おはようございます」



起立、礼。おはようございます。


「おはようございます」
私の号令に合わせ、元気の良い挨拶の声が教室に響いた。
今日は日差しが眩しく、とても蒸し暑い。それに蝉の声がとても煩くて、いよいよ夏も本番になろうとしているのをひしひしと感じた。



おはようございます皆さん。
期末テストも終わり、いよいよ夏休みも近づいてきましたね。ええ、それから・・・





先生の頭は相変わらず淋しいな・・・。


田中先生はいわゆるハゲだ。いつも朝礼の時彼の頭に注目してしまう自分を許して欲しい。だって頭のてっぺんだけ何もないんだもん。・・・いや、何でもないです。
でも彼はとてもいい人なので、できれば髪の毛に恵まれて欲しいと思う。



では夏休みまであと数日。皆さん気を抜かずに頑張りましょう。





気を付け、礼。ありがとうございました。


「ありがとうございました」
教室に再び響く男女の声。その声は心なしか、夏休みを前にして興奮しているような気がする。
7月13日。ああ、今日は全く、いつもどおりの朝だ。



あとは学級日誌だけ・・・今日も疲れたなあ。


気付けば窓の外はオレンジに染まり、教室も静かになっていた。どうやら学級委員の仕事を片付けていたら、気づかないうちにだいぶ時間が経っていたらしい。
学級委員の仕事とは案外面倒くさいことが多い。例えば今は、今日の分の学級日誌を書いている。これが地味に毎日つけなくてはならないためだるい。
まあ学級委員は別段やりたくてやっているわけではないが、まあ別にやれと言われればやれる程度のことなので別に困ってはいない。ただ時たまこう「面倒くさい」と思うときがあるのは仕方がないことだろうと思う。



『今日は体育の授業で荒川くんがカッコつけようとしたのに失敗して転んだのが面白かったです』っと





ま、このくらいは書いていいよね。


だってどうせ誰も読まないし。
と独り言を続けようとした私の視界を、突然白い何かが遮った。



お願いだからそれは忘れてってば。





って、荒川くん?


白い何かが遮ったと思ったのは、彼の髪の毛だった。
彼の髪色は白。悔しいがその色は非常に美しく、不思議と私はその色を見るたび目を奪われそうになってしまうのだ。私は平凡な黒髪だから、ちょっと憧れるのかもしれない。
まあどう考えても白い髪が自毛なはずがないので、明らかに校則違反をしているのは間違いないんだけど。ちなみに四月に入ったばかりの頃の私は「髪を染めるのは校則違反です!!」と毎日彼に言っていたけど、彼はへらへら笑うだけで全く直す気がなかったので私ももう諦めてしまった。



ねえねえそんなことより浅葱は今から帰りだよね?





えっそんなことな・・・





帰りだよね!





あっ、ちょ、ちょっとー!?


どうやら荒川くんは私の言うことに耳を傾ける気はないらしい。
抵抗を試みても男の人相手では全くきかず、彼にぐいぐいと腕を引っ張られてしまうので、私は観念して帰り支度を始めた。



今日は図書室に行こうと思っていたんだけどなあ・・・。


まあ仕方がない。荒川零とはこういう人間なのだ。
私は読みたかった本のことを少し残念に思いながらも、そそくさと下校しようとする彼の背中を追った。



彼女は無事に家に帰ったかな。


彼女というのは、先ほどまで俺の隣でにこにこと笑っていた彼女、浅葱凜音のことだ。
彼女とは出席番号が前後なことや、なかなかウマが合うということもあり、今年の四月からずっと仲良くしている。そのうち放課後彼女の帰りを待ち、彼女を送り届けるのが俺の毎日の日課となっていた。
という話をするとよく周りには付き合っていると勘違いされるのだが、実際そんなことはない。まあ俺のほうに彼女に気があるかと問われれば肯定するんだけどね。
でも彼女は恋愛には疎そうだから、この恋が実るのは当分先になりそうな気もする。



・・・?


ふと後方から冷たい殺気を感じ、思わず歩く足を止め振り返った。あたりの気温が一気に下がったのかと思ったくらい、夏だというのに肌寒い気すらした。



誰・・・?


振り返った俺は、気配のする方へと暗闇に目を凝らす。
そこには年のそう変わらないように見える、ひとりの青年が立っていた。この黒い世界の中で異質に浮いている、白。



僕? 僕は…





――輪廻の外側を、廻る者。


彼は俺の問いに律儀にも応えてくれた。しかし、その内容は要領を得ない全く不可解なものである。



生憎、何を言っているのか全くわからないな。





・・・そうか。だが君こそ僕に名乗っていないのだから、僕から君に丁寧に説明してやる義務はないよね。





・・・ああ、そうかもね。


随分と嫌味たらしい男だ。
その姿は夜の闇にそぐわない純白で、まるで天使のようだというのに。



で、要件は一体何?


こんなに冷たい殺気を纏わせて、俺に何をしようというのか。別に俺はこいつに何かをした覚えは全くないし、というかこれが初対面ですらある。だから背筋を伝う冷たい汗は、夏の暑さのせいだと思い込んだ。



単刀直入に言うよ。君、彼女に近づかないでくれるかな?


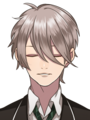


彼女って…凛音のこと?





もしそうだって言うなら、その願いは聞けないな。


俺がそう言うと、男は不愉快そうに眉を潜めた。
だが俺は怯まない。そもそもこの謎の男の話を聞いてやる義務なんか俺にはないんだから。



そう…。ならいいよ。彼女を不幸にする存在が近くにいるというなら、僕が幸せにしてあげればいいんだからね。





…は?





俺が彼女を不幸にしてるだって?


そんなはずはない、と否定したかったが、男は俺の話など何も聞かずに勝手に踵を返す。



じゃあね、不幸をもたらす少年くん。


そう言い残して去っていった彼の最後の声は、憎たらしいほど透き通った声だった。



不幸をもたらす少年…ね


零はそう呟くと、先ほどまで男が居た場所を意味もなくぼーっと見つめた。
すでに辺は何事もなかったかのように静寂に包まれ、先ほどのできごとは全て夏の暑さがみせた夢だったんじゃないかという気すらしてくる。
――でも、未だ背筋を伝う汗が、それらを現実なのだと物語っていた。
これはとあるひと夏の――少女たちが紡ぎ出す、美しい幻想物語。
