もう随分と空は暗く、その闇の中で2つの人影はゆっくりと動いていた。
もう随分と空は暗く、その闇の中で2つの人影はゆっくりと動いていた。



ミオ、大丈夫かい?


心配そうに見つめる瞳で、少年は少女を気遣う。



ふふっ、そんなに心配しなくても大丈夫よ


二人は、この先にある街に向かって歩いていた。予定ではもう少しでたどり着けるはずなのだが。
ちょっと休憩が多かったのかも知れない。でも少女には無茶をさせたくは無い。そして野宿は出来るだけ避けたい。
いろいろな考えがぐるぐると頭の中を駆け巡ったが、もうすぐ辿り着けるはず。そう思い、この夜の街道をゆっくりと進んでいた。
そうして幾ばくかの時間が過ぎ、ようやく街の明かりが二人の目の前に見えた。



見てごらん、もうすぐ街に着くよ


顔を少女の方に向けて軽く微笑むと少女の手を取り、少し駆け足気味になった。



見えてるんだから、そんなに急がなくても…


少女はというと、あくまで自分のペースでゆっくりと進みたいような印象だ。
はっとした顔で身体を少女の方に向き直ると、少年は少女の身体のあちこちを確認し始める。
やはり…
少女にとって長い時間だったのか、足の裏に肉刺が出来ていた。
少し無理をさせすぎたと思い、少年はすまなさそうな顔を少女に向けた。



もう…そんな顔しないで


少女は少年の頬に軽く口づけすると、微笑みながらこう言った。



それなら、街までおんぶしていってよね


あれから30分ほど少女を背中におぶったまま歩いた。
街の明かりがだんだんと大きくなり、そして無事に街の入り口に着く。
街の中に入ってからも少女は背中から降りようとはせず、また少年もそうさせようとはしなかった。
疲れていたのか少女は寝ぼけ眼になっており、その焦点の定まっていない瞳で少年の方を向いた。



お腹…空いちゃった





ああ、僕もだよ


ゆっくりと歩きながら、街の中で宿屋の看板を探す。
その中にこじんまりとした趣の宿を見つけ、その入り口に立つ。



ここに入ってみようか?





うん、賛成よ。


中の様子はというと、調度品は少々古めかしいがきちんと手入れされていることが分かる。
カウンターに居る女性が二人を見つけると、気さくな感じで声を掛けてきた。



もしかして、宿泊希望かな?


少年はおぶっていた少女を丁寧に床の上に立たせると、被っていた帽子を脱ぐ。



はい、こちらでは部屋は空いてますか?





ええ。いっぱい空いてるわよ、空きすぎて困るくらいに。


女性はにこやかに微笑むと、二人をカウンターに手招きした。



あなたたち二人でいいのよね?


宿泊者名簿に日付と担当である女性が名前を書いている。



あなたたち、お名前は?





僕はライムです、こっちの女の子はミオです。


ライムは少女の名前を女性に教える。女性がミオのほうをちらりと見ると、ミオはにこやかな顔で軽く会釈をした。



ありがと。で、何日くらいこちらに滞在の予定かな?


さらさらと名簿に羽ペンを走らせながら、女性は質問する。



まだ決めてはいないんですけど、1週間くらいはこちらでお世話になりたいと思っています


ライムはミオの方を見ながら、答えた。



はい、心得ました。部屋の方は別々?それとも相部屋?


女性は少しイヤらしい視線を向けながら、ライムに質問する。



…相部屋でお願いします


ライムは恥ずかしそうに下を向いた。ミオの方はというと然も当然といった表情だ。
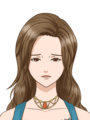


いやねぇ、別に冗談じゃない。別々に泊まるとお金掛かっちゃうもんね、分かってるわよ。


女性はすこし困ったような表情で苦笑いして、ライムにそう言った。
ほっとした表情で顔を上げると女性の方を向き、ライムは話しかけた。



すみませんが、どこかで食事を取れる場所ありませんか?僕達お腹が減っていて…


よく見ると疲れきった表情をしている事に気がついた女性は、奥の部屋を指差した。



うちは酒場もやっているから、そこで食べていくといいわよ。この奥にあるから。


女性に案内をされ奥の部屋に進むと、20人も入ったらいっぱいになってしまうようなホールだった。
ホールでは6人の男が、エールを飲みながらつまみを口に運んでいる。
男達はよく見ると旅人のようだった。
二人は、彼らの脇を抜けてカウンターの席に向かった。



ようこそ、ご注文は?


二人がカウンターの席に着くと、酒場のマスターが注文を聞いてきた。
歳の頃は30後半程度に見える。精悍な顔つきだが、人の良さがにじみ出ているような印象を持っていた。



暖かいスープとかパンがあれば、それでお願いしたいんですけど。


やっと食事にありつけると思ったからか、途端に疲れが襲ってきた。
マスターも二人の表情や動きでそのことを感じたのか、すぐ脇にある大きな鍋からスープを木の器に注ぎ、戸棚の奥から黒パンを取り出した。



スープもちょうどいい感じに温かいから疲れも取れる。この黒糖のパンは甘いから疲労の回復にもいい。


たっぷりの野菜が煮込まれている温かなスープと甘い香りが漂ってきている黒糖で出来ているパンが二人の目の前に用意された時、ミオのお腹が可愛い音で鳴った。
ミオは少し恥ずかしそうな顔をしたが、すぐに気を取り直し手を合わせた。それを見て、ライムもまた手を合わせる。
二人は食べることが出来る喜びを神に感謝すると、スープを一口啜った。



あ、美味しい…





あ、美味しい…


二人が同時に声を上げると、マスターはうれしそうな顔をした。



そうだろう、ココの看板メニューだからな、旨くて当然だ。まだまだあるから、足りなかったらいいな


二人は空腹であり更にスープの美味しさも手伝って、あっという間にスープを飲み干した。
疲れていて動くことが億劫ではいたが、食べている間は幸せでいっぱいになり、疲れなど吹き飛んでいた
ライトは食べ終わると、ミオの食べている様子を笑顔で眺めていた。ミオは食べるのが遅く、いつもライトが最後まで食べるのを助けていた。



お代の方は、宿の支払いと一緒でいいからさ


マスターは二人に向かってそういうと、先ほどの男達の方に歩いていった。



どうする、まだ何かいるかい?


男たちは既に半分くらいの数は酔っ払っているようで、ろれつも回っていないようだ。



いや、もうそろそろ休むことにするよ。


背の高く体格も良い革鎧の男が、そういうと他の仲間達に声を掛けた。



さあ、明日もあることだし、もう寝るぞ


男たちはふらふらと立ち上がると、ゆらゆらと揺れながら出口に向かう。



それじゃ、お二人さんもお休み。


男はライムとミオにも声を掛けると、仲間たちを支えながらホールから出ていった。
