夏の終わりといっても、まだまだ秋にはほど遠い、八月の終わり。
それは空から突如現れ、計っていたかのように僕の頭上に舞い降りた。
本当に軽いものなのに、なぜだか僕はそれに気がつき、何だろうと左手でそれをつまんだ。
薄いそれを見て、僕は君を思い出した。そして、ぎょっとした。嘘だろうと言いたかった。
僕は君を思い出した。
夏の終わりといっても、まだまだ秋にはほど遠い、八月の終わり。
それは空から突如現れ、計っていたかのように僕の頭上に舞い降りた。
本当に軽いものなのに、なぜだか僕はそれに気がつき、何だろうと左手でそれをつまんだ。
薄いそれを見て、僕は君を思い出した。そして、ぎょっとした。嘘だろうと言いたかった。
僕は君を思い出した。



忘れるのは常だよ


と、君は白い顔をして笑った。化粧をしたのかな、と思うような白い肌は、しかし、当たり前だが君の肌そのものだった。
僕は、君と肌の話がしたかった。白いね、綺麗だね、美しいよ。
もともと、君の肌は白かった。出会った頃から。僕はそれが綺麗だと思っていた。
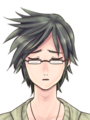


どうしてそれを、早く伝えておかなかったのだろう


僕は、何度目かの後悔をする。今、肌が綺麗だなんて言ったら、君は別の意味でとらえるだろう。
そうじゃない、君は前から、なんて僕は言えるはずもなかった。



……忘れるのは、常


繰り返すだけ。僕は、それ以上君への言葉が見つけられずに、ただ来るであろう時間を恐れていた。
細い、細すぎる手を取ると、君はいつでも、僕の健康すぎる指に、そっと指をからめてきた。
僕は、その弱々しい動作がとても好きで、同時に、とても辛かった。
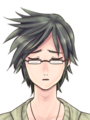


愛している


すがるように言った。



私もよ


君の方が、僕の何倍も強かった。ふふ、と君は僕の頭を撫でる。僕はまた、知らない間に泣いていた。
出会いのその瞬間を、僕は覚えていない。
気がついたら君は、僕の名字を呼んでいたし、僕も君のことを名字にさん付けで呼んでいた。それから、二ヶ月ぐらいで、僕は君のことを名前で呼びたいと思うようになった。できれば、相手も名前で呼んでくれたら。
結局その夢は叶わなかった。君は最後まで僕のことを名字で呼んでいた。
でも、呼び方なんて関係ないのだ。いとおしさが加わると、同じ呼び方でも、天と地ほどの差がある。
出会って半年で、僕らは結ばれた。あのときの、天にものぼるような気持ち。
出会いのことは、本当に覚えていない。気がついたら、君はいた。
しかし、別れのカウントダウンが唐突に始まった日は、鮮明に記憶している。



だめみたいなんだよね


君は、すべてを受け止めていたのだろう。
おかしいことぐらい、僕も気がついていた。食欲がなくなってきたこと、細くなっていくこと、眠る時間が多くなったこと、外に出る時間が減ったこと、病院に何度も通うようになったこと。
病気だということも知っていたけれど、でも、まさか、もうすぐ終わってしまうだなんて、そんなことを唐突に言われて、誰がやっぱり、と思うだろう。
いつだってその可能性のことだけは、頭の奥の奥の方においやって、鍵をかけて、無いものにしていたのに。
その鍵を、君はいとも簡単にひょいとあけてしまったのだ。



だめって……





つまり、もう長くないってこと


だめ、の意味がわからないわけではなかった。つまりなんてことばを期待していたわけではない。
そうじゃない。でも、それしかないのか。
うん、と返事をしたんだっけ。僕は、どうしたんだっけ。
記憶はおぼろげで、できれば、忘れてしまいたいけれど、あのときの衝撃は、ことばにできないまま、僕の心の奥の方に沈んでいる。
最期が近いと言われたその日から、僕は君の傍にできるだけいることにしようと、密かに決心していた。
しかし、君はそういった僕の献身ぶりを嫌がった。



特別扱いは嫌だ


と言っていた。たまに会いに来てくれるぐらいがいいと言ったのは、多分強がりだったのだろう。そう思う。僕がそばにいるとき、君はたしかに楽しそうだった。
そもそも、もうすぐいなくなってしまう人に、特別扱いをしない方が無理だ。
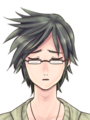


ただ君と一緒にいたいだけだ


と言うと、君は困ったように眉を下げて笑った。



仕方のない人


という言い方は、どこか古めかしくて、僕もつられて笑ってしまった。
君と笑いあう時間は特別だった。でも、辛いこともあった。その日、家に帰って、全ての会話を思い出したいと思っても、それは無理だと知ったことだ。
ノートにできる限り書き綴ってはいたが、明らかにその量は、今日の君と過ごした時間よりも少ないのだ。
あっというまに、手が止まってしまう。君のことばの隅々を、覚えていない。
僕は、僕の脳みそを呪った。
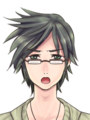


なんて使えない


と頭を殴ったりもした。もっと働け、もっと働け、君を忘れないために。
君は強くて、僕は弱かった。もしかしたら、君は僕に弱さを見せなかっただけかもしれないが、僕は君に弱さを見せていた。見せ続けていた。最後まで、僕は君に甘えっきりだった。
僕は毎晩、暗闇の中で恐れていた。君を失うことも怖かったけれど、君を忘れてしまうことも同じように怖かった。
今思えば、どうしてそのことを君に打ち明けたりしたのだろうか。僕が弱かったから、ですまされるような行動では無い気がする。
しかし、優しい君は、そのときに、馬鹿ねえと細い声で言った。
忘れるのは、常だと言ったのだ。



忘れないと生きていけないの。忘れていいの。
ずっとずっと、覚えている方が無理よ。
頭、おかしくなっちゃうよ。
私だって、天国で少しずつ、あなたのことを忘れていくわ


天国!
やめてくれと、僕は君にすがりついた。君からそんな言葉を訊くのが嫌だった。もうすっかり、何もかもを受け入れている君の強さが怖かった。何もかもが怖い僕がいやだった。
君の細い腰を抱きしめた。



赤ん坊ね


彼女が頭を撫でる。僕は、静かに泣いた。
弱さを見せてくれとも言えない僕は、もしかしたら、君の悲しみの代弁者になっていたのかもしれない。
そう思うのは、少しおこがましいだろうか。
冬のある日、寒い、寒い日。君は雪より白くなって天国へ行ってしまった。
君は、僕に手紙とプレゼントを残していた。プレゼントは、腕時計だった。
生きることへの暗示だということは、すぐに分かった。いつ書いたのだろう、君がくれた長い長い手紙の中で、君はずっと、僕のことを心配していた。



忘れていいの。でも、全ては忘れないで。少しだけ覚えていてね


この言葉が、僕をどれだけ苦しめたか。
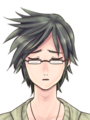


忘れないから


僕は、常に左腕に腕時計をつけるようにした。
それを見るたびに君を思い出そうと誓ったのだ。君は望まないかもしれないが、それでも君をできるだけ覚えていようとした。
ノートに、君との思い出を書きつづった。時間のある限り、君を思い出した。
くるくると、何度その時計の針が回ったか知れない。僕は、生きていた。君のいない世界で、不思議な感覚だったが、生き続けていた。
何度冬が来ただろう。そのたびに寂しくはなるけれど、僕は君を忘れてはいないよと、星に向かって呟やいた。星が瞬くのを、返事だと思って、雪の中一人微笑んだりもした。
僕には自信があったのに。
夏の終わりまで、それは奇跡的に木の枝にでも引っ掛かっていたのだろう。
しぼんでいたが、微かにピンクの色を残した、その花びらをつまむその指先は震えていた。



あ……


桜の花。桜花。それは君の名だ。この花弁は君か。僕は緑色の木を見上げた。
花びらを取って、それを見たときに、僕は君を思い出した。
君がくれた時計を、つけ忘れていることに気がついたのだ。脳みそで記憶の連鎖が起こり、僕はすぐに君を思い出した。
そしてぎょっとしたのだ。
僕は君を忘れていた。
君のくれた時計を忘れて、君のことを忘れて、ふらふらと歩いて、僕はどこへ行こうとしていたのだろう。
舞い降りたそれは、おそらく君だと思った。君は、微笑んでいたはずだ。
ほら、忘れている、とでも言いたげな花びらを、僕はそっと手放す。それは、風に乗って、ふわふわと飛んで行った。
僕は雲ひとつない空を見上げた。
空は、あまりにも高く遠かった。
君への言葉を、探していた。
了

私の中にある、この思い出も、絶対忘れるわけが無いと思っているこの想いも、何時か忘れていくのかな……と。少し、さびしいというか、不安になってしまいました(^。^;)
忘れるのは、常。だからこそ前を向いて歩いて行けるのだろうとわかってはいても、その行動、現象を嫌悪してしまう。
奈魅優利様>コメントありがとうございます! 短編も読んでいただけて本当に嬉しいです!! わすれたくないことも忘れてしまうのって、寂しいなあと私も思います。恐怖でもありますよね。現象を嫌悪、確かになあと思いました。
大人ですよ! 子どもだったら考えもしないことかもしれません、子どもは忘れることを知らないのかも、と考えます、吸収ばかりで。ふと立ち止まって、忘れてる、と感じるのが大人だとしたら、大人になるって寂しいものです……