エルムはいつも、丘の上に生えているニレの木に話しかけている。
エルムはいつも、丘の上に生えているニレの木に話しかけている。



ニレさん。きょうはね、学校のお友達とあそんだの





でね、こんな首飾りもらっちゃった。貝で作ったんだって。きれいでしょう?


エルムは自慢気に、手に持った首飾りをニレの木に見せた。
あ、いけない、と少女は呟いた。はやく帰らなきゃ、ママにしかられちゃう。



またね、ニレさん


エルムは駆けて行った。
ニレの木は、少女の声が遠ざかるのを聞いた。
目がほしい、とそのニレの木は思った。
あの少女の首飾りを見たい。
すると突然、森の精霊が囁いた。



ピンニ


さわさわとニレの木の葉が揺れた。



目がほしいのかい


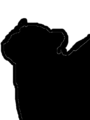


はい。……いえ


ピンニは、ためらいがちに言った。
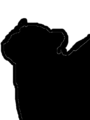


少しだけ、あの子の……、エルムの、首飾りが見たくって。少しだけ





そうか


森の精霊は頷いたようだった。
ピンニのまわりの空気が、ふわ、と動いた。
あ、とピンニは思った。怒ったのだろうか、と心配になったのだ。
話しかけようとしたが、すでに森の精霊はいなくなっていた。
翌朝、まだ朝日の昇りきっていないころ、ピンニは目を覚ました。
見える。目が、あるのか。
ピンニは驚いた。世界があまりに眩しかったから。
馴れるまでに時間がかかった。
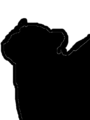


ティピ


ピンニは森の精霊の名を呼んだ。
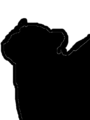


ありがとう


さわ、と柔らかい風が吹いた。
目に見えるものと、いままで手(枝)で感じていたものとが一致するのに少し時間はかかったが、ピンニはすぐ覚えた。そしてあの少女、エルムだとわかった。声が聞こえてきたから。少女はかけあしでピンニのそばまで来ると、昨日の首飾りらしいものを首にかけ、嬉しそうにピンニに見せた。



どう、にあってる?


似合ってるよ、とピンニは思う。葉がさざめく。
エルムは、にい、と笑った。



ありがとう!


それだけいうと、もと来た道を軽快な足取りで歩いて、ついには走りだした。
エルムのにおい、手(枝)触り、風の動き方、どれをとってもエルムだ。まちがいない。
ピンニにはわかる。あの可愛らしい声、おてんばで活発な動き、まあるい目をしてこちらを見る。あの少女だ。いつも話しかけてくれている、あのエルムを、見ることができたんだ。
最初は首飾りさえ見られれば、とピンニは思っていた。エルムの姿が、聞いていた声のとおり、元気で明るい子だったから、ピンニは感動していた。
(ただ、少し大人びたかな)
夜更けになり、興奮で眠れずにいると精霊が話しかけてきた。



そりゃそうさ。人間の成長は早い。そして寿命は短い


(そう。だからエルムも)
これ以上考えるのはよそう。思って、ピンニは目を閉じた。
あれから何ヶ月、何年、いくつもの季節が巡って、何度目かの春。
あの少女が来ない。もう、ずっと来ていない。
しかし、ほかの人間はいくらか来た。
恋人たちが木陰で一休みしたり、初老の男性が読書をしたり、家族がピクニックに来て、ここでお弁当を広げたりしていた。
いつも人々がピンニのまわりにいて、ピンニは彼らをぼんやり眺めていた。
来る日も来る日も、彼らを見て過ごした。入れ替わり立ち代り、いろんな人が来て、そして去っていった。
夜。
うとうとしていると、人声が聞こえた。
(エルムだ。会いに来てくれたんだ)
ピンニはエルムのにおいですぐにわかった。
(真夜中、こんな暗い中を、どうしたのだろう)



ニレさん……


様子がおかしい。あの、いつも元気だったエルムが。
エルムは太いロープを、ピンニの腕(枝)に括りつけた。
そばにあった台をロープの真下に置き、エルムはそこにのぼる。
(ぼくとずっと一緒にいたいのかな。エルムはニレの木になりたいのかな)
次の瞬間、ぐっ、と枝に重さを感じた。見ると、そこにエルムがぶら下がっている。
(エルムが……。嬉しい……)
エルムの顔に浮かんだ表情の意味はわからなかった。
一瞬、ピンニの体重が少し軽くなった気がした。
だがピンニは眠くてしかたないので、ふたたび眠りに落ちた。
翌朝、エルムは紫色になっていた。
(ぶどう、みたいだ)
ピンニはそう思った。
森の精霊が、ピンニのそばでささやいた。



エルムはそこにはいない


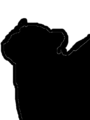


そんなバカな。だってここに


それは、かつてエルムだったものだ、と森の精霊は言った。



彼女自身は、山の神様のもとへ行ったのだよ


それがどういうことかわからず、ピンニは森の精霊に訊ねようとした。
が、すでにいなくなっていた。
(もしかして、ぼくの目は)
ピンニはその夜、考え事をしていた。
(ぼくが目を授かったのは、あの少女の、エルムの命と、引き換えに)
そこまで考えて、やめた。
そうである証拠など、ない。
ただなんとなく、そう感じた。
それだけだ。ピンニはまた、眠りについた。
深い、深い眠りだった。
何十年かの年月が流れた。
夏、真っ盛り。夕方。
さっきまで鳴いていたセミたちが、ぴた、と鳴きやんだ。
鳥たちも、どこか騒がしい。



なんだか雲行きが怪しい


ピンニの足もと(根もと)にいたおじいさんが、空を見上げた。



こりゃあ、一雨くるぞ


そう言っておじいさんは、去っていった。
遠くのほうで、雷鳴が轟いた。
ごろごろごろ、という音が、もう一度、鳴った。
近い。
ピンニは空を見上げた。
ピカ、と光が一閃した。
と同時に、ものすごい衝撃が、ピンニを襲った。



落雷したんだよ、君に


(ぼくは、どうなったの)



君はまあ、無残にも、まっぷたつさ


(無残ってなに)



ひどい、ってこと


(ひどい、って)



まあいい。とにかく、君をつれてくるようにと、言われているんだ


(山の神のもとへ)



そう


(ティピ。前から思ってたんだけど)



なに


(君は、いいやつなのか悪いやつなのか、わからない)
ざ……、と、ピンニの周囲にある木々が、ざわめいた。



ピンニは、そんなこと考えるひと(木)だったかな


ティピは少し、笑っているようだ、とピンニは感じた。



ピンニは少しずつ、エルムと会ったころから、変わったようだ


(どうういうこと)



ぼくは森の精霊。いいやつでも悪いやつでもない。精霊。それだけ


じゃ、行くよ。
雷が落ちた木にはその後、誰もよりつかなくなった。
人々の憩いの場であったことも、忘れられていった。
(了)
