脳内に鳴り響く、目覚まし代わりのToDoリストに、布団の中で再び首を傾げる。



忘れずに、おやつのパンを注文すること。
忘れずに、バターケーキを予約すること。
忘れずに、店の場所を検索して地図登録すること。
忘れずに、絵はがきを探すこと。





……あれ?


脳内に鳴り響く、目覚まし代わりのToDoリストに、布団の中で再び首を傾げる。



また、『絵はがき』?


自分がリストに載せたものではないことを確かめて、昨日削除したはずなのに。



なんで?


もう一度首を傾げながら、小さな部屋のベッドから身体を引き剥がす。
『絵はがき』について、昨日仕事が終わってから『システム』を利用して調べたことを思い出し、尤理は強く首を横に振った。
厚手の紙に、写真や絵を印刷、あるいは手書きで絵を入れた、『はがき』と呼ばれるものの一つ。『大災害』の前、まだ郵便制度とwebメールが並立していた頃には意外とたくさん流通していたもの。しかし郵便制度が無くなった今では、昔のものを展示している博物館でしか見なくなってしまったもの。



どうしてToDoリストに、そんなものが?


首を傾げて唸りながら、昨日と同じパンを注文する。
その時、目の前に見えた白いものに、尤理は目を瞬かせた。
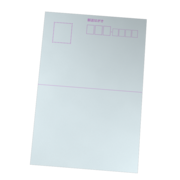
薄暗い部屋の、簡素な机の上にあったのは、ぼうっと光っているようにも見える、白い紙。尤理の小さな手では持て余してしまう、少しざらざらした手触りの紙の裏面に描かれていた『絵』に、尤理ははっと胸を突かれた。



この、絵、どこかで。


その時。



……あの、すみません。





え?


不意に響いた、高い声に、背中がびくっと震える。
何とか心を落ち着かせ、扉の方を振り向くと、小柄な少女が尤理の方を見つめているのが見えた。尤理と同じ制服を着ているから、彼女も『管理者』。不審な人物ではない。尤理はほっと息を吐いた。
だが。



……。





……どこかで、見た、覚えが、ある、気がする。


少女の方をもう一度、今度はしっかりと見据え、尤理は再び首を傾げた。



あ、その、絵はがき。


尤理が思考する間に、少女が尤理の側まで来る。
この絵はがきを、少女は探していた。それを理解する前に、尤理は少女に手の中の紙を差し出した。



探してたの。
ありがとう。


『絵はがき』を受け取り、嬉しそうに微笑んだ少女の影が、不意に尤理の目の前から消える。



えっ……?


再び頭の中を回り始めたToDoリストに気付くまでの数分間、尤理は呆然と、開いたままの扉を見つめ続けていた。
宿舎で借りた自走車で、三十分ほど山道を走る。



……懐かしい。


ようやく見えてきた懐かしい風景に、尤理は目を細めた。
人が住むことを許された区域の端を守る『限界管理者』。『大災害』によってがらりと変わってしまった場所に人々が足を踏み入れないよう監視しながら生きることが、尤理を育ててくれた母方の祖父母の職務。
祖父も祖母も、その職務を楽しんでいるのだろう。こぢんまりとした赤い屋根の家の周りに広がる野菜畑の広さに肩を竦めてから、尤理は砂利の部分に自走車を止めた。



尤理っ!
おみやげっ! フライケーキ!


自走車に素早く気付いた、祖父母の家に居候している中等部所属の従妹、順が赤い屋根から走り出てくる。
まだ育つ前なのか、それとも祖父母の血を濃く受け継いでいるのか、尤理の肩の高さしかない小柄な影にまだ温かい紙包みを渡すと、尤理は保冷剤を入れた銀色の鞄とともに自走車から降りた。



おみやげっ! フライケーキ!





じいちゃんとばあちゃんは?


できたてのフライケーキを頬張る順に、とりあえず尋ねる。



あ、ふ、じゃ、馬鈴薯掘ってる。


尤理が肉を買って来るから、久し振りに肉じゃがを作るんだって。熱いフライケーキと格闘しながらの順の言葉で、肉と馬鈴薯を醤油で煮ただけの美味しさを思い出す。



フライケーキも良いけど、荷物、お願いね。





え、あ、うん。


自走車内の米を家に運ぶよう順に言い置いてから、尤理は赤い屋根へと向かった。
誰も居ない台所の冷蔵庫に肉とバターケーキを突っ込み、屋根裏部屋へと上がる。
斜めになった天井と、尤理の肩の高さの本棚の上に立てかけられた油絵が目に入り、尤理はそっと目を細めた。



……。


『大災害』前に描かれた、海沿いの町。海際から山の中腹まで覆い尽くしたあらゆる色の屋根と、淡い夕日に輝く水面を描いた絵。あの、尤理の部屋に突然現れた絵はがきの絵と、同じ構図。
そして。



……あった。


本棚のアルバムを抜いてページをめくると、尤理の許に絵はがきを探しに来た少女と同じ姿を見せる写真と、その少女に渡した水彩画の絵はがきが、確かに、あった。
この家の先にある山の向こうには、かつて、軍港として栄えた小さな町があったらしい。その町のかつての光景を写し取った油絵が何故尤理の祖父母の家にあるのかは、分からない。
だが、その絵を気に入っていた祖母の兄が絵はがきサイズの紙に水彩でその絵を模写し、同じようにその絵を気に入っていた、『管理者』となっていた祖母に送ったことは、尤理も知っている。祖父母に預けられていた小さい頃、この部屋でこの絵はがきを見つけて『欲しい』とだだをこねたときに祖父が話してくれた逸話を、尤理はシステムの助け無しにまざまざと思い出していた。



……。


祖父母が戻ってきたのだろう、下の階が急に賑やかになる。
肉じゃがを煮る、醤油の甘い香りが漂うまで、尤理はアルバムの中の色あせた絵はがきに見入っていた。
