夜空の下を駆け続けて、立花研究所に着いた私の呼吸は過呼吸一歩手前。




はぁ……はぁ……はぁっ……。


夜空の下を駆け続けて、立花研究所に着いた私の呼吸は過呼吸一歩手前。
こんな時間にも関わらず、立花研究所の明かりは灯ったままだった。
これがいわゆるブラック企業か。
そんな、どうでもいいことを考えてしまった。
私の楽観的な悪い癖だ。
しばらくショッキングなことが多すぎて、発揮されていなかったけれど、元来私はそういう人間だったはずだ。
そして、今回の場合もそれはいかんなく発揮されていて、というのもここに来た目的ははっきりしていても、その手段というのは完全にノープランだ。
しかし、直感があった。
きっとあの少年はここにいる。
ここのどこかにいる。



とりあえず、蓼科先生に――。


走り続けた足と、血液を循環させ続けた心臓を休ませながら、私は独り言ちる。
ここの研究室に私がコンタクトを取れる可能性があるのはあのだらしのない研究者しかいない。
しかし、その蓼科だって信用ができるとは限らない。
私を「処分」すると言った、あの者たちは彼を敵視しているような口ぶりだったけれど、かといって、あの少年を助ける、という立場をとるかどうかは不確定だ。
敵の敵は味方、なんていう理屈が通らないことはもう分かっていることだ。
それは先刻、私があの少年を「裏切る」という形で証明してしまったようなものだ。
あの少年は、おそらく、泪を始めとする《自由七科》の殺害に、なんらかの形で関係していることはもう疑いようがない。
それが、加害者としてなのか、
はたまた被害者としてなのか。
それは分からないけれど。
もう、無関係ということは言えないだろう。
そういう意味ではこれ以上首をつっこめば、私にも危害が及ぶということもまた確実になってくる。
けれど、だからといって。
“首を突っ込まなければ”安全だということでもあるまい。
もう状況は開始され、進行してしまっている。
もう、無関係ではいられない。
その発端があの少年を助けたことなのか。
あの少年に出会ってしまったことなのか。
あの実験に参加すると決めたことなのか。
そんな運命論みたいなことを言ったって仕方がない。
それであれば、動こうと動くまいと無関係ではいられないのであれば、私は私の心に従いたい。
あの少年の味方でいたい。
あの少年の敵の敵でなく、味方に。
正義の味方じゃなくてもいい。
私には正義なんてものは重すぎるし、眩しすぎる。
だから、私は正義に生きるわけではなくて。
自分の心に、正直に生きるだけだ。
研究室の中は、明かりさえあれど、やはりいつだって薄暗いし、肌寒い。
その暗さと寒さは私のきりきりと張り詰めた心のピアノ線をさらに強く張り詰めさせる。
張りすぎたピアノ線は、調律など無視して、あげくの果てに切れてしまう。
記憶の混乱は《ロジカ》の能力によって修復されたとはいえ、その能力行使の負荷か、あるいは復帰の後遺症か、身体の調子も悪い気がする。



はぁ……はぁ……。


いや、これは、本格的にまずい。
気のせいとか、思い込みとかでなく、身体が不調をきたしている。
足がもつれ、目が霞み、手がしびれ、耳鳴りが襲う。
蓼科先生を――
見つ、け――――――
な――――――――――――
い、――――――――――――
と――――。
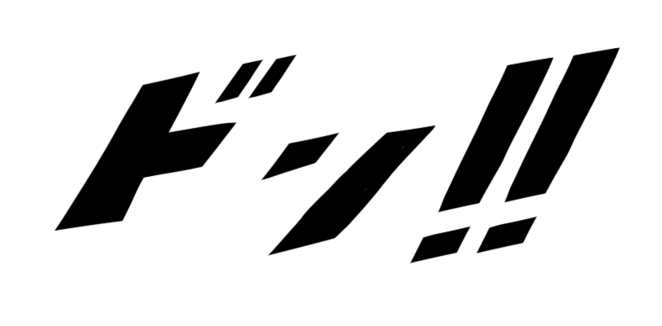



大丈夫かい、瞳ちゃん?



目覚めると、そこはいつか訪れた待合室。
そして、声の主は、幸いなことに、先刻まで私が探していた人物であった。



蓼科……先生……。





お目覚めみたいだね?





私……一体何を――?





どちらかというとそれは僕の方が聞きたいんだけどね?
こんな真夜中に女の子一人が出歩く先としてはこの研究所はいささか役不足ではないかい?





それは、その――。





それに、なぜか廊下の真ん中で倒れてるしね?





う……。


普通にこの状況を推察するに、体調不良で倒れた私をたまたま蓼科先生が発見し、ここで看病をしてくれた――ということなのだろう。
廊下で倒れている自分を客観的に想像してみると些か滑稽で、それを目の前のずぼらな研究者に見られたと思うと恥ずかしさが込み上げてきた。



それで?
結局なんの用だったんだい?
瞳ちゃんがここに来るってことは何かしら僕に用があったんだろう?





あ、はい、そうなんです。
その、例の吸血鬼の事件のことについて――


と、話し始めた刹那――。

耳障りな音ともに窓ガラスに穴が空く。



きゃ!!


思わず悲鳴を上げる。
だが、私はもっと目を疑うような光景を目の当たりにすることになった。




ぐ、ぐぅ……!!!!


目の前の研究者の肩口を銃弾が貫いていたのだった。
