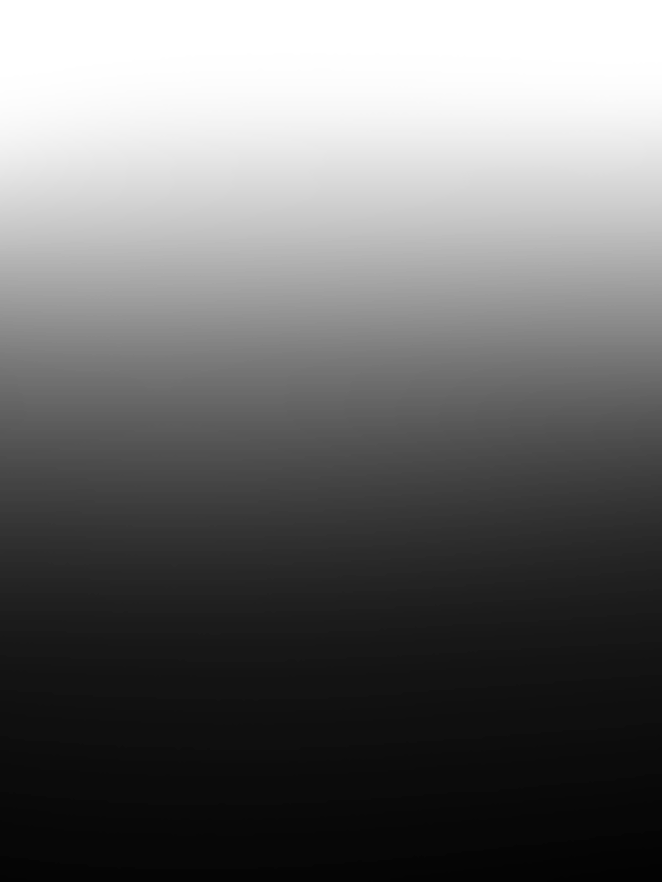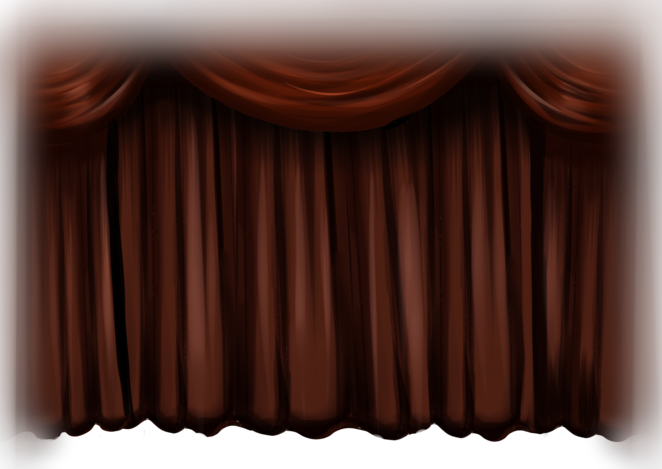早く、早く!
また彼が誰かに買われちゃうかもしれない……!

早く、早く!
また彼が誰かに買われちゃうかもしれない……!
底なし沼のような不安感と焦燥感で、心が闇に引きずり込まれそうになる。もがけばもがくほどはまっていくものだから、堂々巡りの思考に白旗を上げた。
鈍臭い足を必死に動かし、恥ずかしげもなくぜぇぜぇと荒い息遣いで走る。
途中、日傘をさしたマダムにぶつかったり、辻馬車にひかれそうになってどやされたり、敷石に躓いてこけたりしたが、そんな些細な受難は痛くも痒くもなかった。
1時間弱でようやくパサージュ・ショワソルが姿を現した。
朝にここへ来たのは初めてだが、夕方のおどろおどろしい雰囲気と真逆で、人類未踏の聖地のように静謐な雰囲気が漂っていた。
足をもつれさせ、奥歯を噛み締めながら踏みとどまる。見慣れた【Antiquaire(骨董屋)】という看板が見えて安堵したのも束の間、扉の前で中肉中背の男性が張り紙を貼ろうとしているところで、その張り紙の文字を見て唖然とした。
そこには、
FERME(閉店)
と殴り書きされている。
焦り九割悲嘆一割の口調で口火を切った。



あ、あの!
閉店、されるのですか!


おそらく店主だろう男性は、白髪だらけの頭を撫でながらわたしを見つめる。しかし、目を細めてこちらを確認すると、



おや?
そうだが……マドモアゼル、そんな血相を変えてどうされたんですかな?


と言いながらこちらへきちんと焦点を合わせ、「ああ!」と少し声を弾ませた。



これはもしや――よくショーウィンドウからドールを見てくれてたマドモアゼルでは?





な、なぜお分かりに……?





ちょうど窓から死角になる机から様子を伺っていたのですよ。
あんなにも熱のこもった視線でドールを見られるのはマドモアゼルくらいだったので。


全部、見られていたんだ。虚をつかれ、何度も瞬きをしているとどんどん顔が熱くなる感覚を覚えた。



――で、用件は何ですかな?





あ、そのドールのことでして


ちらりとショーウィンドウを見ると、そこにドールはいなかった。もしかして、また売れてしまったのかもしれないと焦燥感をあらわにしていると、店主はさもおかしげに唇に弧を描いた。



マドモアゼル、お気に召しているところ申し訳ないが、あのドールは持ち主を点々と変わるドールでね……。
1ヶ月も経たないうちに必ずこの骨董屋に戻ってくるんだ。だから、今回閉店するのを機に、戻ってきたあのドールも処分しようと思ってね。もう売り物にならなそうだし――。


処分、という言葉に身も心も凍りついた。
それはいけない、と激しく疼く鼓動がその意志を物語っている。わたしは考える余裕もなく声をあげた。



処分なんてしないでください……!


ガラス屋根にこだまするほどの声が口から出て、自分でも驚いて口を手で覆う。



あ、その……すみません。
お金がない身分でお恥ずかしい……。


こういう時、ドールを買えるだけのお金があればと思ってしまう。エリゼがもらうお小遣いの半分でもあれば、きっとこのドールも買えたのに。やるせない気持ちで肩を落としていると、店主は店の奥へ入っていった。
話にならないから、呆れられたのだろうか?
そうかもしれない。だって、いきなり財力もない人間に処分するなと言われては開いた口が塞がらないことであろう。
痛切に運命の残酷さを感じながら、踵を返したその時であった。



マドモアゼル、どうだね?
どんなことがあってもこのドールを手放さないと約束できるなら、無償で譲ろうではないか。


それはまるで救いの甘言であった。一気に悲嘆の色が霧散し、その言葉の深い意味を考えず頷いてしまった。



い、いいのですか!





ああ、マドモアゼルのような優しい子なら――きっとこのドールも喜ぶだろう


渋ることなく店主はドールの入った箱をこちらへ持ってきた。震える手でそれに触れようとした瞬間、店主は



いいかい


と念押しするようにもう一度言葉をなぞる。



どんなことがあっても、ドールを手放したらいけない。いいね?


今まで欲しいと思ったものを一つも手に入れた経験のない愚かなわたしは、一際強く



はい!


と応答し、長細くて自身の身長とそう変わらない紺色の箱を抱きしめた。
やっと、やっと手に入った……!
嘘みたいだ、と思う。けれども箱を抱きしめるその触感であのドールがこの手にある実感を噛み締めた。



『アベル』?


箱に記してあった名前を口にすると、どうしたものか、まるで口に蜜を含ませたような得体のしれない感覚が心身ともに充満した。
まさかこの巡り合わせがわたしの人生を180度変えてしまうとは、この時これっぽっちも思ってもみなかったのである。
ほくそ笑む店主、店からこちらを覗き見る目、ガラス屋根に叩きつける風、それらの存在はわたしの五感には届かなかったのだ。
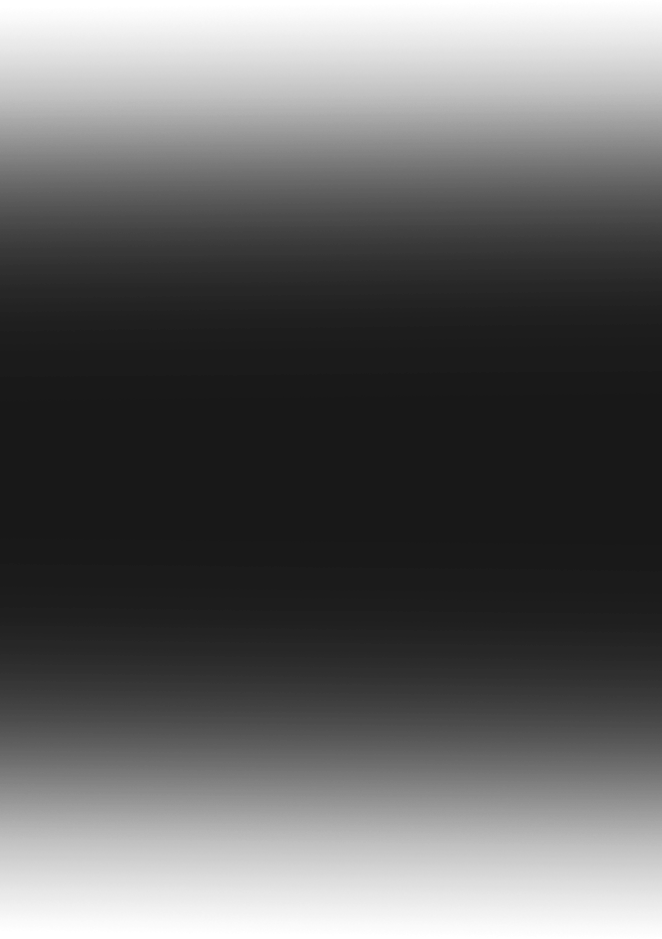
流石に体躯の細い女の子に徒歩で箱を持ち帰らせることはできない、と店主は頑なに首を振りながら、わたしのために辻馬車を提供してくれた。至れり尽くせりで、いくら鈍いわたしでも少し違和感を覚える。



いいのかしら……1フラン60サンチームもあちらがもってもらうなんて


ただの庶民が使うにはもったいない辻馬車に揺らされながら、赤ん坊を抱くように箱を抱きしめつつそう呟いた。
こう考えることすら罪かもしれないけど、上手くいきすぎて怖い。だって、わたしの人生で一度も上手くいったことなんてなくて、それが普通だと思っていたから。こんなことがあっていいはずがない。目当てのドールが一銭も出さず手に入り、帰りも額に汗することなく自宅へ送ってもらえるなんて、冷静に考えると一気に幸運が舞い降りすぎというものだ。
その予感が的中してしまうことになるとは。
やっと自宅のアパルトマンに到着し、馬車から降りて御者さんと馬2頭に恭しくお礼を言っていると、

アパルトマンの5階の窓が勢いよく開く。そこには、なんとエリゼがいたのだ。