第二話
第二話
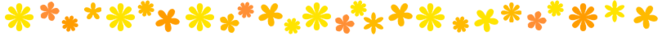
横浜広しと言えども、しょこらあと、つまりチョコレートを第一の売り物に掲げる店は長崎屋しかない。
チョコレートといえば、カカオ豆を挽いて湯に煮出したほろ苦い飲み物である。

遠くヨーロッパにて、その昔健康に良い飲み物としてコーヒーとチョコレートが人気を二分したが、
コーヒーがその戦いに勝利し、今ではチョコレートを飲む習慣はほとんど無くなったらしい。
だから日本には、コーヒーだけが文明開化の飲み物として伝来している。
「しょこらあと」は、明治の世より少し前、江戸時代は長崎の出島に伝わった。
飲むと肌艶が良くなり、官能が刺激される媚薬として、遊女の間で珍重されたという。



あたしは遊女の出でね


女将は細長いきせるをふかし、ゆるりと紫煙を吐いた。



「珈琲」より 「しょこらあと」のほうが好きだったから、この店を開いたのさ。
「珈琲」は、パっと明るく頭が冴えるような気がするが、
「しょこらあと」はもっと深く、ゆるく、暗いチカラが沸いてくる





……





こんな店にやってくるなんて、野次馬かよっぽどの好事家だ。
たいていは一見さんでオサラバだが、あんたは足しげく通ってきた。
何かあるなとは思っていたが、マリルーが狙いとはね





狙いだなんて、そんな


身を乗り出した菊次郎は、自分が籐の椅子に縛り上げられていることを思い出した。
見下ろせば、奇妙にきれいな亀甲縛り。
菊次郎は当惑の表情を浮かべて辺りを見回した。
隣にいるのは、黒いざんぎり髪の男だ。
日本刀を手にしているが、その風貌は武士ではなく渡世人のソレだった。
彼は菊次郎の視線に気づくと、



あぁん?


低く唸ってカチャリと刀の鍔を鳴らした。



……ひっ





あまり脅かしてやるな、朱天


長崎屋の女将の隣で、場違いに楽し気な微笑みを浮かべながら菊次郎を見つめているのは銀髪の男だ。
マリルーと同じ異人のようだが、着くずしたような和服をまとっている。
銀髪と黒髪は長崎屋の常連で、菊次郎もしょっちゅう目にしてきた。
昼間は不思議なほど現れないが、
夜はここに住んでいるのかと思うくらい四六時中、店に入り浸っている男たちだ。



俺はこのお兄さんの言い分をぜひ聞きたいな。
通いはじめは、去年の霜月くらいだったろう


銀髪が言い、黒髪が目を丸くした。



よく覚えてるな、エルンスト





うん、とても可愛いなと思ったからね





この衆道





きみの最初の目的は純粋にチョコレートだったように思うのだが?





……ご、ご明察です


面食らいながらも、菊次郎は大きく頷いた。



僕は西洋菓子を研究していまして、特にチョコレートに大変興味がありました。
しかし、なかなかその味を知る機会は無く……そんな折、こちらの店を知りました







……うわ、あっつ、苦っ……


ねっとりとまとわりつくような熱さと苦さに、菊次郎は思わずうめいてカップを戻した。
それが、初めて口にしたチョコレートだった。



うわっ、ストレートで飲んだのか?


口を押えたまま、しばらく顔を上げられずにいた菊次郎の目の前に、トン、と美しい切子のグラスが差し出された。




ほら、水だ! 飲め!


女のくせにひどい言葉使いだなと思ったが、髪の色や肌の色からするとこの娘は異人であるらしい。
どこかで間違って日本語を覚えてしまったのだなと思いつつ、菊次郎はありがたく水を飲んだ。



ふうぅぅぅぅぅ……


美味だった。
いっきに飲み干して顔を上げると、異国の女給が阿修羅のような顔で見下ろしていた。



お前はばかなのか? わたしは砂糖を入れろと何度も言ったはずだ


菊次郎はしゅんとうなだれた。
確かに、しょこらあとを注文した時に、くどいほどこの女給に指示を受けていた。



すみません……コーヒーを何も入れずに飲めるので、チョコレートもいけるだろうと思ったのです





……


はん、と、女給は鼻を鳴らした。



でも違った……。苦さがなんというか別種類で……この苦さはまるで泥沼のようだ……いつまでも後を引く





当たり前だ。しょこらあとは、珈琲よりずっとまずいんだ





ええ、まずいですね!





だがな、こうすると



女給は白磁の砂糖壺から、高級そうな白糖を掬うと、惜しげもなくさらさらとしょこらあとにこぼし入れた。
その匙、実に5杯。



わ、わ、そんなに?


女給は柄に小さな鈴がついたマドラーで、くるくるとしょこらあとを混ぜた。
真っ黒な液体がかすかに泡立ち、鼻孔をくすぐるような甘い匂いが沸き立った。




香りが変わった……





飲んでみろ





えっ……


舌がまださきほどの苦さを覚えていたが、菊次郎はおそるおそる、カップに唇をつけた。



!


その液体を、舌の上で転がし、口腔と鼻腔で堪能する。
感じたことのない甘さ。
苦さと甘さが同時に駆け抜け、紙一重のところで甘みの印象が残る。
その後から、ゆっくりと舌の奥に広がっていく、うま味といっていいコク。
最後に鼻を通り抜けていくのは、刺激的な香り。



この香りを何と表現したらいい? 花か? 果実か? 違う、もっと動物的な……麝香のような……





まるで……高貴な動物の内臓か糞のような……飲んではいけないものを飲んだような……


夢中で言葉をつむいでいく菊次郎をぽかんと見下ろしていた女給は、




プッ



盛大に噴き出した。



糞はひどいな!





あ、すみません、思わず……





いや、かまわん。あながち間違ってもいない





え?





船乗りに聞いたことがある。
チョコレートの原料になっているカカオの実というのは、恐ろしく気持ちの悪いものなんだそうだ


女給は楽し気な足取りで店のカウンターに走っていくと、壁に貼り付けられていた絵を一枚、
鋲から引き抜いてこちらに持ってきた。



ごらん



それは精密に書かれた植物画だった。



人間ほどの背丈の樹で、枝はほとんど無い。
こうやって、幹から直接ぼこぼこと実が垂れ下がっているんだ。
この赤黄色いのが、カカオの実だ


菊次郎はそれをまじまじと見た。
珍妙な絵だった。
普通の植物なら、人や動物の手の届かないところに実を結びそうなものだが、この樹はそうではない。
まるで取ってくれ触ってくれといわんばかりに、
幹の低いところから、
大きな果実をぶら下げているのだ。
まるでその様子は、



女の乳房のようだろう?





えっ


ごく近い距離でそう言われ、菊次郎はカっと耳を赤くした。



カカオの産地には、体中に乳房のある女神がいるそうだ。
わたしはそれを聞いた時、昔の人も考えることは一緒なのだなあと思った


女給は菊次郎の様子なんかおかまいなしに言うと、髪を耳にかけ、うーんと思案した。



なんとなく、この樹って動物のメスっぽいよなあ。
糞とは思わなかったが、動物の何かを飲んでいる感じというのは、言い得て妙だ


女給は、首まで真っ赤にしている菊次郎をひょいと覗き込んだ。



お前、気に入ったぞ





へっ





わたしはマリルーだ。お前は





森永菊次郎です





そうか、これから毎日来ていいぞ、菊次郎!


マリルーはにっこりと笑い、白砂糖スプーン5杯分の追加料金を請求した。
