第五話 来訪者
第五話 来訪者
種村さんと再会してからというもの、急にジルの動きが活発になった。
最近では、起きてくるのはたいてい昼の12時すぎ。
俺がコンビニから昼メシと「鉄マッスル」(ドリンクタイプ)を買ってきて、
二人で遅い朝メシ、というのが日課になっている。




なあ、アマネ。AKBというのはどうしてこんなにたくさんいるのだ?


ジルは25年の空白を、主にワイドショーやDVDで埋めている。
種村さんはジルの部屋にパソコンを運び入れたが
(驚くことにこの吸血鬼は25年前にパソコン通信をしていたのだそうだ。何だ!パソコン通信って!)、
ジルとしては動画というものにはまだなじめず、テレビを見るほうがやっぱり好きなんだそうな。



さあなー、こんだけいると自分の好みの女の子が一人は見つけられるからじゃないのかねー





お気に入りが見つかっても前のほうにいなかったら探すの大変だな





そう思っちゃったらもう相手の思うツボなわけよ。自分の推しメン…ええと、応援してる女の子を少しでも前に出したいじゃない?





ほうほう





そうすると、ファンはその子のためにCDをいっぱい買って、金出して投票して、女の子がセンターになるように尽くすわけ





ふうむ、なるほどな。
ヴィクトリア女王のころは舞台女優やバレリーナにそういうパトロンが山ほどついていたものだ。
時代が戻ったらしい。


戻りすぎですね。
こういう時のジルは、吸血鬼というより完全に独身のアラフォーだ。
なんとなく感じてはいたが、奴はまるっきりゲイというわけではないらしい。
AKBも嵐もジバニャンも好き。美しいものや、カワイイものがとにかく好き。



なんかの小説で、吸血鬼は処女の血しか吸わないとか読んだけど


アイドルに顔がゆるみっぱなしの吸血鬼に、俺は頬杖をつきながら何気なく問いかけた。



あんた見てる限り、そんなわけでもなさそーな





処女の血……


オッサンはつぶやくと同時に
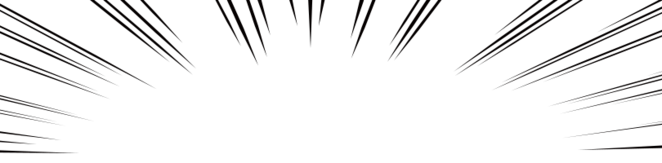

盛大に腹の音を鳴らした。むしろ屁かと思うほどの轟音!



そりゃお前、処女の血に勝るものはないさ


振り向いた吸血鬼は、ひどくみじめな表情をしている。



でも、いないし





待て待て待て待てテレビ指しながら言わないで!炎上する!





もうかれこれ半世紀近く処女断ちしてると、すっかりその味も忘れてしまった


なんか禁酒中のおっさんが最後に飲んだウィスキーを思い出しているような。



バーサンの血を吸おうとは思わなかったの





思うに決まっている。踏みとどまるのは至難の業だった


吸っちまえばよかったのに、と心の中で思う。別に、あの因業ババアが吸血鬼になったって、
あんまり変わらないような気がするのは気のせいか。



だがまあ、基本的に吸血鬼は鉄分とオドを摂取さえしていれば滅びることはないのだ





オド?





オド……言い換えればエロスだな。エロい妄想やエロい雰囲気だ





エロい妄想……


どういう仕組みなんだ。



人間というものは、エロいことを考えるときに強いエネルギーを発する。それがオドなのだ。
東洋では「気」とか「精気」とか「波動」とか呼んでいるな。
我々吸血鬼はその人間の気を吸って生きるのだ。





気……はよく言うけども、あれってエロいことを考えると出るもんなの?





気を出す方法はいろいろあるさ。その中で最も簡単なのがエロい妄想だと思えばいい


俺の頭の中で

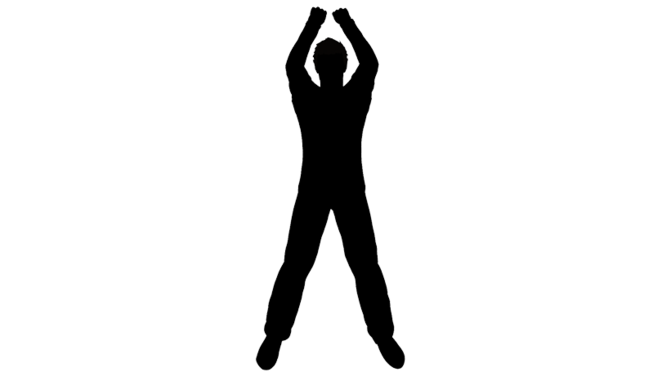



昇龍拳!!!


や、

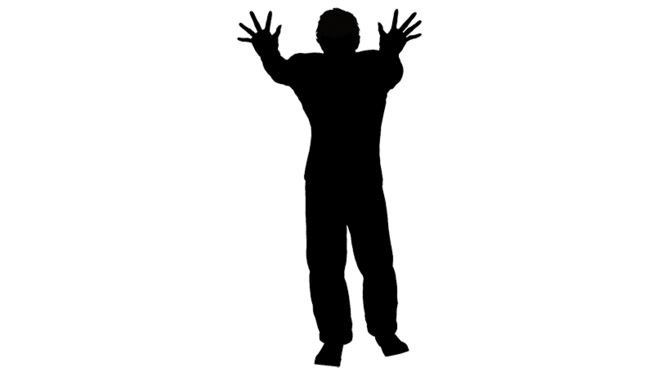



波動拳!!!!


といった気系の波動砲が頭をよぎった。
いやだ!
あれがエロい妄想で出てるものだと思いたくない!



人間のエロスというものはすごいものだ。
肉体を超え物質にも宿る。
だから私はエロ本だのエロDVDだのを常食にして、人を傷つけることなくオドを摂取しているのだ。


そう言うと、なんかストイックに聞こえてしまって悔しい。
ようするにこのオッサンは毎日サプリメント飲みながらエロいもの見てるだけなんだが。



これは必要最低限の栄養でしかない


ふいに、ジルがテレビから俺に視線を移した。



私にとっては仕方のないことだが、
アマネはどうしてそうしている?





へ?


急に話題を自分に振られ、俺は一瞬何を聞かれたか理解できなかった。



私と一緒になって、暗い家で乾いた食べ物ばかりを食べている必要はない。
お前は自由に外に出られるのだから、
もっと愛情を求めに外に行けばよいのだ。





愛情を求めにって


俺は薄ら笑いを浮かべながら首を振った。



そんなこと考えたこともなかった。
え、何、ナンパしに行けってこと?





例えばナンパもありだろう


25年前にもナンパはあったそうです。



どんな方法でも、恋をしたいとは思わないのか


外国人ってすごい。
中世から生きていればなおさらだ。
こういうこと真顔で言うもんな。
昔の少女漫画か!
…いつもの俺なら激しくツッコミを入れるところなのだが、
なぜかその時は、ジルのまっすぐな言葉が胸に突き刺さってしまって、
喉がつかえたように、言葉が出なかった。
それは予感だったのだろうか。
リ・ゴーン。
チャイムが鳴った。



種村さんかな


俺はその場から逃げるようにして、いそいそとリビングを抜け出した。
種村さんだったらいいなと思った。
なんとなくこれ以上ジルと深い話をするのはやばいような気がしていたんだ。
俺に欠けている何かを認めるような気がして。
だが、玄関に立っていたのは種村さんではなかった。



………え





………





……七星………





……おひさしぶり…です……


そこにいたのは、渋澤七星17歳。
俺の従妹。
学校の帰りなのか、
知らぬ間に降っていた雨の中に所在なさげに立ちすくんでいる制服姿の七星は、
俺がその先一週間忘れられないくらいに、可憐に見えた。
のだが、
その後ろからぬるっともう一つの影が現れた。



ごきげんよう、普様。アポも取らずに申し訳ございません。今お時間よろしゅうございますか


七星の女執事、北鎌倉。
俺とジルの平和な午後は、この時終了した。
