もしも
誰もが知る童話に幾つかパターンがあるとしたら
もしも
誰もが知る童話に似て非なるものがあるとしたら
もしも
誰もが知る童話に幾つかパターンがあるとしたら
もしも
誰もが知る童話に似て非なるものがあるとしたら

これは世に広まる
誰もが聞き知った童話の
『ありうるかもしれない』
可能性を組み込んだ
異説・寓話の類である
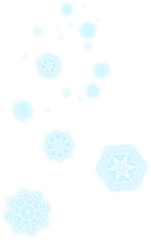
それは毎日絶えることなく雪が降り積もり、やっと雲が消えて星々がきらきらと微笑みを見せる夜のことであった。
ある国の城ではパーティーが行われていた。
賑やかな広間以外は警備兵や下働きの者を残すだけで、最低限に灯りを点されている城内は水を打ったように静まり返っていた。
しかし、あるひとつのドアへと手をかける人影があった。
人目を気にしているのだろう。手にしたランプをかざし、息をひそめて注意深く辺りを見渡している。自分以外の気配がないのを何度も確かめ誰もいないと確信してから扉を人ひとりが入れる程度に開く。
その隙間に身を滑り込ませるようにして中へと入っていった。
室内は天井から垂れさがった布で何重にも遮られていた。明りはなく、窓もない。厚くもしなやかな布に幾重も覆われ、手元のランプだけが頼りの空間だった。
だが忍びこんだ人物は慣れた手つきでかき分けていく。
最後の深紅の布をくぐって辿りついた部屋の最奥には小さな机と、似た赴きであつらえた背凭れ付きの椅子がひとつずつ置かれていた。そして、行く先がないと告げる壁には古めかしくも、立派に磨かれた鏡が飾られていた。

それは侵入者の頭の先からへそまでを映すほどの大きさであった。
影は机にランプを置き、鏡の前で手を翳す。目の前にある鏡にだけに聞こえるように、ゆっくりと澄んだ声で囁いた。



鏡よ、鏡……


緩やかな手の動きに合わせ、平らな鏡面が波を作る。何度も往復させた後、最後に何もない空間を摘むように指を引いた。
歪んで映り込んでいた己の顔は消え、代わりに白い仮面を付けた青年が現れた。
薄ぼんやりと浮かぶ姿で低く落ち着いた声を部屋に響かせる。



……はい、お后様


鏡の精は怪しい人影を后、と呼んだ。
この部屋で唯一点される淡い橙色の明りに浮かび上がるのは、まだ若くとも聡明な女性の横顔。
まごうことなき、この国の女王だった。



鏡、私は……綺麗かしら





勿論ですとも、ですから……


鏡は真実を告げるというよりは何かを諭すように、言葉を続ける。



ですから、そんな顔をなさらないで
今宵は祝いの席ではありませんか
妃である、貴方様のご懐妊を祝した





だから……と言ったら?


ランプの心もとない光を頼りに彼女は注意深く椅子に腰掛け、ゆったりとしたドレスの上からでも妊婦とわかる自分の腹を撫でた。



祝福されているのは宿ったこの子。私の妊娠ではないわ
この国の王の血を受け継ぐ者が生まれるから、皆が祝辞を述べてくる……私でなくてもよかったという者だって、一定数いるわ


彼女は昔からこうだった。普段は王妃として凛と顔を引き締め、民に雛菊のような優しさを放っているが時々落ち込みやすく、憂鬱になることが多々あった。
どちらかといえば、お人好しな王妃は人から相談される側だった。
自分の弱みを見せるよりも、他人の苦しみや悲しみを和らげることが大切だと考えていた。彼女はそれが自分の長所でも短所でもなく、自分自身が最低でも出来ることをしているだけだと譲らなかった。
気苦労を背負っても他人に見せようとしない彼女の唯一の相談相手は、目の前の魔法の鏡だといっても過言ではない。
これは代々彼女の生まれた城に伝わっていた古い鏡。何百もの年月によって命を宿した鏡だった。
当時、倉庫で埃にまみれながら眠っていた彼を見つけたのはまだ姫と呼ばれていた、遠い日の王妃であった。
飾られることで化け物と周知されてもなお、大切にしていたのも彼女だけだった。
鏡は大切に接されるにつれ、幼くも聡明な相手の心を知り、いつの間にか相談を持ちかけられるようになっていた。
幼い頃から共にいるなのらば、扱いに慣れていてもおかしくはない。
彼がくれる言葉は、彼女が少女でだった頃から自信や希望、ひらめきを与えてくれるものだった。
質素だが幸せな国の王女として生まれた彼女は姉妹や兄弟の中でも、一番整った目鼻立ちに聡明さと純粋さを兼ね備えていた。
ある時その噂を聞きつけた、さる大国の王から求婚の申し出があった。そこは自国の数倍の規模と面積を持ち、比較にならないほどの富と兵力を所持していた。返答次第では国の運命がかかっている政略結婚だった。
両親は悩んだ。若い姫に現実を突きつけたら嘆き、悲観するかと思っていた。しかし彼女は文句の一つも言わなかった。
それどころか自ら王の元に出向き、笑顔でこう答えたのだ。



婚約を謹んでお受けいたします


弱い故郷の己の立場を理解し、痛感したのだろう。
断れば国と共に一族は滅びてしまうかもしれない。自分が行くことで解決するのなら、喜んで向かおう。
その代わり、大切にしていた鏡だけは嫁入り道具に入れるよう頼んだ。王にも誰にも知られぬような部屋を探し、彼をそこに立てかけた。
鏡は孤独な王妃の話し相手となった。王の愛を疑ったとき、心ない中傷に傷ついたときは打ち明けられ、力になる助言や言葉を返した。民や家臣が認める女王になった今でも、夫と家族同等、それ以上に己を晒せる相手は鏡以外にいなかった。
きっと今回も良からぬ噂を耳にしたのだろうと、鏡は感じていた。
悪阻が酷く此処に来ることもままならないことは鏡から視えており、伺い知ることは出来た。安定期に入り、パーティーに出席できるほど体調は回復したが、胸の内にため込みやすい王妃に油断と負担は禁物。心労が祟って産まれてくる命や彼女自身に危険が及ぶ可能性も高いはずだ。
優しく賢明で、不器用な王妃の不安を拭うように、鏡はゆっくりと語りかける。



でも、嬉しいのでしょう
自分を愛してくれる方の命を分けられた子を
産めるなんて





ええ……とても


目を細め、穏やかに微笑む顔には慈愛と喜びに満ちていた。彼女のも女性、我が子を憎んでなどいない。政治の道具として扱われたことを思い出し、不安になっているだけだ。



貴方も小さな命も、祝福されることに違いはありません
皆から喜ばれ、貴ばれているのはお二方です





有り難う、貴方にはいつも励ましてもらってばかりね





いいえ、それが私に出来る全てです
それよりも、どんな方がお生まれになるのでしょう
私も楽しみにしているのですよ





そうね……


王妃は昨日、王と穏やかに過ごした夕べの出来事を思い出した。
暖炉にくべた薪が耳障りのいい音をたてる。
暖かな部屋で二人は窓際のソファーに座り、王は読書を、彼女は針仕事に勤しんでいた。
まだ見ぬ我が子への想いを一針一針に込めていたが、暖かさにまどろみ、瞼がゆっくりと重くなっていく。完全に閉じられる間際、指先から走った小さな痛みに意識は引き戻された。
赤い滴が指先で玉を作り、指の腹の上に広がる。
それを見た王妃は隣で本と向き合う夫に声を掛けた。



もし――――


もし、この子が産まれてきたのなら。
庭に積もる雪のように白く滑らかな肌を、
窓枠の黒檀のより艶やかな黒い髪を、
指に滲む血の如く真っ赤な瑞々しい唇を持った、
そんな素敵で、
素晴らしい子であればいいと思いませんか?



そう話したら、あの人も嬉しそうに頷いてくれて


王妃はさっきまで沈んでいたとは思えない、大輪の華のような笑顔で鏡に語っていた。
彼女はこうでなければ。
鏡の声色もさらに柔らかくなり、彼女の背を押す言葉を紡いだ。



お后様、とても素敵な笑顔になられましたよ
さあ……皆様がお待ちになっています





有り難う、またパーティーの様子も教えるわ





お気遣い、痛み入ります。
ですが私は鏡の精です、きちんと見ていますよ。
此処からでも、どこであっても……
何時いかなる時であろうと、私は貴方様の味方です


彼女からの今日二回目の礼に鏡の精はおどけたように締めくくり、姿を消した。

鏡面は何事もなかったように、王妃だけを映し出している。その顔は母として、女性として誇りに満ちている。
王妃もランプを手にし、カーテンを潜って何食わぬ顔でその場を後にした。彼女しか知らぬ、彼女の心内を知る彼の場所を。
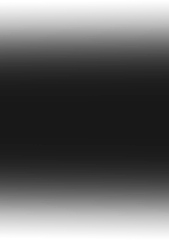
だが、愛しい想いはいつか砕けることとなる。鏡の精でも未来で起こりうることを見ることは出来なかったのだ。
後々の彼女の生活、人生は一変した。
美しくも醜悪な娘、白雪姫によって……――
