ヤー君は天才だった。
私は凡人だった。
ヤー君は天才だった。
私は凡人だった。



ミホちゃん


低い声で名前を呼ばれた。真夜中の、暗い道で。とっさに構えながら振り向くと、学生服の男性がそこにいた。電灯に照らされた彼は、



やっぱり


と微笑んだ。目尻が柔らかく下がる。
不思議と怖くはなかったけれど、それでも、警戒はしてしまう。



会えた





……どなたですか?


とりあえず危害は加えられないようだと思いながらも、私は身構えたままだ。



わかんない?





……残念ながら


新手のナンパ? いやいや、こんな地味な女性を、こんな夜遅くにナンパはないだろう。
辺りには誰もいない。電灯が、じじ、と頼りなく頭上で鳴っている音以外、本当に何の音もしない、静かな空間なのだ。



ヤスだよ、十年ぐらい前、隣に住んでた


男性は、困ったように笑った。まだ分かんないかな、とでもいいたげだ。



ヤス……


隣に住んでた。私は数秒考えて、記憶の底の方から、幼い少年の笑顔を思い出した。
笑顔が一致する。言われれば、面影もある。



ヤー君?





そうだよ、久しぶり!


手を広げ、彼は私に抱きついた。あれから十年。
彼はおそらく、十八歳ぐらいだ。三十路である私の体温が一気に上昇する。
彼は私とは対象的に、とても冷んやりとしていた。



わ、本物だね、夢では触れなかったんだよ


ふわりと思い出す。
こういう言葉の使い方。きれいな、素敵な……私にとってみれば、天才的な、世界の見方。表現力。
本当に本当に、羨ましかったのだ。



ヤー君……すごく久しぶりね。いつ戻ってきたの?


ゆっくり彼を引き剥がしたが、彼は私の腕を両手でしっかりと握りしめたまま話さない。
密着した距離で触れあっている。



さっき


白い歯を見せて笑う。なんだか照れくさくて、私は彼の後方に視線をずらした。



さっきかあ。私を、夢に、見たの?





そう、それで、ミホちゃんに会いたくなって飛んできちゃった。
聞かなきゃならないことがあってね。でも、あんまり時間がないんだ


早口で彼は言う。
切羽詰まっているような口調に、私は不安を覚えながらも、じゃああそこで話そうかと、公園のベンチを指差した。



ベンチ? それよりブランコがいいな、空に近くなれるから、空気が綺麗だよ


幼いころの中身のまま、外見だけ変貌してしまったような無邪気さがそこにはあった。
懐かしい。私は彼に、幼い彼に、何度嫉妬したかわからない。
彼と対峙するとき、私はいつでも自分のつまらなさを突きつけられていた。君にはこんな表現方法ができないだろう、と何かに言われている気がいつもしていた。
私にとって、夢で触れられないことは、残念なことでもなんでもない。
ブランコは、空に近づくためのものではなく、子どもの遊具だ。



まだ、言葉の選択で嫉妬するんだ


私は、静かに一度、目を閉じる。未練、たらたら。
世界を、美しい言葉で紡ぐことなど、あきらめた、はずなのに。



――いいね、空に近づこうか


私が同意すると、彼は嬉しそうにブランコに向かった。
ブランコに乗って、彼は勢いよく立ちこぎをはじめる。
古くなったブランコが、ミシミシと音を立てる。壊れるよ、と言おうとしたとき、ヤー君は



ねえっ


と大きな声を出した。



夢の話、してもいい?


先程言っていた、私が出た夢のことだろうか。



いいよ。どんな夢見たの


言うと、あはは、とヤー君は首を降る。縦に揺れながら横に首を降って、もう大変なことになっている。



危ないよ、ヤー君





大丈夫。夢って、ミホちゃんの夢の話!





私の夢の話?


心臓がドックンと大袈裟なほどに跳ねる。



そう、訊こうと思ってたこと。ミホちゃんの本は、まだ出てない?


私の本。胃がぴり、と痛む。彼の記憶力に驚愕する。
返事ができない、どうして覚えているのだろう、あの日の私の言葉を、夢を。



……もう、書いてないの


えっ、と彼は顔をこちらに向ける。勢いよくこぎながら、



そんなあ


と叫ぶ。
私は身構えた。非難されると思ったのだ。やめてしまえるほどの夢だったのか、がっかりだ、と。
しかし、違った。彼は分かった、と言って、一人でそうかそうかと笑いはじめたのだ。



何が分かったの?





記憶喪失でしょ?


間髪いれずにそう言われ、私は言葉を失う。



……へ?





記、憶、喪、失!
なっるほどねー、そうきたか


勝手に納得している彼をよそに、私はぽかんとしながら小さく



なんで


とつぶやいていた。その声は、彼に届いていなかったはずだ。それでも彼は、返事をするように高らかに言った。



だって、小説家になるって夢を、ミホちゃんが忘れるわけないもん!





……それは


特別な言葉ではなかった。
それでも、私の胸に、その言葉はざくりと深く、食い込む。
今までのどの言葉よりも深く、深く、沈んでいくような感覚だった。
ヤー君みたいな発想力も表現力もなく、言葉の渦に飲み込まれ、もう無理だと夢から顔を背けたのは、五年も前のことだ。忘れてはいない。夢を、私は捨てただけだ。



私は……


言いよどんでいるのを、ヤー君はとても肯定的にとらえたようだった。



もうすぐ思い出せそう? いいね、ゆっくりでいいんだよ


そうじゃない、と言うことができなかった。
なにも言わずに、ふわふわと夜を縫うようなブランコを、ぼんやりと眺める。



ミホちゃんが聞かせてくれた物語、すごく好きだったよ。空飛ぶ船に、虹色の妖精、笑う傘に、甘い雪


ひとつひとつ、思い出す。忘れるわけがなかった、私の世界。
他にも、覚えてくれている人がいるなんて、夢にも思っていなかった。



……よく、覚えてるね





あんな素敵な物語と夢、忘れる人が変なんだよ。そうだよ、ミホちゃんは、変なんだよ


ヤー君の方が変だろう、と思って笑うと、よかったと微笑まれた。



笑顔も忘れたのかと思った


そんなに笑っていなかっただろうか。問う前に、彼は前を見つめたまま、



時間だ


と真剣な表情でつぶやいた。真っ暗な暗闇をじっと見つめている。



僕、すぐにまた引っ越すんだ。
引っ越した先には、宇宙一大きな本屋さんがあるんだよ





宇宙一?


面白い例えだ。そう言おうとしたが、言いかけて、飲み込んだ。彼の表情は、とても真剣だったのだ。



うん、絶対にね。
宇宙一、大きいんだよ――僕は信じてる。
だから、ミホちゃんの本も絶対に読める。
記憶、戻ったよね?





え……





さっき、よく覚えているねって言ったとき、懐かしいなって顔、していたから。
素敵な表情だったよ





……本当に?





嘘はつかないよ


ヤー君は、さあて、と息を大きく吸い込んだ。



そろそろ行かなきゃ。ミホちゃん、約束だよ。どうか、本を書いて、僕に読ませてね


彼は膝に力を入れて、ぐんとまえに大きくこいだ。そして、闇に向かって、手を離し、飛んだ。



またね、バイバイ!


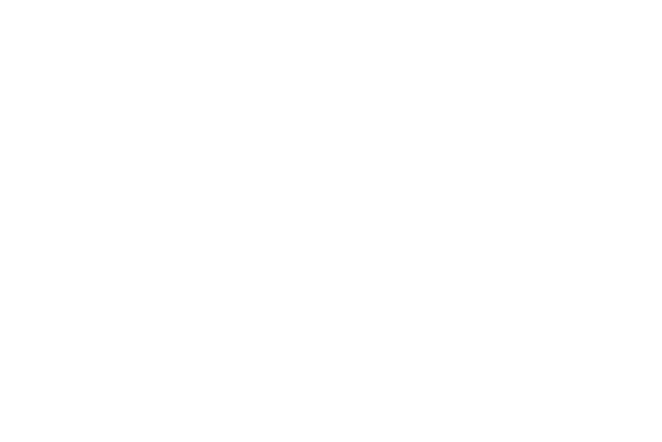
月明かりに照らされながら、ヤー君は白い光になって消えた。
うそ、と呟く私の声が遠くから聞こえる。白い光はきらきらと上昇しながら、星空に消えていく。



ねえ、お母さん、ヤー君って覚えてる?


電話の向こうで、あら、と母が驚いた。その後、母が何と言ったかは覚えていない。
ただ、断片的な単語のみが、今でも記憶の中心にある。
私はその後、再びペンをとった。相変わらず拙い文章だが、それでも、一度は捨てた夢を掴むために、そしてヤー君のいる世界の本屋に私の本を届けるために、物語を書き続けている。
母の言葉。
ヤー君、病気、もうすぐ。
もうすぐ。
今でも、一人机に向かって泣きだしてしまうことがある。
ヤー君は引っ越すと言っていた。
そうだ、引っ越しだ、と自分に言い聞かせる。彼は引っ越したのだ。星の向こうに消えるようにして、引っ越していったのを私は見た。
記憶を取り戻した私は、彼へ届くようにと、今日も物語を編み出すのだ。
またね、と彼は、確かに私に言ったのだから。
了

TAKAYA様>コメントありがとうございます! 短い作品ですが、その内容を汲み取っていただけて本当に光栄です……! 楽しんでいただけたのなら本当によかったです、ありがとううございます!