――目の前で、日常が崩れ落ちる感覚を味わったことがあるだろうか。
――目の前で、日常が崩れ落ちる感覚を味わったことがあるだろうか。
真っ逆さまに叩き落されるような、それでいて何時まで経っても地面に足を付けることが出来ないような不快な浮遊感。
『ねぇギコ君、聞いてるの?』
『聞こえている。当たり前だ。』
彼は今担当している事件の事で手いっぱいだった。いつもなら見ている人間の方が恥ずかしいと思えるほどの会話まで交わすこともあるというのに、その時だけはたまたま考え込んでしまうような事件の担当だったのだ。
『ねぇギコ君、あの子供、ちょっと危ないよ』
『ん? ああ、確かに。親御さんはどこへ行ったんだか』
それが運命を分ける会話だったと、当時の彼は気付いていない。ただただ彼は、生返事をするだけである。
『ねぇギコ君! あの子!』
『え?』
切羽詰まった椎の声に、漸く彼は我に返る。しかし、運命は既に決まった後だったのだ。
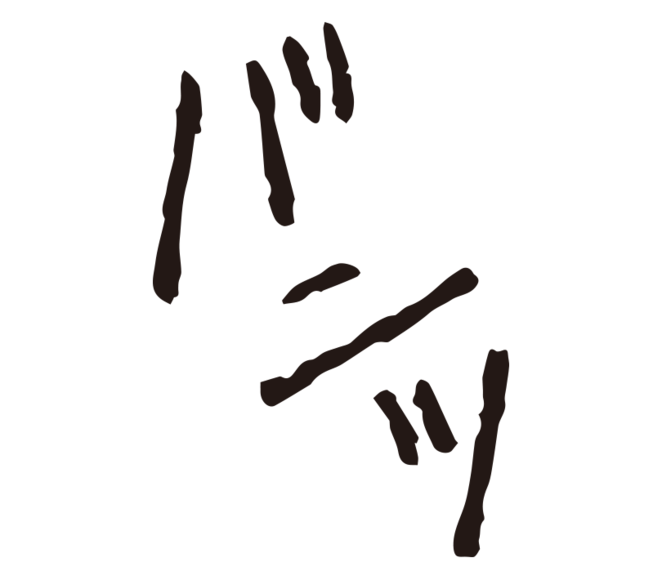
広がる赤。
赤。
赤。
赤。
一瞬にして、彼――埴谷義己の日常は奪い去られた。そして、それは今も彼の網膜に焼きつき、彼が自信を保つために記憶を歪ませた今でも、目を閉じれば彼女の顔が現れる。
美しかった瞳は濁り、空虚に埴谷を見つめるその視線。
『どうして、私の話を聞いてくれなかったの』
その瞳がずっと、埴谷にそう語りかけている。少なくとも彼はそう思った。救急車を呼ぶことも忘れ、辺りから悲鳴が飛び交う。いくつもの事件に相対した彼が、何も出来ずに立ち尽くしたのはこれが初めてだったかもしれない。



埴谷警部? 大丈夫ですか?





え? あ、ああ……。


恵司がプログラムを直した後、埴谷の元に向かった音耶は資料室で一人ぼーっと立っている埴谷を見つける。疲れのせいだと言いたいが、椎の話をした後では音耶もそのせいとか思えなくなってしまう。



ごめんね、ただいまギコ君





おかえり、椎。……にしても、お前らにバレるどころか椎と仲良くなるとはな





え? ああ、そう、ですね


埴谷の中で彼女が死んだという記憶は消えている。だからこそ双子が埴谷と椎の関係を知った経路が彼の中ですっかり書き換わってしまっているのだ。元々埴谷自身が彼女の死の際に音耶に伝え、それを聞いた恵司が埴谷のためにプログラムを作るというのが正確な流れだった。しかし、埴谷の中では何かの拍子に椎の事を知った音耶が恵司にバラしたという話になっている。それでも仲に亀裂が入らないのは椎の言動のおかげでもあろう。
周りに誰もいないことを確認し、椎が起動しているパソコンを埴谷に差し出す音耶。埴谷はそれを大事そうに抱え、ぎゅっと抱きしめる。



調子は戻ったか、椎





うんっ! ……えへへ、音耶さんがいるし、やめてよギコ君





そうだな、一応仕事中だったな


もし椎が生きていればここまで見せつけられることに「リア充爆発しろ」、等の言葉位言えたかもしれない。だが、言えないのはその様子の異常性故だろう。パソコンを愛しそうに抱く友人の姿はあまり見ていて笑える光景ではない。



すみません、お二人の邪魔をして。それで埴谷警部……何かわかりましたか?





ああ。過去の事件から似た痕跡を見つけた。後は調べればあいつがやったという証拠が出るだろう





それはよかった。ごめんなさい、あまり私は出来る事がありませんでしたね





椎と仲良くしててくれただけで十分だ。それに、こいつが急に仕事を見たいなんて無茶を言ったのに、お前がなんとかしてくれたんだろう?





あ、あはは……そうですね


実際何か許可を取った訳ではない。仕事場にパソコンを持ち込む程度であれば問題は無いのだ。別にそれで何か仕事関係の事をする訳でもなければ、データを移そうとしているわけでもない。何か重要な情報が漏れるとも思えない使い方しかしないのであれば隠れてでも出来るだろうと音耶は判断したのだ。埴谷にはこのパソコンは椎に見えているのだから、そんなこと出来るはずもない。
真面目な埴谷がルールに対してルーズになったり当然拒否すべきものを肯定してしまうのは椎への過剰な愛故なのか、それとも実際は彼女が人間でないと理解しているからなのだろうか、と音耶の頭にはそう過った。



ねぇギコ君、やっぱりギコ君ってカッコいいね! 警察官なんて、たくさんの人を守ってるんだもの!


椎のその言葉に、埴谷がぴくりと今までとは異なった反応を見せたのを音耶は見逃さなかった。しかし、彼はすぐさま元の調子に戻る。



だけど、一番守りたいのはお前だよ、椎





……ギコ君


単なる恋人の会話のそれではない重さを感じた音耶は、一度資料室を出た。彼らに配慮したというわけではない。ただ、この二人を見ていることは、まだ心のある殺人鬼にとってこれ以上無い苦であったのだ。
